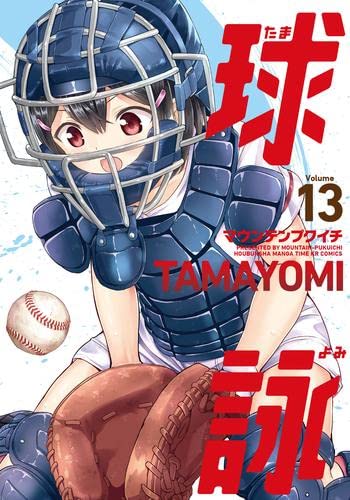球詠アフター【第73話から分岐するIF】

注)当小説は「こんな未来もあるかもしれない」というIFを描いた同人作品です
本編とは作中団体名などが異なるパラレルワールドと理解して下さい
記事ページではく固定ページですので、コメントはできません

球詠アフター
~第73話から分岐するIFの未来~
- 球詠アフター【第73話から分岐するIF】
- ◆Chapter01:最後の夏が終わって
- ◆Chapter02:世代最高の二遊間コンビ
- ◆Chapter03:大学野球での再会
- ◆Chapter04:フリーバッティング
- ◆Chapter05:プロ注だったライバルの今
- ◆Chapter06:ドラフト会議
- ◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その1
- ◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その2
- ◆Chapter07:キャッチボール
- ◆Chapter08:姉と妹
- ◆EXTRA:柳大川越アフター
- ◆EXTRA:主将・岡田 怜の休日
- ◆間幕:菫と稜
- ◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その3
- ◆Chapter09:新越谷高校受験勉強部
- ◆間幕:絶対王者
- ◆Chapter10:母校凱旋
- ◆EXTRA:瑞帆VS詩織
- ◆間幕:京子、蘭々、美咲の絶望
- ◆Chapter11:それぞれの想い
- ◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その4
- ◆Chapter12:同窓会
- ◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その5
- ◆Chapter13:年末年始
- ◆Chapter14:希の開幕
- ◆Last-Chapter:卒業式――たまよみ(珠✕詠)
- ◆EPISODE:後日談 ~27歳の秋~
- ◆EXTRA:続・YouTuber中田奈緒(前)
- ◆番外編:息吹のキモチ ~26歳の冬~
- ◆EXTRA:続・YouTuber中田奈緒(後)
◆Chapter01:最後の夏が終わって
――息吹、高校3年の秋。
202X年10月19日。
新越谷高校3年生、川口息吹と大村白菊の2人は早朝から快速電車に揺られていた。
理由は皇京大学硬式野球部の練習に「特別課外実習」という名目で参加する為である。合宿の日程は月~金の4泊5日だ。
合宿期間中は野球部専用寮に泊まる。
白菊は特待生での、息吹はスポーツ推薦枠での来春入学が内定しているからだ。
大学側からの誘いに新越谷高校が乗った形である。
実習としての内実は「入部が確定しているので少しでも多く、そして少しでも早くから練習に参加しろ」だった。
流石は野球の名門大学である。
始発に乗っているので、電車は空いていた。
白菊が息吹に話しかける。
「そういえば、怜先輩と理沙先輩に会うのって夏の県大会決勝以来ですね」
「春とは違って夏の全国大会の時は、先輩達も大学リーグでこっちに会いに来られる余裕なかったものね」
「凄いですよね、2人共」
「1年春からレギュラーで、キャプテンはリーグ最優秀選手で理沙先輩はホームラン&打点の二冠王、か」
今や大学野球界のスター選手の仲間入りだ。
息吹にとって岡田 怜の活躍は誇らしかった。
むろん藤原理沙の活躍も嬉しい。
「新越谷で活躍した時も凄かったですけれど」
「あの頃はヨミと希が目立っていたから」
「高校時代よりもプロのスカウトからの評価がグンと上がって、3年後のドラフトが楽しみです。2人とも上位指名、間違いなしです」
「ドラフトといえば、明日が希の運命の日ね」
「球団の公言通りにハドバンが単独1位指名で、そのまま希望球団にプロ入りですよ。心配いりません。希さんもいよいよプロです」
今年のドラフト会議。
高校生で1位指名が確実視されているのは3名。
4~6球団の競合が予想されている美園学院の諸積恋美。埼玉京武ライオンズが単独指名すると目されている咲桜の松井遥菜。そして福岡ハードバンクホークスが1位指名を公言済みで本人も「他の球団ならば大学進学」と表明している新越谷の中村 希だ。
「――ヨミさんは後悔していないのでしょうか?」
白菊の声が憂いを帯びる。
春夏連覇の全国優勝投手。6球団から調査書が届き、ドラフト候補(予想は3巡目か4巡目)に挙がりながらプロ志望届を出さなかった武田詠深は、大学野球に進む。
しかも、なんと弱小の珠川大学を選んだ。
皇京大学と同じ首都大学リーグのチームであるが、1部の皇京大学とは違い珠川大学は2部リーグなのである。
これにはマスコミと高校野球ファンは驚いた。
ドラフト候補の詠深ならば強豪大学を選び放題だった筈なのに。
「珠姫、菫、稜と同じチームっていうのを最優先したんだから後悔なんてないでしょ」
詠深は、大学で山崎珠姫と野球を続ける為に高卒でのプロ入りを選択肢から外す。
その選択に、藤田 菫と川﨑 稜が付き合った形である。
この2人は2人で、色々と思うところがあっての進路、詠深と珠姫と同じチームでの挑戦に違いない。何故ならば最後の夏大会、自分と白菊とは違い2人は――
「最後の夏、予選から全国まで私はトップ固定で、白菊は4番固定だった」
白菊の運命の分岐点、分水嶺。
1年目秋大会の準決勝で放った、代打同点スリーランホームラン。バックスクリーン最上段に突き刺した超特大の一発だ。上位打線がエース園川 萌をマウンドから引きずり降ろし、リリーフ直後の初球を捉えた快心の一撃は、美園学院の2番手・黒木亜莉紗を完全に粉砕する。続く珠姫もヒット。そこからストライクが入らなくなり、連続フォアボールでワンナウトも取れずに降板。スクランブル登板となった3番手・小宮山は新越谷上位打線に捕まる。5番・川原のダメ押しホームランから、2打席連続となる白菊のレフトスタンド中段へのソロホームランで、観客は大爆発した。
ビッグイニングで美園学院を大逆転にて下す。
2打席連続の特大弾で白菊は有名になり、本人の自信も各段に上がる。
新越谷と美園学院の立場が逆転した試合だった。
決勝も梁幽館を返り討ち。秋の県大会を制したのである。
「1番が息吹さん、2番が希さんのコンビは本当に良く機能しましたね」
「でも、新越谷での私の打順は、きっと下位打線が私的ベストナイン」
息吹が呟く。
1番が希、2番が菫、3番がキャプテン、4番が理沙先輩、5番が珠姫、6番が白菊、7番が私、8番がヨミ、9番が稜。それが――最高の私的打順。この打順が新越谷。
「楽しかったですね、人数ギリギリだった頃」
「またあの頃みたいにキャプテンと野球ができる」
待ちに待っていた時間がやってくる。
自分が最高学年だった2年の秋以降よりも、怜がいた頃の方が楽しかった。
それは希も一緒だったと感じている。
新2年生の春に念願だった全国出場を果たし、そこから4期連続での全国出場。3年の春夏は連続制覇。そして希が慕っている川原 光が部活引退した後、希は目標を失った様になっていた。練習も「今よりも将来を見据えた」個人メニューに偏り、主将になった芳乃も黙認する。2年生1年生から不満があるのは分かっていたが、3年生の自分たちは希の気持ちを優先した。チーム練習への参加は最低限だったが、それでも希は全国で活躍した。全国区で天才打者と名が売れる。だが、希は明かに高校野球に対し2年生の頃の様なモチベーションが欠けていた。5割以上簡単に打ててしまう投手の球を打つ事を時間の無駄と思っているのを、息吹は心が読めるかのように感じていた。
実質、手抜きに近かった高校3年の希。
(それでも打率6割オーバーだったけど)
モチベーション全開なら、きっと7割打っていた。
(ま、2年の秋からU18日本代表チームの方が希のメインになっていたし)
怜たちが引退後の新チームは、希1人が抜けても大丈夫な程には選手層が充実する。
息吹も3年春と最後の夏の全国は、怜たちと出場した全国ほどの感動はなかった。
怜たちとの全国は春夏共にベスト4敗退。3年春・3年夏は春夏全国制覇だったのに。マスコミは新越谷の春夏全国連覇に「王者・新越谷の黄金時代が到来」とフィーバーしたが、それも遠い過去に感じる。なぜならば――
どこか冷めて他人事めいていたのだ。
2年生の頃よりもずっと実力をつけて、そして大活躍して強豪大学が刮目する個人成績を残した筈なのに、2年生の頃に戻りたいとすら密かに思った。
けれども再び――
「またキャプテン達と一緒に優勝したい」
「ふふっ。怜先輩が例外的に新2年生の来春で新キャプテンに内定しているって、なんだか運命を感じます」
「運命?」
白菊は上品に微笑む。
「はい。きっと息吹さんにキャプテンって呼んでもらう運命ですよ」
◆Chapter02:世代最高の二遊間コンビ
皇京大学野球部専門寮に到着した。
名門校だけあり、洒脱なマンションといった外観だ。
規模も大きい。
「来年度の新入生の、大村と川口だよね?」
綺麗なエントランスホールの前。
ジャージ姿の野球部所属と思われる学生が息吹と白菊を出迎えた。
「私は3年、来年は4年の笹川。案内役だよ」
「大村白菊です」
「川口息吹です」
2人は丁寧に腰を折った。
「知ってるよ有名人。TVで活躍しているの何度も観たし。全国大会通算8ホーマーの大砲・大村白菊に、全国通算盗塁数18で失敗ゼロ、4大会で通算出塁率6割3分の「天才」川口息吹」
「恐縮です」と、白菊。
「天才はオーバーですよ」と、息吹。
笹川は息吹と白菊を先導する。
その背を追いながら息吹は訊いた。
「入学前に練習に参加する新入生って、他にもいるんですか?」
「ううん、今日はあんた達だけ。他の推薦組は年明け。セレクション組は希望すれば2月からかな。ってか、他の推薦組は審査中でまだ内定出していないし、セレクションが行われるのは来月だ」
息吹と白菊は顔を見合わせた。
背中越しに笹川が言う。
「この時期からの練習参加は初の特例だよ。新越谷出身の岡田と藤原が大活躍したからって感じかな」
「岡田先輩って来春からキャプテンなんですよね?」
白菊の確認に、笹川は足を止めて首肯した。
「3年前に監督が代わってから、ウチは超実力主義になった影響だね」
新2年生が主将は、野球部史上初かつ異例中の異例との事。
それだけ今年の活躍が圧倒的だったという証左である。
逆に副主将(新4年生が予定)はまだ未決定だった。
「ちなみに私は4軍。最下層だよ」
「4軍まであるんですか」と、息吹は驚く。
この大学の野球部は1軍が25名、2軍が30名前後、3軍が30~40名、4軍が20~30名という構成が基本との話だ。むろん年度によって人数は上下する。
新越谷高校は、息吹たちの代が最高学年になり新入生が入ってきた段階で、ようやく1軍と2軍に分けられる規模になった。新3年生は息吹の双子の妹、芳乃(主将、マネージャーという名目の指揮官)を除き7名。新2年生は15人。そして新1年生は22人で、合計で44名という所帯だった。
1軍がベンチ入り20名で、それ以外が2軍という区分で練習していた。
それとは別にマネージャーの生徒が合計で5名いる。来年度も2~3名は入る筈だ。
全国大会での活躍の甲斐があってか、新1年生は地区選抜レベルが6名に、全国選抜レベルが3名と新2年生(地区強豪校レギュラークラスが最高)と比べて格段にレベルが上がっていた。中でも二遊間コンビは中学ナンバーワン(U15日本代表)で、高確率で2年後のドラフトで指名されるだろう。
二遊間コンビは打順も4番の白菊を挟んで、クリーンナップを担っていた。打率も共に4割を超え5割に近い成績を残す。仮に梁幽館、咲桜、美園学院を選んでいても1年の夏からレギュラーだっただろうという圧倒的な才能と実力だった。
実際、埼玉のみならず日本全国の強豪校から「将来のプロ入り」まで見越して好条件でスカウトされていた2人であったが――
〇1年の夏から確実にレギュラーになれる
〇設備が充実している
〇マスコミが注目している
〇全国を狙えるチーム力がある
といった条件から「埼玉3強」ではなく新越谷を選択したといった次第だ。
中学時代地区予選ベスト16レベルの菫と稜に対して、世界大会U15日本代表の二遊間コンビ。レギュラー争いは勝負にすらならなかった。
正捕手の珠姫ですら、エースの詠深が登板する時以外はベンチに下がっていた。
そんなレベルの中、希は別格にしても自分と白菊が堂々とレギュラーかつ上位打線を任されていたのは、2年生の頃を思えば不思議といえば不思議な感覚である。
息吹たちが引退した後の新チームは秋の県大会を制覇。単純な戦力比較ならば、間違いなく昨年度の新チーム始動時点よりも強い。もうじき始まる秋の関東大会の優勝候補筆頭である。贔屓目なしに全国レベルでも屈指の戦力だ。
間違いがなければ、春の全国優勝までノンストップで勝ち続けるだろう。
「4軍の部員は1軍2軍の練習補助のみならず、交代でゴミ出しとか寮の雑事と洗濯や清掃をやっている。まさに下っ端だね」
その上に位置する3軍は、練習設備と用具の整備およびグラウンドの管理を交代で請け負う。むろん練習の補助もだ。マネージャーの学生もいるが、彼女たちの役割はスコアラーとデータ分析、マッサージ等の選手のケア、そして監督とコーチの補助といった面を担当だ。
練習に専念できるのは1軍と2軍のみである。
白菊が息吹に耳打ちした。
「息吹さん、ひょっとして私達は寮で雑用する為に呼ばれたのでは?」
「ちょっ、白菊、声大きい」
「そんなわけないでしょ」と、笹川は苦笑する。
特待生は1軍スタート、推薦組は1軍と2軍に振り分けられる。セレクション合格組は3軍スタート。その他一般入試組は4軍からだ。
「あんた達は1軍が決まっているの。じゃなければわざわざこんな早い時期に呼んだりしないわよ」
息吹と白菊はそれぞれの個室に案内された。
来年から4年間使用する予定の部屋だ。
寮内には不祥事を防ぐ為にあらゆる箇所に防犯カメラが設置されているので、2軍以下の選手にパワハラしない様にと笹川は釘を刺す。
学年と年齢よりも、何軍に所属しているかの方がヒエラルキーとして重要であった。
「あの岡田の後輩だし、2軍以下をいびったりしなさそうだけどね、あんた達は」
◆Chapter03:大学野球での再会
息吹と白菊は用意されていた練習用ユニフォームに着替えた。
そのまま野球用グラウンドに連れていかれる。
「このメイングラウンドは主に1軍が使う」
笹川は隣を指さした。
「あっちのサブは2軍がメイン。で、3軍と4軍は2軍が使わない時にサブグラウンドを使う。2軍も上位メンバーは1軍に混じってメインを使う時もある」
つまり3軍と4軍は絶対にメイングラウンドは使えない。
露骨な格差であった。
それはグラウンドのみならず、トレーニング室および屋内練習場(フリーバッティングも可能な専用の体育館)も同じ。常に1軍が優先されて、次に2軍。3軍と4軍は設備が空いている隙間時間しか使用できない。それも自主練がメインである。
トレーナーやコーチに個別指導されるのは2軍より上だ。
3軍以下の選手は2軍に上がる為にはどうにかしてトレーナー、コーチ、監督の目に留まる必要がある。
ただしチャンスが不公平なわけでなく、1月上旬、4月上旬、8月上旬と年に3度の「選抜期間」が設定されており、その期間内に実施される各種のテストおよび紅白戦で結果を出せば誰もが平等に上に行ける。逆に言えば下に落とされる事もある。
「息吹さん息吹さん、なんか凄いとこ来ちゃいましたね」
「思っていても声に出さないでよ」
「あんた達、野球エリートにしては一般人っぽいね」
「まだまだ初心者ですから」と、息吹。
「はい。始めたのは高校入ってからです」
「キャリア3年で全国であの活躍だから天才の部類ってか、4軍の凡人からすれば立派な野球エリートだって」
笹川はベンチに向け、大きな声を張り上げた。
「キャプテン! 後輩を連れて来ました!」
その声に、ベンチから3名が駆け寄って来る。
息吹の胸がときめく。
(キャプテン!!)
だが、最初に話しかけてきたのは、怜でも理沙でもなくもう1名であった。
「久しぶり。私のコト覚えている?」
「はい。金子小陽さんですよね。お久しぶりです」
「覚えていますし、普通に知っていますよ」
姫宮高校出身というか、元・新越谷高校というか、そもそも1番ショートのレギュラーだ。怜が2番センター、理沙が4番サードである。
「怜先輩が推挙してくださったお陰で、私と息吹さんは無試験で都内一流大学に入学できます。本当に助かりました」
「いや白菊。私は形式だけとはいえ、通常推薦組と一緒に小論文の提出と面接試験があるんだけど」
「そうだったんですか!? 初耳です」
「学校の成績的に、白菊が無試験の方が安全と思ったから特待枠を譲ったのよ」
「事実とはいえ、微妙に傷つきます」
特待生枠の方が貴重(1枠が基本)で、学費など必要経費が全て免除になるが、息吹の推薦枠も学校側から特別奨学金が支給、という形式で実質的に学費等が無料になる契約だった。ただし推薦枠なので無試験入学といかない上に、入学後のカリキュラムも相応に学業を含んでいる。卒業研究と卒論もあるのだ。
白菊の特待生枠は、本当に野球だけやっていれば自動的に卒業だった。講義は自主的に受けられるが単位取得には関係ない。
「ってか、白菊の成績だと推薦枠だって皇京をまともに卒業は怪しいでしょ」
「面目ありません。恥ずかしながらお母様もその点では非常に安心なさっておりました」
理沙が少し引き攣った顔になる。
「ええと、白菊ちゃんって文武両道だと思っていたけど」
「あ、そっか。理沙先輩は知らなかったでしょうが、私達の中で白菊と稜の成績はちょっとヤバ目でした。普通に劣等生の部類ですよ」
「なんとヨミさんが私達の中で成績トップなんです」
そう胸を張った白菊に怜、理沙、小陽は複雑な顔になった。
◆Chapter04:フリーバッティング
監督、コーチ陣および1軍メンバーが注視する中、息吹と白菊の練習が始まる。
それを球拾いの為に外野に陣取っている3軍と4軍(ジャンケンで負けた連中、合わせて計20人)が、キャッチボールしながら見守る。
ピッチングマシンではなく1軍ピッチャーの瀬川(現2年)が投げる。
3軍と4軍が囁き合う。
「あれって今日から参加の新人?」
「新越谷の川口と大村」
「誰、それ」
「知らないの? 有名人じゃん」
「打席はどっち?」
「左に入っているから、スイッチの川口でしょ」
息吹が鋭いドライブが効いた打球を外野に飛ばす。
制球がよい。打ちやすい球だ、と息吹は気持ちよくスイングする。
(初日だからサービスしてくれるわね)
「うわっ、打球が鋭い、しかも伸びる」
「フォームが柔らかいなぁ」
「あれが全国トップクラスの打者か」
「やっぱ1軍確約は凄いわ」
「私達とはモノが違う」
「選球眼いい」
「際どいボール球に全く手を出さない」
「3年生時の通算出塁率、洒落になっていない数字だったよ。特に四球の数」
「明日のドラ1確実の中村 希よりもこっちが天才って声もあるくらい」
「川口、中村は高校野球史上最高の1・2番コンビって評判だったからね」
「あ、そんな有名人だったのね」
「走塁センスも凄いし、これでまだキャリア3年という天才というか化物」
「2年の秋大会から盗塁数が激増して、3年時の公式通算は30幾つだっけ?」
「公式戦だけで41だったと思う。練習試合を含めて失敗1の神記録」
「1試合で4盗塁を記録した事あるよ」
「ほとんどの試合で1回の先頭の川口出塁、盗塁でノーアウト2塁か3塁、中村があっさりとタイムリー、でサクッと点が入るというチートだった」
「岡田の追っかけだったからドラフト指名されなかっただけで、プロ志望だったら少なくても4球団は育成1位で指名したかったってネット情報」
「それなんJとなんGじゃない?」
「おい、無駄口を叩くな3軍4軍!」
と、コーチが叱咤を飛ばし会話は止んだ。
ヒット性の当たりを連発する息吹。
外野の頭を越す豪快な当たりこそ少ないが、綺麗なライナーが糸を引くように外野に伸びていく。当たり損ねがない。ゴロでも詰まった当たりは皆無である。
シェアなバッティングは見る者を唸らせた。
左投げの栗林(現2年)に交代すると、息吹は右打席に移動。
スイッチしても変わらずに鋭いライナーを打つ。
監督が「OK。もういい」と、息吹の番は終わった。
怜は満足げだ。
「夏よりもパワーが増して力強くなっているな、息吹」
「キャプテンがここに誘ってくれてフィジカル強化、頑張りましたから」
「相変わらずセンスは流石だ」
「天才の希が近くにいるので、実感ないですけどね」
「希はプロ1年目から3割を打ちそうだしなぁ」
「それにお客さん扱いで、かなり打ち易い球を投げてもらいましたし」
肩を竦めた怜に、理沙が次打者を促す。
「次、白菊ちゃん」
「はい! 参ります」
気合いを入れた白菊がゲージに入った。
やや力みと固さがみえる白菊は、打ち損ねもあった。しかし芯を食った打球は軽々と外野の定位置を超え、その半数がフェンスオーバーだ。
息吹は渋面だ。リラックスすれば、あの程度の球、白菊ならもっと打てるのに。
圧倒的な飛距離とパワーに、球拾い担当の外野陣(3軍&4軍)は感嘆する。
「なんて飛距離」
「うぉ打球がえぐい」
「もう来シーズンの新レギュラーの4番か5番が確定じゃん」
「ってか、ウチの左右の新エースがパカスカ打たれているの、不安なんだが」
「打たせているんじゃないの?」
「ンにゃ、試しに本気で抑えにいかせるって小陽が話していたよ」
「お前、3人衆と仲良いんだっけ」
「小陽とは学科が一緒っスよ、先輩」
「そういや岡田のヤツ、特待生のくせに成績もトップクラスなんだよな」
「怜は真面目ちゃんだから」
「お前は少し真面目にやれよ。そうすればお前ならすぐに2軍にいけるぞ?」
「ってか、来年のウチって地味にヤバくね?」
「岡田、藤原、金子以外のレギュラーと主力が全員卒業だからな」
「新越谷なら武田も獲った方が良かったかも」
「武田を獲っていればエースだけは何とかなったよね」
去年、今年と強かった反動が来年度に一気にくる。
新4年生の投手陣は手薄。新2年生の投手は期待できない。
新3年生の左右エース(予定)も息吹と白菊相手に抑えにいってこの様、と来年度の戦力ダウンに内心で焦るコーチ達。野手にしても準レギュラークラスは新2年生、新3年生、新4年生に揃っているが絶対的な新レギュラーがいない。レギュラー当確なのは、1年生レギュラーだった新2年生の3名だけ。
怜が異例のキャプテン抜擢と、息吹と白菊をこの時期に呼んだのには相応の理由があった。
監督が小陽に言った。
「やっぱり1番がお前、2番が岡田、3番が川口、4番が藤原、5番が大村――で上位打線を予定するしかないか」
「問題というか課題は守備ですね」
息吹、白菊は正直いって大学野球で即戦力の守備力とはお世辞にも言えない。
しかし投手力が弱いので、打力優先のオーダーにせざるを得ないチーム事情である。
守備力の高い準レギュラークラスの打撃レベルアップよりも、現時点でも打力が高い息吹と白菊の守備を鍛えた方が総合的に期待値が高いと目論んだのだ。
「川口はセカンドとレフト。大村は藤原とDH併用にするが、ライトかファーストも守れるようにする」
「来年の春までに徹底的に守備を鍛えます」
この5日間で地獄の守備特訓が待っているとは、この時の息吹と白菊は知る由もなかった。
◆Chapter05:プロ注だったライバルの今
初日の練習を終え、息吹と白菊は疲労困憊だ。
今は食堂で夕飯の時間である。
同席している怜が言った。
「2軍以下は同学年同テーブルが原則だ」
息吹は食堂内を見回す。
ちなみに息吹のテーブルには、白菊の他に怜、理沙がいる。
「あの怜先輩。小陽先輩はどうしたんですか?」
「小陽はよく監督コーチ達と一緒に食べる」
理沙が言い添えた。
「姫宮時代も怜とは違う方向性で選手をまとめていたというし、怜がいなければ小陽が主将だったと思うわ」
「というか、私よりも小陽の方が適任だ」
「それはMVPの実績と知名度、そして息吹ちゃんに対する監督のサービスね」
「ちょっと白菊。仕組まれた運命だったじゃない」
「それだけ息吹さんが期待されているって事で」
そんな中。
明らかに年長の学生が4人、息吹たちに声をかけてきた。
「岡田、藤原。その2人が期待の新レギュラーか? 監督とコーチ達が絶賛してたぞ」
「主将、どうも」と、怜が畏まる。
「いや、私は引退でもう主将はあんただし。ってか、気を遣い過ぎだっての。もっと堂々としろMVP。とっくにウチはお前のチームだ。誰もが認めている」
理沙が小さく会釈。
「明日のドラフト、よい結果を願っています」
ドラフト候補の4人だが、2人は上位での指名確実で残り2名は育成枠か指名漏れの可能性がある微妙な立ち位置。育成枠ならば内定が出ている企業でノンプロに進む。
明日のドラフト時には、この食堂でTV中継と記者会見が行われる。
3位以上の指名が確実視されている清田が言った。
視線は大型ビジョンに向いている。
「高校3年の時のリベンジ、叶えてみせるよ」
プロ野球ポストシーズン、最終ステージが放送中だ。
勝った方が日本シリーズに進出という大一番。
北海道日清ハムファイヤーズと福岡ハードバンクホークスの一戦。
『さあ、打席には4番の中田』
梁幽館の後輩を、清田は羨望の目で見つめている。
中田奈緒、2年前にドラフト1位で北海道日清ハムファイヤーズに入団。
白菊が呑気に言った。
「高卒1年目で2軍の本塁打王。2年目の今シーズン、後半戦から1軍定着してついに4番就任。期待通りの成長と活躍です」
後半戦だけで打率2割5分1厘、13本塁打、62打点。
OPS.910。
来シーズンは間違いなく不動のクリーンナップだ。
息吹は思い出す。中田奈緒が詠深から打ったホームランを。
ドラフト2位で同チームに入団した陽 秋月も7月上旬から1軍定着しており、こちらは代打がメインで打率3割2分をマーク。シーズン最終戦ではプロ初アーチも放った。
『見逃し三振、速い、中田は手が出ない!』
唸る剛速球がインハイに炸裂し、スリーアウト。
ミットから響く轟音がTV画面越しでも凄い。
奈緒は悔しそうに天を仰ぐ。
『これで奪三振は二桁の10。この回もゼロに抑えました』
この試合、被安打3で綺麗なゼロ行進だ。
平均球速NPBナンバーワンの剛腕ピッチャー。
若きエース、松岡凛音。
去年のドラフト1位。
高校時代よりも球速を上げてオープン戦から好投を続ける。ルーキーイヤーなのに開幕ローテーションを獲得し、そのまま常勝鷹軍団の若きエースと呼ばれる様に。
レギュラーシーズン17勝4敗。防御率1.21、WHIP0.77、QS率8割9分、奪三振率11.5。
最多勝以外の部門を総なめしており、新人王どころかリーグMVPを確実視されている。今や間違いなくNPBを代表するピッチャーの1人にまで知名度を上げた。メジャーのスカウトと海外のマスコミも注目する1年目の活躍だった。
同じ高卒ドラフト1位、マリンスターズの園川 萌が2軍戦で苦しんでいるのとは対照的だ。2軍で2勝8敗。防御率4点台、QSはゼロ。ノックアウト降板が5つ。三振だけは取れている。来シーズンは先発枠から外れて、中継ぎや抑えを試すプランも出てきていた。
ドラフト3位でドラゴンレイズに入団した朝倉 智景の方が通用していた。朝倉は1軍に中継ぎでデビュー済み。9試合登板だ。2軍で5勝2敗4ホールド7セーブ、防御率3.53とまずまずの数字を残していた。来シーズンは開幕から中継ぎで1軍定着が見込まれている。
「松岡はモノが違っていたな」
怜が懐かしんだ。
理沙も同意する。
「希ちゃんと光くらいしか、松岡さんのフォーシームはまともに打てなかったわね」
最終回、裏の攻撃はハードバンク。
ツーアウトランナー2塁。
打者は3番センター。
別のテーブルから悲観の声が。
「あー、ここでギータかぁ」
「なんとかグラシアルに繋いでくれれば」
「もう四球狙いでいいよ、今のギータだと」
「ギータ、最近は調子落としているし、ちょっと期待できないわね」
「ポストシーズン、ホームラン0だし」
「打率も2割4分なんだよな、ポストシーズン」
「1年目だし、ギータ疲労のピークっぽいな」
ギータとは登録名でなくファンの間に定着しているニックネームである。
プロ入り初ヒットが初ホームランでヒロインインタビューに上がった時、「フルスイングだけでなく小技も得意ですので注目してください」とアピールしたのだが、翌日にイージーな送りバントを盛大に失敗した。
それがSNSでトレンド入りし「犠打失敗」が転じて「ギータ」になったのだ。
『スリーワン。バッティングカウントです川原」
川原 光。新越谷高校卒のルーキー。
8球団から調査書は届いていた(ゆえにプロ志望届けは出していた)ものの支配下枠ではなく育成枠で指名だろうと報道されていたが、ハードバンクが6位で川原を指名。
5月下旬に1軍昇格。6月中旬には3番打者に定着していた。
ほとんどの識者が予想外のルーキーイヤーでの活躍。1軍昇格まで3年はかかるという予想が大半だった中、早期でのプロにアジャスト&覚醒である。打撃スタイルの持ち味を変更する事なく、完全にプロ仕様の打者に改造を終えた。
なお、開幕まで投手との二刀流を試していたが、結局は打者一本に絞る事になった。
レギュラーシーズン1軍118試合スタメン出場。
打率2割7分3厘。23本塁打。74打点。
OPS.879。
プロの打者としては、中田奈緒が打点を稼ぐホームラン打者ならば、川原 光はホームランも打てる中距離打者という区分になるだろう。
希がハードバンクに固執する理由は九州出身というだけではなく「また光と同じチームで」というのが大きい。特に光が3番打者に定着して以降、希の目は完全にプロの世界に向いていた。高校野球は眼中から外れていたと息吹は思う。球団側も「翌年に中村 希を釣り上げる為の布石で川原を6位指名したが、まさかの成長と早期覚醒だった」とカミングアウトだ。
『打ったぁ、入った、サヨナラホームラン!』
あれが入るのか、と清田が苦笑する。
「出たよ、ギータの変態ホームラン」
『不調の川原、待望のポストシーズン第1号が出ました』
変態ホームラン、が今や光の代名詞だ。
ニックネームの方はともかく「変態ホームラン」は本人的に不本意らしい。
確信歩きも随分と様になっている。
「木製バットになって高校時代よりも格段に飛距離が伸びたわね、光」
「ああ。あれだけ泳がされても軸がブレずにフルスイングして、しかもあの当たりと角度でホームランだからな。まさに変態ホームランだよ」
「今ごろ希は大興奮ですよ、間違いなく」
「希さんのSNSさっそく光先輩の変態ホームランがアップされています」
ヒロインインタビューでお立ち台に呼ばれた両名。
投打の主役が仲良くファンの声援に応える。
プライベートでも親しい凛音と光だ。
「希さんのSNSが更新されました。調子の乗るな松岡、光先輩から離れろ、と悪口を書いていますが」
「自分の立場、分かっていないわよね希」
凛音は希が入団予定のチームの先輩にしてエースである。
その投稿のリツイート(リポスト)と引用リツイート(引用リポスト)が、あっという間に1万を超えて、さらに伸びていく。表示回数もグングンと数字が回っていく。批判的なコメントも次々と。1位指名確約のドラフト候補&高校野球界の天才打者として、希の注目度は現時点でも高い。トレンドのトップにきており、普通に炎上しそうだ。
理沙が困惑し始める。
「松岡さんのファンから、博多の狂犬はハドバンに来るな、とか、天才だからって生意気なんだよウンコ野郎、とか、お前なんてホークスに要らない、氏ね勘違いバカとか批判コメントされて希ちゃん、逆切れコメント返ししているわ。リツイート、5万を超えたし」
怜が呆れた。
「アイツ、明日のドラフト以降SNS禁止にした方がいいな」
◆Chapter06:ドラフト会議
大勢の記者とTVカメラに囲まれて、中村 希は緊張していた。
頭上には大きなくす玉。
監督の藤井 杏夏が隣に座る。
それを新越谷野球部の面々が遠くから見守る。
胴上げと記念撮影要員だ。胴上げに使う緩衝用マットも用意していた。
「凄い景色だなぁ。去年、光先輩の時は「指名漏れだったら恥ずかしい」って、記者会見用意してなかったんだよな」
稜の言葉に菫が苦笑する。
「そうそう。予想外の支配下6位指名で、慌てて記者会見がセッティングされたのも今では良い思い出よね。部員を招集したけど人数不足で胴上げできなかったし」
「しかも1年後の活躍なんて誰も予想できなかったよなぁ。ぶっちゃけ私、数年は2軍暮らしだとばかり思っていた。なのに今やハドバンの3番打者だぜ?」
「希が凄すぎてあまり実感できなかったけれど、今思うと光先輩のバッティングも随所でヤバかったわ。それにプロ向きの打撃スタイルだったし」
「流石に怜先輩と理沙先輩のバッティングよりは格上だって、私は光先輩が入部してすぐに気が付いたぜ。フリーバッティングだけでも、希とは別方向で凄かったもんな」
「確かにスイングが私達とは違っていたわね」
「オフになったら光先輩にも会えるだろうから、一緒にサイン入りグッズを貰おうぜ。将来、金に困った時にネットオークションで高値で売れるかもしれない。ついでに松岡のサインも欲しいな。いやいや、いっそのこと光先輩のコネでハドバンの有名どころ全員――」
「アンタねぇ」と、菫は稜の頬を抓る。
「いくら光先輩が優しいからって図に乗るのは止めなさい」
詠深が言った。
「ウチから2年連続でプロ選手が誕生とは、これは来年の新入生が更に爆増かな。遠征用のバスも2台じゃ足りなくなるかも」
「1年目の秋大会以降、見事に世間は掌を返したわよね、私たちに対して。2年目からは不祥事の不の字も出なくなったのには笑ったわよ。ヨミほどじゃないけど、私も内心では見返したいって思っていたから」
「菫、お前って地味に根にもってたのな」
「頑張った甲斐があったよ、皆に応援して貰えるようになって」
嬉しそうに微笑む詠深を、珠姫は複雑な顔で見ていた。
「どったの? タマちゃん」
「ううん、何でもない」
約4年前に起こった不祥事により新越谷野球部の評判は地に落ちた。それを3年前、詠深たち8人の新入生(当時)が立て直し、世間の悪評を拭い、さらには名門復活の礎となった。
後に、この世代は埼玉高校野球史において「新生・新越谷第一世代」「伝説の8人」と語り継がれる。
「なーなー芳乃。光先輩と松岡はルーキーイヤーから1軍レギュラーゲットできたけど、希はどうなると思っている?」
「ハドバンは1番と2番打者が割と流動的だから、春のキャンプでプロにアジャストできれば、希ちゃんなら開幕レギュラーも充分にあり得るチーム事情だと思う。今シーズンも打順ガッチリ固定は3番の光先輩だけ。後は2番と4番を担った近藤選手。小久保監督も野手レギュラー確定は、この2名だけと明言しているからね」
芳乃は考えながら、開幕先発オーダーを予想した。
「1番は周東選手が最有力、次点で三森選手かな。2番が希ちゃんと牧原選手、柳町選手の争い。3番が光先輩。4番がどすこい山川選手。5番は近藤選手。6番はDHメインで新外国人の助っ人だと予想。トレードが確定的なウォーカーじゃないかな。7番以下は2番争いで負けた選手の1人で、それと井上選手と川瀬選手の争い。8番は今宮選手。川瀬選手が今宮選手から正ショートを奪取できれば、色々と総合的に変わってくると思うけれど。そしてラストバッターの正捕手は来シーズンも甲斐選手で決まり、だと思うよ」
「ほぅほぅ。開幕投手は?」
「松岡さんか千賀投手か、ちょっと私にも判断がつかないかな?」
「でも千賀はメジャー移籍がほぼ決まりっぽいよな」
「うん、海外FA取得したからね。ハドバンは日本から世界一の球団をってコンセプトのチームだからホスティングでのメジャー移籍は否定的だけどFAは止められない。光先輩はホークスに骨を埋める覚悟って言っていたし」
「希もメジャーを目指すってタイプの打者じゃないよな。あっちでファン受けするホームランバッターじゃないし」
そうこう会話している内に、ドラフト1巡目指名が順調に終わる。
大方の予想通りの結果だ。
ハードバンクの1位指名および交渉権の獲得が決定し、くす玉が割れた。
それとタイミングを合わせて、校舎の正面には「中村 希選手、福岡ハードバンクホークス1位指名おめでとう!」の垂れ幕が降ろされている。
球団職員のみならず、異例中の異例で球団社長が駆けつけていた。
つまり予想外の競合はあっても、1位指名漏れは絶対にない状況である。
特例イベント的に、真新しい背番号7のユニフォームに希が袖を通す。球団キャップを被って記念撮影だ。カメラマンの注文に応じて希がポーズをとる。仮契約前だが相思相愛かつ入団決定的なので、どうせならばここまでやる、とマスコミにも通達済みだ。
色紙に描いた目標は「開幕レギュラーと打率3割」。
記者団からの質問が一通り終わった後、待ってましたとばかりに記者の1人が悪意ある言葉を投げかけてきた。
「ヤホーニュースにも上がった「松岡投手を誹謗中傷したツイートが炎上した件」について、中村選手はどうお考えでしょうか? リツイートというかリポスト、31万を超えていて、コメントもほぼ批判一色ですけれど」
ぐぬぬ、と希が悔しそうに歯ぎしりした。ちょっと涙目になっている。
どう見ても反省の色は皆無だ。
慌てて球団社長が希をフォローする。というか、実質的にそのために来ていたのだ。特例イベントでユニフォーム姿披露は、本当についで、であった。
「球団広報としては問題視しておりません。当の松岡が意に介していないですし、2人は高校時代に対戦した時の知り合いでもあります。そういった辺りは球団公式YouTubeチャンネルに動画をアップしますので是非ともご覧ください。松岡は中村選手の入団を快く歓迎しています! ファンの方々もその辺にご理解をお願いしたします」
「私は悪くなかろーもん」
仏頂面の希。
会見前に理事長から強烈な説教を食らった事を根に持っていた。「プロ野球選手として自覚をもった言動を心掛けなさい」と約30分も叱られたのだ。
素晴らしい反射速度で杏夏が、「ぅおっとぉッ」と希の口を物理的に塞ぐ。
「こ、こ、この子はマスコミの皆さんがご存じの通りに、ちょっと不器用で口下手なところが、その、悪気はないですよ、今だって「悪気はなかったもーん」と言いましたし! それから野球以外の質問はNGで!」
2年生と1年生の部員たちがコソコソと言い合う。
ちなみに1軍メンバーはもうすぐ始まる秋季関東大会の準備でこの場にはいない。揃っているのは2軍メンバーのみである。
「中村先輩、性格アレだしねぇ」
「3年同士の会話ですら、中村先輩って芳乃キャプテンとの会話がほとんどだったよ」
「色々と誤解されてるよね、希先輩って」
「実は私、中村先輩とまともに会話したコトない」
「安心しろ、ソレ3年以外ほとんどだから」
「他の3年はめっちゃ気さくなんだけどね。特に稜先輩とかヨミちゃん先輩とか」
「芳乃キャプテンがフリーだと芳乃キャプテンにベッタリだったけど、それ以外は基本的に部活中はボッチだったよね、中村先輩」
「信じられないけど、野球部以外だとかなり友達多いんだよ、あの人」
「あの人は天才すぎて、野球やってると心の壁が、ね」
「白菊先輩がホームラン打った後に、後ろから本気の蹴りは入れていたけれど、あれって数少ない中村先輩からのコミュニケーションだった」
「1年は知らないだろうけど、去年は光先輩がいたからまだマシだった」
「光先輩ってハドバンのギータ?」
「そそ、そのギータだよ。で、同じ先輩のキャプテンと理沙先輩でも中村先輩には強く出られなくて。そんだけの天才だし、あの人」
「懐いていたギータ先輩いなくなって、中村先輩ほとんど個人練習ばかりになったってのは、ヨミちゃん先輩とかから聞いてます。それでも問題なしの実力だったけど」
「中村先輩にとって去年の夏の全国で高校野球は終わっていたと思う」
「あーー、またキャプテンと野球したいから、私も皇京大を目指そうかな」
「私も皇京大、一般入部でいいから目指すか」
「大学だったら高校と違ってキャプテン達と2年近く一緒にやれるんだよね」
「2年の先輩たちにとってのキャプテンって、やっぱり岡田って人なんですね」
「うん、芳乃キャプテンは名目はキャプテンだけど、昔っから真の監督だしね。私達2年にとってはキャプテンって感じじゃないかな」
「うちら2年生世代までは、キャプテン=岡田 怜なんだよ」
最後に胴上げの段になって、遠巻きから観ていた後輩たちが芳乃に呼ばれた。
なお、希は目標であった開幕レギュラーをゲットする事になる。プロ入り1年目から打率3割4分8厘(リーグ2位)をマークするものの、惜しくも新人王を逃したのは別の話――
◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その1
プロ野球シーズンオフ某月某日。
時刻は19時。
場所は埼玉県某所にある高級料亭。
松井遥菜は中田奈緒の呼び出しに応じて、とある飲み会に参加していた。
否、飲み会ではなく食事がメインの親睦会だ。そもそも飲酒可能な二十歳になっている者が2年前のドラフト組しかいないのだから。
参加メンバーは「2年前のドラフト以降にプロ入りした埼玉出身の野球選手」のみで構成されている。その名称は『中田会』との事だ。
遥菜は参加に気が乗らなかったが、母校である咲桜高校の先輩かつ同じライオンズ所属のプロ選手、田辺由比も出席しているので、無下に断るわけにもいかなかったのだ。
むろん費用は全て奈緒が負担する。他の者は1円も出さなくて良い。
高級料亭の一画が丸々貸し切りになっていた。
「遅いぞ、松井」と母校の先輩である由比が、軽く遥菜を叱る。
どうやら自分が一番最後だった模様だ。
「これで全員が揃ったな」と、奈緒はご満悦である。
この『中田会』に新加入したのは、今年は4名だ。ライオンズ1位指名の遥菜(咲桜出身)、マリンスターズ1位指名の諸積恋美(美園学院出身)、ホークス1位指名の中村希(新越谷出身)、マリンスターズ7位指名の愛甲(美園学院出身)である。
遥菜は殊勝に頭を下げ、下座に腰を落ち着けた。
(必要な付き合いとはいえ、面倒だナ)
上座からザッと面子を見回すと――
2年前にプロ入り組
中田奈緒(梁幽館):ファイヤーズ1位指名
1軍(4番打者)
推定年俸1500万円⇒今季2000万円⇒来季4000万円
陽 秋月(梁幽館):ファイヤーズ2位指名
1軍(来シーズンはレギュラー獲りに挑む)
推定年俸1000万円⇒今季1200万円(※)⇒来季1950万円
田辺由比(咲桜):ライオンズ3位指名
2軍(内野手、1軍登録・出場あり)
推定年俸800万円⇒今季800万円⇒来季930万円
久保田依子(熊谷実業):ホークス5位指名
2軍(外野手、1軍登録なし)
推定年俸600万円⇒今季650万円⇒来季520万円
1年前にプロ入り組
園川 萌(美園学院):マリンスターズ1位指名
2軍(投手、1軍登録なし)
推定年俸1500万円⇒来季1200万円
松岡凛音(深谷東方):ホークス1位指名
1軍(先発ローテ2番手、エース)
推定年俸1400万円(※)⇒来季5500万円(複数タイトル料込)
朝倉智景(柳大川越):ドラゴンレイズ3位指名
1軍登板9試合(中継ぎ)
推定年俸700万円⇒来季1050万円
川原 光(新越谷):ホークス6位指名
1軍(3番打者)
推定年俸400万円(※)⇒来季2500万円(日本一ボーナス込)
小林依織(梁幽館):シャイアンズ7位指名
2軍(捕手、1軍登録なし=3年間のファーム育成計画)
推定年俸500万円⇒来季820万円
(※)凛音と光、陽はほぼフルシーズン1軍登録だった為、1軍最低保証年俸として契約年俸ではなく無条件に1600万円が支払われる
大卒プロはいない。
奈緒と同学年の大卒組(埼玉の高校卒)が、この『中田会』とやらに加盟するのかは、遥菜にとって知るところではないというか、興味もなかった。
来年のドラフトで、埼玉県の高校から指名されそうな有望株は現時点で梁幽館の野村瑞帆と美園学院の渡邉詩織の2名らしいので、来年の今頃、この集まりの面子は15名か。どうでもいいが。どうせオフの限られた時しかこの埼玉では集まれない。
奈緒が音頭をとる。
「では全員揃ったところで、乾杯!」
楽しい食事が始まった。
ドラフト1位契約とはいえ、現時点では高校生に過ぎない遥菜にとって、こんな高級料亭での食事は非日常的であった。この一晩で200~300万円は軽く飛びそうだ。
(確かスタンダートに契約金1億円+出来高5000万円、って公表していたガ、中田奈緒の契約金は本当は何億だったんダ?)
通例にならった金額(ドラフト1位は1億円+出来高MAX5000万円)とは違い、遥菜は「ピー」億円を5年間月割で支払ってもらう契約(守秘義務あり)だが、奈緒も通例以上に相当な額を貰っていなければ、ここまで羽振り良くできないだろう。
4番を手に入れた今季のオフ、個別スポンサーとの契約やTV出演料を得ているが、それにしたって、まだ大した金額にはなっていない筈。
高級料理に舌鼓を打ち、遥菜は満足だ。
(120点だナ)
タダ飯というところが特に素晴らしい。
「――さて、ここで皆に発表がある」
会食が始まり30分ほど経過したところで、奈緒がそんな事を切り出した。
「新加入した3期生で計13人になった機会に、この『中田会』という集まりをリニューアルしようと思うんだ」
勝手にしてくれ、と遥菜は思った。
単に高級なタダ飯が食えるだけの付き合いだ。
「ここにいる全員でYouTuberグループを結成する」
え? 遥菜は耳を疑った。
何を言っているのだろうか?
場の空気が凍り付く。
(冗談だろ?)と遥菜は奈緒を見つめるが、残念ながら「冗談だ」という台詞は続いて出てこなかった。真顔のままだ。奈緒の高校の後輩である依織が質問する。
「な、奈緒さん、理由を教えて下さい」
「シーズン終わった直後に陽と話し合って決めたんだが、松岡と川原が1年目からレギュラー獲って、陽も1軍定着、私も4番の座を手に入れた。これは知名度的にYouTubeを始めるのには最高のタイミングだと判断した」
皆の視線が陽に集まる。
陽はスマホでプロスピに夢中になっていた。というか、遥菜が来てから一言も喋っていない気がする。ずっとスマホを弄っていた。なんなんだよコイツは。
依織が言う。
「あの、奈緒さんと陽さんの2人組YouTuberではダメなのでしょうか? 私達は必要に応じてゲスト出演するというカタチで。陽さんはどう思います?」
陽はスマホ画面から視線を動かさない。
プロスピに夢中だ。
「シーズンオフなら私と陽だけで定期的な動画アップは可能だろうが、シーズンに入ると2人だけでは無理がある。ネタも続かないだろう。だが、ここにいる皆がそれぞれの所属球団ごとにローテーションして動画を投稿すれば、ネタ切れもしないだろうし、無理なくチャンネル運営をしていけると考えた」
由比が言った。
「でも中田。撮影は自分達でどうにかなるけど、編集はどうするのよ? 正直いって編集作業はかなり時間を食うし面倒だよ。同じ球団の私と松井ならば、松井にやらせれば済むけど、他の球団の面子はそうはいかないでしょ?」
(おい、なんで私が動画編集を押し付けられるんダ?)
遥菜は思った。体育会系の上下関係はクソだ、と。
「心配するな、田辺。各球団のチームごと撮影した動画データをチャンネル運営会社に送ってくれれば良い。編集以外にもコンサルもやってくれる。そしてその会社とはもう既に契約済みだ」
奈緒が合図を送ると、撮影スタッフが5名ほど姿を見せた。
そして死角に設置してあったカメラを取り出す。
(隠し撮りじゃないカ)と、遥菜は呆れた。
他の面子も隠し撮りされていた事に憤慨とまではいかなくても、やや引き気味である。
奈緒を慕っている依織は愕然となっていた。
隠し撮りの必要がなくなったのか、照明とレフ板が堂々と設置された。
この時点で遥菜は帰りたくて仕方なくなっていた。来た事を後悔している。
奈緒が言った。
「では皆に確認する。私の意見に反対、YouTube活動をしたくない者は挙手してくれ」
誰も手を挙げられなかった。
遥菜は思った。体育会系の上下関係はクソだ、と。
「よし。それならば是非ともYouTuberグループの一員になりたいと希望する者は、挙手してくれ。決して強制ではないからな」
陽がスッと手を挙げた。視線はスマホに固定されたままだが。
恋美が「面白そう」と笑顔で挙手。愛甲も「やってもいいかな」と抵抗なく続く。
問題は他の面子だ。
(田辺先輩! 久保田! 頼む断ってくれ!)
そしてこの馬鹿げた思惑を潰して欲しい。
だが、遥菜の願いも虚しく由比と依子は「仕方ないか」と苦笑しつつ、挙手した。
こうなると後輩に拒否の選択肢はない。
萌、智景、凛音、光、希、依織の順で手が挙げられていった。全員、俯き加減でどう見てもやりたくなさそうだ。「なんで、どうしてこんな事に」と希が小さく呟いた。
最後に残された遥菜も観念して挙手する。
遥菜は思った。体育会系の上下関係はクソだ、と。
――続く。
◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その2
なし崩し的に中田奈緒のYouTubeチャンネルに参加する羽目になった遥菜。
ルーキーイヤーを迎えるにあたり野球に集中したいのに、どうしてこうなった。
奈緒は満足げに言った。
「それではお待ちかねの、チャンネル名の発表だ」
(少なくても私は待ってねーヨ)
「ポストシーズン後に、もっとも頭を悩ませた命題といっても過言ではない」
(野球の事で悩めよ。お前、最後の試合4番のくせに4タコだったろ)
「じゃあ、発表しよう」
(いいから勿体つけるなよ。イライラするゾ)
「、、『なかったから作ったよチャンネル』――だ」
「くそダサなチャンネル名だナ、35点」
つい心の声を発音してしまった。
遥菜は言ってしまってから、しまった! と後悔して焦る。
(誰か、助け船を出してくれ!)
場の温度が体感で氷点下にまで下がってしまったが、依織がフォローに回ってくれた。
「あの、奈緒さん。SEO的な観点からチャンネル名には中田奈緒の文字を入れる方が、長期的な視聴者流入を考えれば有用かと思います」
「SEOって何だ? OPSみたいなものか?」
(この女、やっぱり野球を取り除くとバカの部類だったナ)
依織は沈痛な面持ちで視線を落とした。
しかし遥菜は胸を撫でおろす。上手く話題の焦点が逸れてくれた。
「SEOってあれだろ。ほら、プロレス技みたいなものだ、きっと」
それはおそらくSTOだ。
依子の発言に(こいつもバカだったカ)と、遥菜は冷ややかな目を向ける。
ちなみに依子はかなり酔いが回っていた。
(しかも頭の出来だけではなく酒にも弱いし)
萌が言った。
「SEOとは検索エンジン最適化の事です」
由比が感心する。
「聞いた事があるわ。でも、検索エンジンならどうしてKEじゃなくて、SEなのかしら? ITだからSE? ねえ松井、教えてくれない?」
(そういえば田辺先輩も、見た目に反して勉強ダメだったんだっケ)
見た目が激似の某レールガンは成績優秀だった筈。
「サーチエンジンの略でSEで、ITのSEはシステムエンジニアの略です」
「松井、お前インテリだな。お前の学力なら高卒で就職じゃなくて、大学進学して外資系企業を狙った方がいいんじゃないか?」
酔いが回っている依子が締まりのない笑顔で褒めた。
そういった観点で言うのならばここにいる全員が高卒ブルーカラーだろ、というかプロ野球選手だから個人事業主だ、と遥菜は心の中でツッコミを入れた。
依織が奈緒に再び言った。
「確かに奈緒さんの知名度ならば検索流入を度外視して、いきなりブラウジングや関連動画からの視聴者を集められるでしょう」
「依織、済まないが野球以外の専門用語は苦手なんだ。そもそもYouTubeなのに、どうしてブラッシングとか出てくるんだ?」
「ええと、その、簡単にかみ砕いて説明しますと視聴者に分かりやすいチャンネル名が良いという話なんですよ」
「そうか、お前は気が付いていなかったのか。なかった、と中田を掛けているんだ」
「そこはちゃんと気が付いていました」
「本当か? お前はどうだ、松岡」
「え? 私に振る? あ、気が付いていませんでした! 流石は中田さんです、頭が良い」
悲しいほどの愛想笑いで凛音はヨイショした。
依織が真剣に言った。
「奈緒さん。私は『中田奈緒の埼玉魂』が良いと思います。分かりやすいですし、埼玉出身校の現役プロ野球選手チャンネルだと覚えてもらえるでしょう」
萌が賛同する。
「確かに良いチャンネル名ね。小林ちゃんは正しい」
他の昨年度ドラフト組も揃って依織案を押した。
それでチャンネル名は『中田奈緒の埼玉魂』に決定する。
「チャンネル名も決まったところで、メンバーは自己紹介をやり直すから、各自に用意してある原稿に目を通してくれ」
光が言った。
「自己紹介文ですが、名前以外は目の前に置かれている料理の材料の生産元の紹介ばかりなんですけれど。それから私の名前は川原光でギータはニックネームです。一言目の皆さんお馴染みギータです、から以降ずっとお肉の宣伝じゃないですか」
智景も言う。
「私は料理が盛られている陶磁器ブランドの紹介」
奈緒は丁寧に説明する。
「この動画を視聴している人は基本的にギータと朝倉は知っているんだ。でもスポンサーの商品はあまり知らないから、そちらを重点的に紹介するのは当たり前だろう? ちなみに肉の方は紹介料250万円、陶磁器は180万円だから、心を込めて台詞を読んでくれ」
誰もが無言になった。
遥菜の自己紹介は「ライオンズのドラ1、松井遥菜です。そしてこの本マグロは――」と、目の前に鎮座している海産物のアピールに終始している。
まずはスポンサーパートを収録だ。
「大事な箇所だから、リハーサルをしてから本番にいくぞ」
奈緒はそう言うと美味しそうにジョッキでビールを一気飲み。
豪快に飲み干した空ジョッキをテーブルに「どん」と置く。
ジョッキの隣には先ほど中身を注いで空になっているビール瓶がある。ブランドアピールの為にあえてテーブルに残してあるのだ。
「ぷはァー。やっぱりビールはサッポロに限る!」
(ここは埼玉だゾ)
遥菜は心の中でツッコミを入れた。
真顔に戻った奈緒は、皆に確認する。
「どうだ? 美味しそうに飲めていたか? 球団側に許可をとってのサッポロビールとの提携だ。400万円も提供してもらっているだけに、魂を込めてアピールしないとな」
先ほどから金の話ばかりだ。
恋美が言った。
「もっと意図的にゴキュゴキュって喉を鳴らした方がいいですよ」
「なるほど。お前は早くも「野球およびYouTube」のプロとしての自覚が芽生えている様だな。参考にする。これでどうだ?」
テイク2でまた一気飲みを披露する奈緒。
希がおずおずと言う。
「あ、あの。本番前にあまり飲み過ぎると」
皆の視線が依子に向く。
依子は現時点でかなり出来上がっていた。
これ、収録は大丈夫なのか?
「問題ない。ビール瓶の中身はアサヒのノンアルに差し替えてあるからな。後でアピールする予定の日本酒も中身は水に差し替え済みだ」
「え? アサヒ?」と、希は目を丸くする。
隣の光は複雑な表情で首を横に振った。
(ヤラセじゃねーかヨ)
コイツ、素ではこんな性格してやがったのか、と遥菜にとっての奈緒への尊敬の念は限りなくゼロに近づいていた。
スポンサーパートの撮影が終わり、次は終了画面の撮影になった。
そして座談会前半⇒サムネイル撮影⇒座談会後半というスケジュールだ。
「視聴者プレゼントを企画しているから、申し訳ないが、この撮影は全員ではなくすでに1軍で結果を出して知名度がある4名でいく。済まないな、田辺、久保田」
奈緒はそう謝罪した――が(いや、久保田の撮影はもう無理だろ)と遥菜は心の中でツッコミを入れた。どう見ても飲み過ぎだ。
左から順に凛音、光、奈緒、陽と並ぶ。
「台詞は全て私が担当する。皆はアドリブで笑顔を作り手を振ったりしてくれ。最後に私に合わせて右拳をカメラに向かって出すんだぞ。ホームランを打った後、ベンチ担当のカメラマンに対してカメラ目線でやるポーズの要領だ」
(そういえば中田のホームランポーズは、どことなくダサかったナ)
来シーズンは別のポーズにする方がいいだろう、と遥菜は心の中で注文を付けた。
テイク1、スタート。
「最後まで動画を観てくれてありがとう! この動画が面白かったら、チャンネル登録およびグッドボタンをよろしくお願いします。それから動画公開後2ヵ月に抽選をおこない視聴者プレゼントを企画しているぞ。希望者はコメント欄から応募してくれ」
そこで一息入れて――
「まずは私のプロ第1号ホームランのサインボール、サインバットをそれぞれ1名様にプレゼントだ」
(1個ずつしか存在していないんだから、各1名様は当たり前だろ)
「次は、陽のプロ第1号ホームランのサインボール、そしてサインバットもそれぞれ1名様にプレゼントするぞ。どしどし応募してくれ」
光と凛音が右拳をカメラに突き出す準備に入る。
「そして私達だけではなく、なんとギータのプロ第1号ホームランのサインボール、サイン入りバットをプレゼントだ!」
「えぇッ!?」と、驚く光。
はい、カァ~~ト!、とカメラが止まる。
「どうした川原、真面目にやってくれ」
「あ、いえ、私のサイン入りボールとバットの件は初耳だったので」
「それはそうだろう。今初めて言ったからな」
「あ。そうですか。次、気を付けます」
「松岡も分かっているな?」
「はい! 私はプロ初勝利のウイニングボールですよね?」
「ちゃんと分かっているじゃないか。お前たち2人は私の自慢の後輩だけある」
「ありがとうございます」と光。
「はい、頑張ります!」と凛音。
(おいおい中田のヤツ、出身校も所属球団も違うのに、強引に後輩に加えやがったゾ! というか、後輩という名の舎弟じゃないか)
自分はそうはいかない、と遥菜は警戒した。
そしてテイク2に入る。
今度は光も失敗しない。
自分のサイン入りボール、サイン入りバットの台詞の時に、光は可愛らしい笑顔を作り、キュートに両手を振ってみせた。そんな光を遥菜は憐憫の目で眺める。
「最後の視聴者プレゼントは、NPBの若きエース松岡凛音の、プロ初勝利のウイニングボールをサイン入りでだ!」
そこでふと奈緒が考えた。
「松岡だけ1つしかないな。よし! 日本シリーズ優勝のウイニングボールも松岡のサイン入りでプレゼントしよう」
「えぇッ!?」と、驚く凛音。
はい、カァ~~ト!、とカメラが止まる。
「どうした松岡、真面目にやってくれ」
「いえ、その、日本シリーズの記念ボールはもう寄贈していて、手元にないんです」
「そうか。それならば仕方ないな。だが松岡、大事な記念品を安易に他人に譲るのは感心しない。野球ファンだけではなくチャンネル視聴者の事も考えてくれ」
「でもYouTubeの件はその時は知らなくて」
知らされたのは、つい今し方だ。
「失敗は誰にでもある。次から気を付けてくれ」
「はい!!」と、凛音は頭を下げた。
(他人の記念品を勝手に視聴者プレゼントにしておいて、どの口が言うんだヨ)
早くこの場から解放されたい、と遥菜は心から思った。
――続く。
◆Chapter07:キャッチボール
希の会見が終わった。
スタッフが撤収に入っている。
これで解散、全て終了ではなく、希はこれから理事長、藤井教諭と共に学校関係者および支援者、後援者への挨拶回りがある。後日にはローカル局のTV出演、埼玉で仮契約だ。それから全ての条件で合意し球団事務所にて本契約した暁には、晴れて正式な球団所属となり選手寮に引っ越しである。
要約すると――
①指名後の挨拶と仮契約
②メディカルチェック
③本契約および入団発表
④入寮
⑤新人選手合同自主トレ
⑥各球団の春季キャンプに合流
⑧オープン戦開始
⑨高校の卒業式に出席
⑩シーズン開幕
指名挨拶の時に契約条件はかなり詳細まで踏み込んでいたとの話なので、契約で揉める事はないだろう。金銭的には、恒例に従ってスタンダードに契約金1億円・年俸1500万円で発表する筈だ。希にメジャー志向はないので移籍条項の問題もないだろう。
「それじゃあ、先輩方お疲れ様でした!」
2軍の後輩たちが詠深たちに頭を下げてグラウンドへ走って行った。
彼女達は練習用ユニフォームで、詠深たちは学校制服だ。
詠深たちも記者会見が行われた部室前(設営されたテントはTVスタッフが片付け。雨天ならば体育館内の予定)を後にした。
グラウンドの外周を歩きながら、詠深たちは後輩の練習風景を眺める。
この夏までは、確かにあそこが居場所だった。
芳乃の引退を見越し、今年の春先に外部から専門コーチを雇っていた。
そしてマネージャーは2年生が2名に1年生が3名。
人数と活気、熱気が凄い。関東大会目前だ。現役の高校球児たちの姿――
引退した者には眩しく映る。
「来年度の新入生は25人までに制限するって、藤井先生が言っていたよ」
詠深の言葉に、菫が感慨深く返す。
「各学年25名、合計で75名に絞らないと監督1名とコーチ1名じゃ面倒みきれないものね。私達が1年の秋の頃には、芳乃も入れて11人しかいなかったのに」
「でもコーチを増やしたら、総勢100までは視野に入れているってさ。それだけの設備はあるし、寄付金が集まって増設も計画している。予定では、再来年度の新人からはスカウト活動でスポーツ特待も始めるって」
「ウソみたいだよな。もうあのグラウンド、私達の場所じゃないんだぜ」
「ホント、こうして眺めると終わったんだな、って実感するわ」
稜の言葉に、菫は目を細めた。
ふと、掛け声と打球音が止む。
引退した3年生の姿を見つけて、新越谷野球部の部員たちが練習を止めたのだ。そして新キャプテンの指示に合わせて「ありがとうございました!」と3年生たちに向かって深々と頭を下げる。
後輩たちにとっても希のドラフト会議が「3年生の本当の引退」だったのだろう。
「もうそこはお前たちの場所で、今はお前たちの時代だ! 関東大会、頑張れよ!」
稜に合わせて詠深たちは全員が大きく右手を振った。
これ以上は後輩たちに気を遣わせて、邪魔になる。次に後輩たちに改まって顔出しするのは、高校生活のラスト、卒業式後の別れの挨拶だ。
グラウンドに背を向けて、校舎から出た。
新チームになってからの埼玉最大の強敵は梁幽館になるだろう。
2年夏からエースナンバーを背負っている、右の本格派ピッチャー斉藤小町。
打倒新越谷の為に梁幽館に入り、1年秋からレギュラーを獲り、以降5番ショートが定位置で、新キャプテンに就任した5ツールプレイヤー野村瑞帆が中心となっている。瑞帆はプロ注目のショートストップで、U18チーム日本代表でもあった。
梁幽館だけではない。
咲桜のリードオフガール、国内最速センター村松京子。
中学時代の詠深の後輩でもある美園学院の新キャプテン、4番キャッチャーの渡邉詩織(彼女もU18チーム日本代表)とプロ注目の有望株たちが最終学年に入り、新越谷高校のプロ注たちとの激突が埼玉高校野球ファンからの注目が高まっている。
河川敷を歩く。
まだ日は高い。
引退してから「放課後ってこんなに長いんだっけ」と初めて実感した。
それにも慣れつつある。
帰宅して、夕食を終えたら受験勉強だ。模試の合格判定は全員がAなので、そこそこのマイペースで問題ない。
身体が訛らない程度の自主トレは続けているが、後輩たちの邪魔をしたくなかったので学校の施設は使用せず、近場の公営体育館やスポーツジムなどに集まっていた。
珠姫が言った。
「去年の先輩達は部活を引退した後、今日の私達みたいにグラウンドを見る度に、どんな気持ちだったのかな」
「やっぱ寂しかったんじゃねーの。私も正直、寂しいし」
「そうね。私も同じ気持ちよ、稜」
詠深は秋空を見上げ、
「息吹ちゃんと白菊ちゃんは切り替え、早かったよね。なんかさ、引退してすぐに怜先輩たちの大学から誘いがきたってのもあったけど、ホント早かった」
「――ヨミちゃんにも皇京大からのスカウト、あったよね」
珠姫の声音には微かな怒気があった。
「ん~~。でも息吹ちゃん白菊ちゃんとは違って、怜先輩から直の誘いはなかったよ。あったら少しは迷ったかなぁ、どうだったかなぁ。にしても嬉しそうだったよね、息吹ちゃん、怜先輩からの直の誘い。電話の後、理沙先輩と2人でわざわざ自宅まで来たって」
「はぐらかさないで。他の強豪大学からの誘いだって何校かあった。最高条件の特待生で。そもそもプロ志望届を出していれば、希ちゃんだけじゃなくて、ヨミちゃんだって今頃――」
詠深はあっけらかんと言う。
「そうだっけ? 忘れちゃった、そんな前の事」
「とぼけないで。私は悔しいんだよ、ヨミちゃん。光先輩、希ちゃんがプロなのにヨミちゃんがプロどころか強豪大学にさえ進まないなんて。私の所為で、ヨミちゃんの未来が制限されるなんて、悔しいんだよ」
「自惚れるんじゃないわよ、バカ珠姫」
菫がピシャリと断じた。
「ヨミが珠川大を選んだのは、あんたの為だけじゃない」
「そーそー、むしろ私と菫の為の選択だろ。キャプテンだって分かっていて息吹と白菊しか誘わなかった。そして私と菫も分かっている。だから恨みなんてない」
「私と稜じゃ、現時点の皇京大に行ってもレギュラーにはなれない、間違いなく。席は空かないでしょう。そして息吹と白菊はレギュラーで活躍できる。たぶん入学してすぐから。だから先輩たちは私と稜どころか、ヨミにも声を掛けなかった」
「ま、ヨミならどの強豪大学だって1年からエースだと思うぜ。悪くても先発2番手で控えなんて事はない。でも私と菫は違う。入学先を選ばなきゃ即レギュラーは無理だ」
苦笑しつつ明るい声で詠深が言う。
「それ言っちゃうかぁ、菫ちゃん、稜ちゃん」
珠姫は何も言わなくなる。
そのまま歩く。
表情から険しさがとれない珠姫を見て、それまで黙っていた芳乃が口を開いた。
「久しぶりに、ここでキャッチボールでもしようか」
そして10分後。
使うボールは、近くのコンビニで調達したオモチャのカラーボールだ。
芳乃の奢りだった。
詠深は嬉しそうに感触を確かめる。
「懐かしい。子供の頃、このカラーボールでタマちゃんに魔球を投げたのが、私の野球の始まりだった」
珠姫は無言を通す。
キャッチボールが始まる。
まずは詠深から珠姫へ。
不機嫌なまま言葉を発しない珠姫だが、ボールは綺麗にキャッチした。
「次は菫ちゃんにね」
ボールが菫に渡り、菫は稜に投げ、稜から詠深に戻ってきて一周だ。
芳乃は見ているだけ、と最初に参加を断った。
何周かした後――
「私はさ、プロに行くために野球した事なんて、考えてみたら1度もなかったんだよね。仲間と一緒に勝つ事だけを考えていた」
ようやく珠姫が反応を示す。
押さえていた不満を爆発させる様に吠える。
「でも、ヨミちゃんならプロに行ってスターになって大金持ちになれる!」
詠深も気持ちを込めて大声で返した。
「プロよりも、タマちゃんと一緒の野球の方が楽しい!」
そして鋭い直球が珠姫に向かう。
キャッチして珠姫は訴える。
「プロのレベルの高い打者との対戦の方が、今のヨミちゃんには相応しいよ!」
「私は、高校最後の夏、菫ちゃんと稜ちゃんの二遊間で投げたかった!」
そこへ芳乃が冷たい声で言った。
「私は新越谷野球部を私物にするつもりはないから、それは許さなかったよ」
菫が頷く。
「それで良いわ。私も稜も納得している」
稜も頷く。
「逆に先輩だからって、実力のある後輩を差し置いてスタメンなんて惨めだしな。そんな贔屓されたら後輩たちに恥ずかしくて退部するしかないぜ」
菫の背番号は4から14に。
稜の背番号は6から16に。
思い出し、詠深の声に苦渋が滲んだ。
「私も納得はしている。でも心残りだから。このままプロに行ったら絶対に後悔する。プロは私から逃げない。たとえタマちゃんと一緒じゃなくても、プロは4年後にもう1回確実にチャンスが来る。でも、この4人で野球ができるチャンスはこれが本当に最後」
「ヨミは珠姫と野球を続ける為だけじゃなく、私と稜と続ける為に「今を」選んだのよ」
「言っておくけど、私と菫だって3年になってから最高のお手本が近くにいたお陰で、2年の頃よりもレベルアップはしているんだぜ? 公式戦で披露できなかったけどな」
「それは紅白戦や練習の動きで分かっているけど」と、珠姫。
「最初は私とタマちゃん、そして息吹ちゃんと芳乃ちゃんの4人で始まった高校野球だったよね。そして息吹ちゃんは自分の道を選び、芳乃ちゃんもスポーツドクターになるっていう新しい目標を定めて、私たちとは違う場所に行く」
「大学野球は、ヨミちゃんにとっては回り道かもしれないよ?」
「そんな事をまだ言うんだったら、分かった、私、大学野球で完全燃焼して野球を辞める!」
パァン! 詠深のストレートが珠姫の左手に吸い込まれた。
カラーボールなので綺麗にホップしていた。
絶句する珠姫に、詠深は笑いかける。
「タマちゃんは覚えている? 1年秋の咲桜戦。あの時、私は野球終わってもいいって思って投げた。あの時はバカやったと反省している。でも、あの時とは違う意味で大学で野球辞めても良いって、思った」
「本気で言っているの、それ」
「大学野球で完全燃焼した後、プロっていう続きがあるんだったら、その時に野球続けるかどうか、考えても良いかなって程度。分かった、今から私、ずっと隠していた最低最悪の本音を打ち明けるね」
詠深は腹の底から叫ぶ。
嫌だったんだよ、3年の夏は!
菫ちゃんと稜ちゃんがレギュラーでなくなって!
最悪だった!
9人ギリギリの頃が一番楽しかったんだ!
なにがレギュラー争いだ!
後輩がレギュラーでムカついた!
ムカついたんだよ!
ハッキリ言って、芳乃ちゃんにも!
後輩たちは私達を慕ってくれたけれど、最低最悪な気持ちだけれど、アイツ等さえいなければ、菫ちゃんと稜ちゃんがレギュラー落ちで控えにならなかったんだ!
こんな結果になるなら、新入生なんて、たくさん入って来なければ良かった!
「ホント、最低ね、軽蔑するわ」と菫。
「うわー、最悪だぜ、マジで」と稜
「ま、心底から嬉しいけどね」と菫。
「だから私と菫はヨミに付いてくわけ」と稜。
「また1年の頃みたいな野球を一緒にやろう、タマちゃん」
弱小校から、この4人と新しい仲間で、強豪校をぶっ倒す。
新越谷野球部みたいな名門復活なんて目指さない。王者に、強者に、強豪側になった今の新越谷野球部みたいなチームは、むしろ倒すべき対象だ。
言い方は悪いが、2部リーグでも低迷している今の珠川大学に有力選手が来ることはありえない。プロ入りやノンプロを志す有力選手は他の大学リーグや1部リーグの強豪校を選ぶに決まっている。つまり詠深たち4人が活躍してチームが躍進しても、それは4年間だけの仮初の黄金期であり、新越谷野球部の様に名門になる可能性は、ほぼゼロだ。
それを見越しての、チーム選び。
ワクワクした笑顔で、詠深は珠姫を誘う。
「まずは首都大学リーグ2部を優勝。そして入れ替え戦に勝って翌年の1部に昇格。その年に1部リーグを優勝。そしたら翌年春のインカレ春季リーグに首都大学リーグ代表で出られる。そこも勝って全国出場権を獲得。そこからいよいよ目標――大学日本一、全国大学野球トーナメントを制覇しよう」
今でも忘れられない。
高校1年の夏――梁幽館に勝った時の高揚。
あれは仲間とでなければ味わえない感動。
プロや強豪校では不可能なカタルシス。
「またチャレンジャーに戻りたい」
この4人で一緒に。
「とりあえず今は、それしか頭にないよ。細かい事はどうでもいいんだ。この4人でだったら、公式戦じゃなくて練習試合でも、強豪校にどんどん挑んでいこう。結果は大事じゃないよ。途中で負けてもいい。また私にとってのかけがえのない仲間と強敵に挑む、その事が今の私の野球の全て」
再び珠姫でボールが止まり、彼女はボールを見つめていた。
その目を見て、芳乃が告げる。
「私がヨミちゃん達をサポートするのは、これで本当に――最後だね。珠姫ちゃんの気持ちが吹っ切れたら、その瞬間に私の新越谷での役割は、終わり」
珠姫が芳乃に向け、大きく頷く。
「ありがとう、芳乃ちゃん。今から司令塔は私が担当する。このカラーボールは一生の思い出として大切にするね」
「そのカラーボールの代わりに、全国制覇できたらそのウイニングボールを贈ってね」
珠姫は迷いを吹っ切った笑顔で応えた。
決意は固まっている。
「もしもさ、大学野球終わってプロから声がかからなかったら、私はこの4人が中心になって草野球チームを作りたいな。実は草野球チームにも、ちゃんと公式団体とリーグ戦があるんだよ? タマちゃん知っていたかな?」
「それくらい知っているよ。うん、ヨミちゃんがプロ引退したら、この4人で草野球チームを作って公式戦に殴り込もう」
「まー、私は野球を仕事、職業野球なんて元からゴメンって主義だから草野球、賛成だ」
「あんたも私も、プロ云々どころなんてプレイヤーじゃないでしょうに」
わいわいと4人の会話が弾む。
そんな中。
芳乃はそっと1人で去った。
お互いに声は掛けない、そんな静かな別離。
明日また、教室では普通に友人として会話する。
だが仲間としては過去の関係だ。
詠深たちは未来へ進んでいく。
芳乃という過去を思い出に変えて。
「続きをやろうか、ヨミちゃん、菫ちゃん、稜ちゃん。高校2年の夏の全国が終わった後からの、チャレンジャーだった頃の私たちの野球の続きを。先輩達、希ちゃん、息吹ちゃん、白菊ちゃん、そして芳乃ちゃんが居なくなっても、この4人で」
日が落ちて暗くなるまで、4人はキャッチボールを続けた。
◆Chapter08:姉と妹
「ただいま、芳乃」
帰宅した息吹は自室を必要最低限だけ片づけた後、芳乃の私室のドアを開けた。
受験勉強に集中している妹の邪魔はしたくなかったが、一応、声だけは掛けようと思ったのだ。学習机に座り、芳乃は息吹に背を向けたまま振り返らないで応える。
「おかえり息吹ちゃん。皇京大の合宿どうだった?」
「守備練とフィジカルトレばかりで、ホントしごかれたわ。体中が筋肉痛よ」
「春季リーグ戦に出るからでしょ?」
息吹が目を丸くした。
「よく分かったわね。4月1日に入学して1週間後にスタメン予定だとか、私も白菊も知らされてビックリだったわよ。私は3番セカンド、白菊は5番DH」
基本オーダーは1番・小陽、2番・怜、3番・息吹、4番・理沙、5番・白菊。
状況によっては1番・息吹、2番・怜、3番・小陽、4番・白菊、5番・理沙。
この2パターンを使い分ける計画だ。
「そうでなければ、この時期から強引な合宿なんてさせないと思っていたから」
「こういうのってアリなの?」
「インカレ春季リーグは各大学リーグの代表校しか出られないし、そのレベルの強豪校だったら普通そこまで切羽詰まる選手層にはならないからねぇ。進学させる高校側も通常はこんな「特別課外実習」を許可して出席扱いにしないし。それに入学後のレクリエーションなんかも犠牲になるよ。決して褒められた話じゃないかな」
「11月の頭から、また1週間ほど行ってくるから。私と白菊の意思を確認しないで決定事項になっていたわ。ウチの学校はどうなっているのかしら」
もう軽く身一つで行ける状況で、寮での生活も快適だったので息吹に不満はない。
白菊は喜んでいた。まさか春季リーグから公式戦にレギュラーで出られるなんて予想していなかったと。その反面、入学直後から普通の大学生活とはおさらばで、いきなり野球漬けの日々となってしまう。
「可能ならば毎年 皇京大から特待や推薦枠でウチの部員を採って欲しいからね。理事長、校長は打診されたら嫌とは言えないよ。どうせ今年だけの超特例だし」
「じゃあ後輩の進路のためにもしごかれに行くわ」
「そうだね。もう息吹ちゃんと白菊ちゃんは、これから卒業まで高校にはあまり顔を出さなくなるね」
「うん、そうなる。で、希は?」
「ラインで連絡取ってないの?」
「連絡は取っているけど、希からは簡単な返信だけだった。色々と大忙しだろうから、そりゃ当然だろうけど。明日、学校で会えるなら会いたいな、って」
「希ちゃんが学校に来るのは、あとは卒業式だけだよ」
「やっぱりそうか」
出席日数をクリアしているので、必要な用事がなければ希はもう学校に顔を出さない。
11月には球団側からのメディカルチェック(これに問題があれば契約が白紙になる場合も)が控えているし、プロ入りに備えてのトレーニングと人脈作りに集中する。最優先は年明けの新人選手合同自主トレに向けての調整だ。
光が紹介したトレーナーに師事して、徹底的にフィジカルアップおよび光が4月から取り入れた神経系やビジョン系トレーニングを始めている。
息吹は壁に掛かっているカレンダーに目をやり、
「ハドバンは日シリに進出だから、シリーズが終わるまで希は光先輩とも会えないか」
日本シリーズに進出するセリーグとパリーグの代表チーム以外は、すでに秋季キャンプに入っている。ちなみに2軍や1軍半の選手の一部は、10月からフェニックスリーグに参加していたりもする。
残酷な話であるが、この秋季キャンプ前に戦力外通告が行われるのだ。
芳乃が言った。
「12月のファンフェスで一旦福岡に戻るけれど、11月の契約更新が終わったら光先輩すぐにこっちに帰省するって。来年1月の自主トレキャンプに行くまで、1度は学校と野球部にも顔を出すし、日程調整して新越谷の皆と集まろうって連絡を取っているよ」
「キャプテンと理沙先輩もそう言っていたわ。結構マメに連絡取り合っていて驚いた」
「幹事を頼まれているから楽しみしていてよ。光先輩、費用は全額出してくれるから。金額は2人の秘密だけど、聞けば驚く額が私の通帳に振込済だよ。もちろん領収書は光先輩に提出だけど、余った分は私の進学用の準備金でいいって」
医学部志望の芳乃は東大理Ⅲを受験する。
将来はスポーツドクターを目指す。
「来年春から東京の独り暮らしだから、正直いってお金は凄く助かる。私は息吹ちゃんと違って大学生活にお金かかるし、医学部に進んだらそんなにバイトできないから。光先輩も家賃高くてもセキュリティがしっかりしたマンションにした方がいいって言ってくれて」
「いくら援助してもらったのよ、本当に」
「だから内緒だよ。学費も仕送りも親から充分に出して貰えるけど、とにかく医学部はお金がかかる。大学生活は人脈作りや付き合いも必要だから、お金は余裕あった方がありがたいからね。素直に光先輩の厚意に甘える。この恩は将来ちゃんと医者として返すつもりだし。それも約束している」
「まあ、年俸あがるもんね、光先輩」
厚意が前提はもちろんだが、将来的な人脈のキープというわけだ。
それはおそらくお互いにとって。
「平均年俸が低い球団なら1500万円。2割7分に20ホーマー70打点、なによりもOPS.850を超えているから普通2000万円はいくはず。平均年俸トップクラスのハドバンで日シリ勝ったら、2300~2600万円の範囲だと予想かな」
「額面だけ聞くと凄いけど、ハドバンのレギュラー3番打者だと思うと低いわね」
「なにしろドラ6で年俸400万円がスタート地点だからねぇ。ドラ1だったら3500万円は貰えそうな成績だよね。UZRも悪くないし、WARはチームどころかリーグでも上位の数字だから」
「離脱なしで今年と同等の活躍を続ければ、次の次の契約更新で1億円を超えそうね。来シーズンで通算ホームラン50本を達成できればいいけど」
光ともたまに連絡は取り合っているが、来シーズンは3割35本90打点OPS.900を目標に設定しているとの事だ。監督、コーチにもそのレベルを課せられているらしい。
「松岡さんは来年15勝、防御率2点台前半クリアなら次で1億円ジャストだと思うよ。プロ入り後2年で通算30勝達成は普通に球史に残る記録だし」
凛音に関しては、故障なしで順調に成長して成績を積み上げていけば、令和以降のNPB歴代最高レベルの投手になれる――そんな域にきている。彼女レベルだと普通に5~10年に1人、出るか出ないかという投手だ。
息吹が言った。
「光先輩、去年福岡に行く前に私たちの前で希に約束した「1軍で待っている」っていうのを本当に果たすどころか、まさかレギュラーでクリーンナップ定着なんて、正直いって凄いと尊敬する。芳乃は笑うと思うけれど、実は光先輩なら2年目の1軍は充分にあるって私は思っていたわ。ま、結果論って信じないわよね」
「そうだね。今だから言うけれど、光先輩は希ちゃんの前では「希ちゃんが抱く光先輩のイメージ」の為に、そう約束した。それから私にはコッソリと本音を言ってくれたよ。たぶん3~5年で1軍に上がれないまま戦力外通告だろうって。でもプロの世界を見てくるから、ダメだった時には新越谷の皆へのフォローをお願いって」
「そっか。そんなに甘くないよわね、プロの世界は」
「うん。戦力外通告までの平均在籍期間が5年以下。ドラ1の投手でも通算10勝できれば当たりって世界だよ。今年の園川さんが普通。朝倉さんはかなりの当たり。素材がNPBレベルでも超1級品だったというのもあるけれど、光先輩がギータになれたのは運の要素もきっと大きい。希ちゃんですら、故障やスランプで1軍に上がれないまま戦力外通告だってあり得る世界だから、ね」
「でも希に関しては、心配していないでしょ」
「この1年間に自信があるからね。ルーキーイヤーか、遅くてもプロ2年目には見られると思うよ、――最強2番・中村 希を。希ちゃんがプロ入りの決意を固めてから、それを目指して二人三脚でプロ仕様の打者へと造り上げてきたから」
そこで話題が途切れ、少しの静寂が流れた。
「じゃ、私もう行かなきゃ」
最低限の着替えすら、もう親に頼んで郵送済みである。
ここには「最後の」挨拶に寄っただけだ。
自宅が実家になる時、想像より呆気ないものである。
「やっぱり行くんだ」
「白菊というか、白菊の家のお手伝いさんが運転する車が待っているから」
待ち合わせの時間になった。
自室に別れを告げる際、窓から玄関前の道路を確認すると既に車は到着していた。
「追加で必要な荷物は?」
「あったら後で取りに戻るわ」
「私がまとめて送ってあげるよ。どうせ息吹ちゃんの荷物なんて高がしれているし」
「じゃあ、お願い」
「ずっと一緒だったけど、ついに「この日」が来たね」
芳乃はまだ机に向かったまま。
「思えば生まれて物心ついてから、ずっと芳乃と一緒だったわよね。高校まで」
「そうだよねぇ。双子でも早ければ中学、普通は高校で別々だから。田舎で学校が学区内の公立のみ、なんて環境じゃなければ私達みたいなベッタリだった双子は珍しいかも。大学まで一緒の双子なんて聞いたことないし」
「そういった意味では、限界まで一緒にいたわよね、私達」
「うん、息吹ちゃん――いや、お姉ちゃんは私の自慢のお姉ちゃんだよ」
息吹は苦笑した。
「今になってお姉ちゃん呼び? 私からすればあんたの方が自慢の妹だわ。まさに天才で、双子で同学年で良かったわ。学年下の妹だったらコンプレックス凄かったかも」
「私は秀才ってだけで、天才はお姉ちゃんの方だよ」
「いやいや、私が天才って」
「プレーの物まね、コピーの枠で収まっていて、まだまだ初心者的に自分のフォームを試行錯誤していた頃は、ここまでの天才だったなんて想像もしていなかった。高校2年の冬からの進化と成長は双子の私でもビックリだったよ」
「懐かしいわね、コピー打法とコピー投法」
高2の秋からは完全に止めた。
止めたというか、する必要性がなくなった。あれはお遊びの範疇だった。投手陣が充実したので、控え投手の真似事もしなくなり、完全に自分のプレースタイルと選手としての方向性を模索し始めたのだ。
模倣から模索へ。
コピーからオリジナルへ。
「まだまだフィジカルが弱いのと肩の強さを考えたら、お姉ちゃんの理想はショートよりもセカンドだと思う。新越谷だとレギュラー控えの2名も含めてセカンドが充実していたから、お姉ちゃんに本格的に取り組んではもらわなったけれど、大学では本格的に外野からセカンドへの転向を考えるべきだと思うよ」
「そのつもりだし、監督とコーチもその計画。まあレフトも続けるけどね」
「お姉ちゃんはどこに行くの?」
「いや、だから白菊の家に卒業まで下宿させてもらって、一緒にトレーニングするってば」
芳乃はようやく振り向いた。
「そうじゃなくて、お姉ちゃんはどこに行くの?」
ああ、そういう問いかけ。
「とりあえず、大学野球日本一かな」
「ヨミちゃん達も目指しているって」
「そっか。強敵だ」
「その後は?」
「やっぱりキャプテンの後を追いかけたいかな」
「怜先輩と理沙先輩、このまま活躍していくと間違いなく大卒でプロ入りするよ」
「その時は、キャプテンが入ったチームの入団テストに挑戦するわ。生憎と光先輩を追いかけてドラ1になる希とは違うから」
「その言葉が聞きたかった」
「もしもヨミ達と私たちが戦う時、芳乃はどっちを応援するのよ」
「ヨミちゃん達。大学日本一になったらウイニングボールを貰う約束しているから」
「おい」
「それに、お姉ちゃんを本気で応援するのはプロの日本シリーズかな。きっとその時にならないと本気で応援しないよ。お姉ちゃんにとって大学野球は、まだまだ成長の前段階だって思っているから」
「初心者を脱していないって自覚はあるわよ」
まだまだ身体は野球選手としてはヒョロガリの部類だ。
大学の設備にある体組織解析機で息吹のフィジカルを分析したが、無駄な脂肪と水分がない反面、全体的な筋量が絶対的に足りていない。白菊とは圧倒的な差である。大学4年間でどこまで全身に筋量を乗せていけるのかが勝負だろう。
「うん、行ってらっしゃい、お姉ちゃん」
「行ってくるわ」
そうして息吹は川口宅を出た。
黒塗りの高級車の後部座席には、白菊が乗っている。駅で別れて息吹は徒歩で自宅に来た。白菊は大村邸で待っているとばかり思っていたのだ。
「迎えに来てくれたのね、白菊」
「良かったのですか? 卒業まで芳乃さんと一緒に暮らさなくて」
「時間が惜しいわ。まだまだ色々と足りていない。白菊の家の方がトレーニング器具が揃っているし、1人と2人じゃ練習効率が違うでしょ。大学は高校野球よりも勝ち続けるわよ、私達2人で」
「もちろん私もそのつもりです」
「白菊はどこまで行きたい?」
「いずれはメジャーリーグです!」
◆EXTRA:柳大川越アフター
プロ野球シーズンオフ某月某日。
時刻は18時30分。
場所は埼玉県某所にあるホテルの大会場。グレードはそこそこだ。貸し切りになっている。
大島 留々は「とある人物」の登場を心待ちにしている。
そう、この同窓会の主役を。
通常の1クラス単位、1学年単位ではない。年代的には特殊な集まりで、留々の学年だけではなく、その上3学年も含めている。合計で4学年分が集まった。総勢で70名近い。その中心が遅刻中の待ち人なのだ。
「こんにちわ」
その主役――朝倉 智景が来場した。
皆の視線が智景に集う。
留々は破顔する。彼女が駆け寄る前に――
「遅いわよ、朝倉。待たせるんじゃないわよ」
歴代で4人揃っている元キャプテンの内の1人、大野 彩優美が苦言を呈した。
「すいません、遅れて」と、智景が謝る。
この集まりは「智景が高校1年~留々が高校3年の世代」までによる柳川大附属川越高校公式野球部の同窓会だ。一番若い留々たちの世代は、まだ高校には在籍しているものの部活は引退済みである。
「また釣りでもして寄り道か?」
捕手で4番だった浅井 花代子が智景をからかう。
この時期は寒いから無理ですよ、と智景は笑った。
主役が登場し、最高学年次の元キャプテンが乾杯の音頭を求められたが――
「ここはやはり朝倉がやるべきだろう」
なにしろ野球部史上で唯一プロ(NPB)に進んだ部員であり、おそらくこの先、この学校からNPBに高卒でドラフト指名されるケースはないと思われる。
しかしリクエストされた智景は音頭を固辞し、隣の彩優美に頼む。
「ここは私的には大野さんが最適かと」
ニッコリと微笑む智景。
その言葉に、彩優美は1つ咳払いをした後に乾杯の音頭をとった。
留々の進路は早大だ。
もちろん大学野球をやる。東京6大学リーグ。早大の先発2番手を担っている彩優美を追いかけた形というか、本当に追いかけての結果だった。他3名も留々に続いた。
当野球部において、もっとも選手層が厚いのが「智景を慕って」名門ガールズから多くの者が集った留々世代である。名門ガールズ出身のベンチ入り組の多くが、大学野球もしくはノンプロ(社会人野球)を選んでいた。中にはプロを志し独立リーグの門戸を叩く者も。
そんな彼女達の誇りは朝倉 智景だ。
会場内は明るく賑わっている。
話題の中心は智景。色々なグループに引っ張りだこで質問攻めにあっている。
タイミングを見計らい、彩優美も度々 智景に絡む。
「ったく、フカトーの松岡に1年でこんなに差を付けられるなんて、情けない。高2の秋頃までは、あんたの方が格上だったでしょうが」
「今シーズンのリーグMVPで、今やNPBを代表するエース級と比べないで下さいよ」
「泣き言を言ってるんじゃないわよ」
留々が智景をフォローした。
「いやいや、美学のエースだった園川さんですら高卒プロ1年目は厳しいッス。プロの2軍に通用しませんでしたからね。まあ、来年は盛り返すと思いますが。主に敗戦処理だったとはいえ、1軍中継ぎデビューできた朝倉さんは超凄いッスよ。しかも来シーズンは1軍当確なんですから」
「正直、自分でも今シーズンの成績は上出来だったと思っている。ルーキーイヤーから通用する自信なんてなかったから」
花代子が訊く。
「先発は目指さないのか?」
「いずれは。首脳陣もその方針ですし。でも今の私はとにかく中継ぎで1軍定着。そしてシーズン通して1軍の打者に投げる事が最重要ですね。1軍の打者に慣れないと」
「やっぱり1軍と2軍では違うッスかぁ」
「高校時代からの悪い癖、治っていないものね。もっとシッカリしなさい」
彩優美の様子に留々は苦笑する。
(大野さんは本当に「朝倉さんウォッチャー」ッスね)
「そういえば朝倉さん、こんなYouTubeチャンネルあるの知っていたッスか?」
会場に用意されていた大型モニターを操作した。
智景の活躍がアップされているYouTube動画を皆で観られる様に、と設定してもらった物である。先程まではドラゴンレイズの球団公式チャンネルによる智景の映像が流されていた。
切り替わった画面は『朝倉智景のレイジングヒストリー』なるチャンネルだ。
会場内が一気に盛り上がった。
智景が驚く。
「へえ、こんなチャンネル、あったんだ」
「今のところ世界で唯一、朝倉さんをフォーカスしているチャンネルッスね」
登録者数2300人。
動画の再生回数は1000~3000だ。
彩優美が嘆く。
「情けない。もっと有名になりなさい朝倉。あんたじゃ再生数が稼げないから、専門チャンネルがこれ1つしかないのよ」
「いえ、でも凄い凝っていませんか、このサムネイルというかチャンネル」
「編集も頑張っているッスよ。現地で直撮りした映像だってあるッスから」
1番人気の動画『ルーキーイヤー、朝倉1軍での全奪三振』を留々は再生させた。
そのハイクオリティな映像に智景は感動する。
「凄いな。ひょっとして、これ留々が?」
「いやいやいや、自分には無理ッスよ。こんな凝った編集は世界一レベルの朝倉ファンでないと無理ッスから」
「そうか。私にもこんな熱心なファンが」
(このチャンネルの運営者、大野さんッスけどね)
確かに間違いなく世界一の朝倉智景ファンだ。
自分は2番目以下ッスね、と留々は認める。2番目以下はこの同窓会の中でも激戦だ。だが、世界一だけは彩優美で決まりである。
「こういう映像は励みになる。自分で自分のこういうチャンネルは、流石に恥ずかしくて作れないからね」
花代子が言った。
「このチャンネルの再生数はショボいけど、この動画は700万再生されているぞ」
YouTube検索で[ 朝倉智景 ]と入力すると――
【令和の打撃神「村神様」村上宗子202X年 ホームランBEST10】
撃!超NPB解体新訳ちゃんねる 134万
その動画を再生し、概要欄からベスト1のところまでスキップ。
『入ったぁぁぁ~~、神宮ライトスタンドの最上段! あわや場外! 今宵も降臨「村神様」! 朝倉はこれがプロ初被弾! 村上宗子、今シーズン第48号ホームランはダメ押しの1発!』
智景が恥ずかしそうに苦笑する。
「これ鮮明に覚えてますよ」
村上宗子(22)背番号55
東京ワクルトスパローズの4番打者。
史上最年少150号、史上最年少1シーズン50号の記録をもつ「村神様」だ。
令和最初の三冠王にして、日本人最多1シーズン56本塁打を放っている。
ここで解説のナレーション。
『中日の高卒ルーキー朝倉智景ですが、素材だけを見れば「若きエース」松岡凛音にだって決して劣ってはいません。特にストレートの球速と威力。けれど修正力に優れて決して大崩れせず、かつ不調でもしっかりと試合を作れる松岡に対し、朝倉はその辺が高卒ルーキーの標準レベルを出ていません』
彩優美が言う。
「あんたは突然コントロールを乱して崩れる癖、早く完全に克服しなさい」
「プロの打者って甘いコースだと簡単にもっていかれるんで、私の制球力じゃプロ相手だとまだまだ厳しいですよ」
「でも制球力に優れた園川さんがコーナービタビタに決めても、2軍でけっこう打たれていましたから、球威だけで押せる朝倉さんはやっぱり凄いッスよ」
ナレーションは続く。
『朝倉は長いイニングを任せるのには安定感が足りなく、この村上の打席もボール先行で、スリーボールノーストライク。で、4球目のストレートは逆球でしかもインローへの見逃せばボール球なんですよ。その外れているフォーシームですが、球速はこの試合の全ピッチャー全ボールの中でマックスだったという。それをドンピシャで軽々とライトスタンド最上段ですからね。朝倉、鳩が豆鉄砲を食ったような顔してました』
アップでトリムされた智景の顔は、口を半開きにしてポカンとなっていた。
普段は飄々とした美女である彼女らしからぬ、マヌケな表情である。
「本当にプロの洗礼でしたね。でも来シーズンは抑えて見せます」
「ま、せいぜい頑張りなさい。どうせなら松岡に負けないエースを目指すのよ」
「はい」と、智景は笑顔になった。
時間は流れ、時刻は20時過ぎ。
次の予定があるから、この辺で――と智景は切り上げる事にした。
シーズンオフとはいえ予定ギッシリだ。予定があるという事はそれだけ1軍で活躍した証拠である。多忙ゆえに長居できないし、二次会にも不参加だが仕方がない。
最後の帰りの挨拶に会場が湧いた。
アイコンタクトに気が付いた留々が「見送るッス」と後に続く。
留々はこっそりと彩優美にラインした。
2人は会場を後にする。
ホテルのエントランスを出たところで、智景は周囲を見回して人目がないのを確認。
「留々。まずはこれを」
智景が差し出したのは腕時計であった。
ケースはラッピングされておりブランドは分からない。
だが、高級なのは間違いないだろう。
「中身は無難に腕時計。それなりの物かな。これは留々に受け取って欲しい」
「あれ、私にもいいんスか?」
「うん。もっと年俸が高いんだったら全員にプレゼントしたかったけど、今の年俸じゃ留々と大野さんだけが精一杯かな」
「あまり高いと受け取りにくいッス」
「20万くらいだよ。50万じゃ今の私だと分不相応だし、10万だと記念のプレゼントとしてはちょっと安いかなって思って」
そして智景はもう1つのケースを差し出す。
彩優美への腕時計。
直に渡すと断られる可能性があるから、留々を経由してプレゼントというわけだ。
「大野さんに会えるのは、また来年の今頃。来年は今年よりも良い腕時計か、別のプレゼントを用意してくる。もちろん成績と年俸に見合う形で。今から3年以内には先発ローテーションに食い込みたいと思っている」
「来年って、ラインで連絡を取り合えばいいじゃないッスか」
「大野さんに迷惑かなって。だから留々、大学で大野さんを頼んだよ。少しでも大野さんの力になってあげて。私にとって大野さんは特別なエースだから」
留々はやや呆れながら言う。
「素直に大野さんに言えばいいと思うッスよ」
智景は寂しそうに苦笑した。
「言ったら大野さん、困るか怒るかのどっちかだと思うから」
「ま、大野さんの様子は早大野球部に入ったらラインで小まめに報せるッス。援護とフォローも私にお任せッスよ。自分へのこの腕時計はその報酬って事で」
笑顔を残し、智景はタクシーを拾って去った。
留々は内ポケットからスマホを取り出す。
通話中になっており、繋がっているのは――
「聞いての通り、大野さんへのプレゼントを預かったッスよ。お二人の関係は、こうやって付かず離れずがベストなんスかねぇ。橋渡し役の苦労も分かって下さいッスよ」
通話先から聞こえた愚痴の数々は、精一杯の照れ隠しにしか思えなかった。
◆EXTRA:主将・岡田 怜の休日
――12月初旬。
皇京大学硬式野球部専用学生寮。
時刻は21時30分。
岡田 怜の明日は完全オフだ。
理由は背中の軽い張り。疲労が原因との診断で、休養を摂るための練習オフ日である。
よって厳密には休日ではなく休養日だ。明後日の午前中に医務室で診断を受けて、練習メニューを調整する予定になった。
「怜は明日、なにをするの?」
理沙がノートPCで講義のレポートを作成しながら、怜に訊いてきた。
怜は今、理沙の部屋でくつろいでいる。
「予定外のオフだからなぁ」
背中の軽い張り。言い出し難いが、実はすでにほぼ消えていた。だが、休養が決定しているので、今さら「休養は取り消してください」とはいかない。元々からして怜は「オーバーワーク気味」と心配されており、適度に休息を摂れと監督とコーチ陣から注意されている。
「明日は日曜だもの。埼玉に帰ったら?」
「う~~ん、私1人で帰っても」
そこにライン通知。
確認すると息吹からである。年末年始の予定について相談したい、とあった。いいよ、と返信するとノータイムラグで息吹から電話がかかってくる。
「どうした? 息吹」
『キャプテンと理沙先輩は年末年始、帰省するんですか?』
「いや、今年は帰省せずに寮生活だ」
『それって普通なんですか?』
「強制じゃないぞ。希望者は普通に帰省できる。毎年だいたい10人くらいは帰省するみたいだな。でも、みんなほぼそのまま残って、自主練とかしながら年末年始はチームで過ごすっていうのがウチの伝統だ。大晦日の年越しは食堂に集って鍋を囲むし蕎麦も食べる、初詣も残った部員全員で行くぞ。おせちとか、餅つきとか。まあ、私と理沙は今年が1回目になるが」
『それ、いいですね』
「大学時代にしか味わえない貴重な年末年始だ。今から私と理沙も楽しみにしている」
『じゃあ、今年の年末年始、私と白菊もそっちで過ごして良いですか?』
「ああ、来たいのなら歓迎だ」
ついでに他愛ない雑談をしてから通話を終えた。
「今年の年末年始は楽しみね、怜」
「そうだな。なんだかんだで、この寮が今の私たちにとっての家で家族だ」
そこでノック。
「洗濯物の回収ですよ」
ドアを開けて顔を出したのは、同じ1年で4軍の千恵だ。
割と仲が良い。
「なんだ怜もいたのね」
洗濯物を入れる籠の中から、衣類とユニフォームを千恵は洗濯袋内に回収した。
そんな千恵に怜は誘いを入れる。
「そういえば明日、4軍は練習オフだったよな。気晴らしに遊びに行かないか?」
千恵は半白眼になる。
「あのねぇ、新キャプテン殿。あたし達4軍と3軍はオフの日こそ集中して自主練できる貴重な時間なの。1軍2軍とは違って普段の練習日はそこまで追い込めないし」
「そうか。自主練ってどこでやっているんだ?」
「学生用体育館と体育の授業用ミニグラウンド。他の部活やサークルに抑えられてしまった場合は、市民球場とか公園内グラウンドを有料レンタル」
「暇だからサポートしに付き合おうか?」
「いいって。1日だけ来られても邪魔。サポートなら1軍のやればいいじゃない。ってか休養なんだからトレーニングから離れなさいよ」
理沙が言った。
「完全休養だから練習に顔を出すなって、監督に強く釘を刺されているのよ」
「悪いけど、うち等は来年1月頭からの入れ替え選抜期間に向けて必死なの。絶対に2軍に上がってやるんだから。あんた等3人衆くらいなもんよ、選抜期間とか気にしないで呑気にしていられるの。他のレギュラーやベンチ組だって、蹴落とされない為に内心で余裕ない筈よ。1軍から3軍落ちなんてケースだってあるんだから」
「無神経だった。すまん」
「まぁ、怜と理沙と小陽の3人はチーム内の競争なんてレベルじゃなく、ガッコの看板背負ってリーグ戦で勝つことが仕事だからね。そっちはそっちで大変なのは分かっているよ」
他の4軍の学生から千恵に怒声が飛ぶ。
「こら、なに駄弁っているんだよ千恵! 時間ないんだから早く回収して次に行け!」
「すいません先輩!」
千恵は慌てて去ってしまった。
「そうか、そうだよな」と、怜が難しい顔になる。
「どうしたのよ、怜?」
「いや、私はキャプテンなのに知識としては分かっていても、実際は分かっていなかったんだなぁ、と。このままでは新キャプテンとしてダメな気がしてきた」
「怜は余計なことを考え過ぎなのよ」
「理沙。明日の過ごし方が決まったぞ」
――翌日の朝4時15分。
目覚まし時計のアラームに起こされて、怜は起床した。
普段は6時起きなので、1時間半以上も早い。
(眠い。まだ寝ていたい)
しかし、この時間に起きたのには理由があった。
怜は集合時間である4時30分に合わせて、食堂に向かう。
そこには4軍メンバー34名が揃っていた。なお、引退している現4年生(今年度卒業見込み)も退寮するまで、そのままの寮生活(現役の練習には不参加)を送る。退寮時期は早くて年明け、居座る者で2月末くらいまでだ。
「おはよう」と、怜が挨拶すると――
「げ。マジで来たよ」
「本当に来たのか、キャプテン」
「なんて物好きな」
「今日だけ手伝われてもなぁ」
「岡田って暇なの?」
「休養なんだから休めよ」
「変なヤツ」
全く歓迎されていない様子に、怜は渋面になる。
「そんな邪険にしなくてもいいだろ。1度もやった事なかったから、みんなの仕事を体験したいと思っただけじゃないか」
千恵が名乗り出た。
「みんな、あたしがキャプテンの面倒をみるから。それでいいですよね、先輩達。――というわけで、怜はあたしと一緒に仕事して」
「頼む。なんか迷惑かけるな」
「うん、迷惑だから止めて欲しかった」
「そう言うなよ」
集合した後、清掃班、食堂班、洗濯班に分かれて動く。
34人なので、清掃14・食堂10・洗濯10だ。
班分けは1週間単位でシャッフルする。
千恵は洗濯班だ。
クリーニング室に行く。
「洗濯物は昨夜のうちに乾燥まで済ませてあるから、今から仕分けして畳んでいくよ」
「どうやって見分けるんだ?」
「部屋番の札が付いているでしょ」
「なんか凄い量だ」
「134人分あるからね」
怜が見ている中、他の面子がテキパキと洗濯物を仕分けしていく。
130以上ある洗濯物入れ籠が次々と埋まっていった。
「クリーニング屋さんに頼んであった衣類も、この時に籠に入れておく。とはいっても、クリーニング屋さんを使えるのは1軍だけだから、そんなに大変じゃない」
「そうだったのか?」
「知らなかったの? 2軍以下がクリーニングを頼む場合は自腹で、かつ自分で受付まで受け取りに行かなきゃならないって。ああ、最初から1軍だとこのルール知らないか」
怜は洗濯物を丁寧に畳む。
すると注意された。
「違う違う。そうじゃない。3軍と4軍の衣類はそんな丁寧じゃなく、スピード重視。とりあえず畳んであればオーケーだから。各自で畳み直せって感じで」
「どうしてだ?」
「バッカねぇ、あんた。時間には限りがあるんだから、3軍と4軍には時間を掛けてられないの。2軍の衣類は丁寧かつ綺麗に。1軍の衣類はそれに加えて、必要な物にはアイロン掛けをするから」
怜は内心で冷や汗をかく。
(知らなかった。全部の衣類にアイロン掛けされていたわけじゃなかったとは)
そうして配達の準備が終わる。
次は手分けして衣類を各部屋に届けるのだ。
「知っていると思うけど、3軍は同じ時間帯に朝練の準備とか設備や道具のメンテしているから、3軍と4軍の部屋は空っぽ。適当にぶっ込んでおけばいい」
「じゃあ、1軍と2軍は?」
「起こすな。絶対に物音を立てない。そぉ~~っとドアを開けて、そぉ~~っと籠に衣類を入れる。とにかく気を遣う。いい? 2軍は住民として扱う。1軍はお客様として扱う。レギュラークラスは神として扱う。それが長年受け継がれてきたウチの伝統」
「そ、そうか。初めて知った」
「そりゃあんた、最初からレギュラーだったからね」
「ひょっとして私は苦労知らずだったのか」
「だからアンタが背負う苦労は、ガッコの看板背負って試合で活躍する事だって」
洗濯班の仕事が終わり、食堂に戻る。
早朝の時間帯は調理師たちが出勤しておらず、自分たちで必要な物を温め直したり、セルフサービスで取れるようにセットしておく必要がある。
「よし、終わったな」
怜は仕事を終えた充実感と共に、朝食をバイキングしようとした。
しかし、後頭部を引っ叩かれる。
「痛いぞ、千恵」
「その朝食は1軍と2軍用だってば」
「ええ!?」
朝練の準備を終えた3軍メンバーが食堂に合流する。
今から3軍と4軍の食事タイムだ。
「バナナ、野菜ジュース、プロテイン、おにぎり、そしてハンバーガー。これ等を好きなだけ食べていいから。ただし立ったままで。あ、ゴミは分別してゴミ袋にね。間違ってゴミ箱に入れない様に」
怜は見た。
食堂の隅にあるテーブルに山盛りのおにぎりとハンバーガー、バナナ。
その隣の机には、野菜ジュースとプロテインだ。
これ、サイドメニューじゃなかったのか。まさか3軍と4軍の主食だったとは。
「6時半には1軍と2軍が食堂に来るから、それまでが食事タイムよ」
残り時間、僅かに15分だった。
「なあ、ひょっとして私の快適で不自由のない寮生活って、みんなの陰からの努力で支えられていたものだったのか?」
「予算に限りがあるからね。調理師を早出で出勤させたら費用が凄い事になるし、清掃にしても毎日専門業者を入れられるわけないでしょ。昼と夜は普通に何軍とか関係なく食べられるから、そんな大袈裟な話でもないわよ。朝の3時半に起床してまで、1軍2軍と同じ朝食を食べたいとも思わないし」
6時30分になる。
「今から1軍と2軍の朝食が終わる7時15分まで、3軍と4軍の朝練タイムよ。ただし給仕係として10名が食堂に残る。そして今朝の給仕係にはあたしも入っている」
「そういえばいつもいるな、そんな感じの」
なぜかお冷が空になったら継ぎ足してくれる親切な連中だと思っていたが、仕事として役割分担していたとは。今の今まで、あまり気にした事はなかった。
1軍と2軍、総勢55名が食堂に入ってくる。
基本的に時間厳守だ。
全体朝練が始まるのが7時30分なので、その時間までに食事を摂れば問題ない。
見慣れている3軍4軍の給仕係に混じって壁際に立っている怜(キャプテン)に気が付き、1軍2軍メンバーは誰もが怪訝な顔になった。平然としているのは事情を知っている理沙くらいだ。
小陽が怜に話しかける。
「どうしたの怜? 何かの罰ゲーム?」
「違う、気にしないでくれ」
千恵が怜に教える。
「食事中はお冷とお茶が空になったら継ぎ足すのよ。それから食事後に、特定の人には新聞とかデザートとかを運ぶわ。2軍以上が定位置の人は必要な一覧表が作ってあるから」
スマホの画面を見せてくれた。
「私の欄はどうなっているんだ?」
レギュラークラス
岡田|お冷のみ
金子|お冷、カスタードプリン(火、木)
藤原|お冷のみ
(良かった。あまり手間は掛けさせていない様だ)
「これ廃止した方が良くないか?」
「冗談でしょ? 給仕して貰う為にもあたしはレギュラーを目指すんだから。どうせ当番制だからそんなに回ってこないし。あんた余計な改革とかしないでよ。大きなお世話だから」
――1軍と2軍の朝食タイムが終わった。
「さあ、テーブル上のトレイを回収して、簡単に食器を洗っておくわよ」
調理師が出勤してくるのが8時30分なので、少しでも負担を軽くしておく。
食べ終わりの片付けまで4軍がやっていたとは、初めて知った。
怜は申し訳なく思う。いたたまれなくなり――
「これセルフサービスで片付ける方が良くないか?」
「こういった格差も2軍以上を目指すモチベーションになるから、余計な心遣いは逆に迷惑よ。それに慣れれば、この手の共同作業も遣り甲斐あるものだし。そもそも不満に思うなら退寮・退部すればいいだけの話。ってかキャプテンだからって、試合や練習以外で余計な口出ししないでよ。寮生活の規律は4軍の領分よ」
それに、と千恵が真顔になる。
「130人以上の集団生活だから、個々人それぞれで自分の事を勝手に全部やる、だと洗濯1つとっても逆に能率悪くなるし、こういった仕組みの方がトータルでは楽なのよ」
「なるほど」と、怜は感心した。
言われてみれば、確かに不満そうな者は1人もいなかった。
この朝と夜の雑事以外は、1軍から4軍の寮生活にそれ程の差はない。逆に1軍メンバーの方が夜間はミーティングなどで時間が拘束されたりする。
朝練が終わり、道具等の片付け、グラウンド整備を3軍が行えば、そこから先は午後の練習が始まるまで普通の学生生活になる。とはいえ、今日は日曜だが。
オフである4軍以外は、休憩を挟んで午前中の練習に入る。
午前中、怜は大学図書館で調べものを片づけた。
野球部外の友人3名と学内のカフェテラスで、少しだけ豪華な昼食を楽しんだ。
それから普段は足を向けない構内を散策する。
穏やかでのんびりとした時間だが、やはり練習したいなと怜は思う。
朝から夕方まで、寮には4軍の学生が2名待機する決まりになっている。
1名が巡回と簡単な清掃(半分は受付での待機)。
もう1名がエントランス脇にある受付室で郵便物を受け取ったり、電話番をするのだ。万が一、火災や事故などが起こった場合、すぐに現場に駆けつけて大学内の防災センターに通報する役目もある。無人には絶対にしない。
講義の出席率にかかわるので、その辺はしっかりと管理されてのローテーションだ。
受付室は快適空間なので、この仕事を嫌がる者は皆無である。むしろ公然と講義をサボれるので、一部には人気であった。
午後2時を過ぎ、寮から呼び出しの電話がきた。
来客がいるので急いで戻ってこいとの事だ。来客の名前は教えてくれなかった。会ってからのお楽しみらしい。
友人達と別れて、怜は学生寮に戻る。
帰ってから応接室に入ると――
「光、久しぶりじゃないか!」
新越谷時代のチームメイト、川原 光がいた。
「久しぶり、怜ちゃん」
「なんだ、来るなら来るで連絡してくれれば良かったのに」
「驚かせようと思って。理沙ちゃんには電話で伝えていた。練習中だったから軽く顔見せしたよ。元々パワーあったけど高校時代より飛ばす様になっていたね。最先端のデータ解析装置に、コーチだけじゃなくトレーナーもいて、流石は一流大学だと思った」
お土産、とケーキが入った箱が差し出された。
アンリ・シャルパンティエのケーキセットだ。
「とにかく座ってくれ」
「うん。じゃ、遠慮なく」
2人は応接室のソファーに対面で腰かけた。
「いい選手寮だね。立派で綺麗で」
「ま、まぁな。光も選手寮だろ」
「うん。ウチの選手寮も立派だけど、こんなオシャレな感じじゃないかな」
「3年前にフルリフォームしたらしい。各部屋も寮というよりもちょっとしたホテル的な内装になっている。ここに何不自由なく快適にタダで住めて、なんていうか、ありがたさが身に染みているよ、特に今朝」
「今朝? なにかあったの?」
「なんでもない」
「でも親元を離れて生活だと、食事は寮母さんが用意してくれているけれど、洗濯が大変というか面倒だよね。全部をクリーニングは逆に手間がかかるし。遠征先のホテルなんかでも、本当に洗濯が大変」
「は、ははは。そうだよな、うん」
怜の頬が引きつり、背中に冷や汗が流れた。
「背中は大丈夫?」
「理沙から聞いたのか。実は、言いにくいが昨日の夜の時点でほぼ治っていた」
「それなら良かった」
ドアが開いて、お茶菓子が運ばれてきた。
「あ、お構いなく」
「ありがとう。ついでにこのケーキ、1つずつ今日の当番で食べたら、残りを私の部屋の冷蔵庫に入れておいてくれ」
「分かりました、キャプテン」
「本当にもうキャプテンなんだ」
光は嬉しそうに目を丸くする。
「うん。監督の方針だ。実力最優先。今の2年と3年、つまり来年度の3年と4年が谷間の世代になってしまって。その影響で。だから息吹と白菊にも早々にレギュラーとしてスタメンしてもらう。遊びじゃない。大学の看板を背負って野球をしている」
「あ、あの~~」と、お茶菓子を運んできた4軍学生は、まだ立っていた。
「どうした?」
「いえ、キャプテンにじゃなくて、ハドバンのギータ、じゃなかった川原選手ですよね?」
「はい」
「サイン、していただけませんか!」
シャツを2枚、そして油性マジックを差し出して、深々と頭を下げた。
2枚あるのは受付室に待機している相方の分である。
客人に失礼だぞ、と怜が注意しようとしたが――
「喜んで」と、光はサインと握手に応じた。
サインと握手が終わり2人きりになってから、怜は光に言った。
「流石に慣れた感じだったな。やっぱりNPBの人気選手になると知名度が違うな」
「ファンサービスも仕事のうちだから」
人気が出てくれたのはラッキーだったよ、と光は苦笑いだ。
開幕から圧倒的な投球で名前を轟かせた凛音とは違い、ある意味、怪我の功名で得た知名度だ。それが人気に繋がった。
「今だから言うけれど、初ヒット初ホームランの次の試合の第一打席で送りバント失敗した時は、もう駄目だ、もうスタメンで使ってもらえないかも、次の日に2軍に落とされるって絶望したよ。レギュラー獲るまでは1つのミスで出番なくなるって、常に崖っぷちの気持ちだった」
「ギータ命名の元になった「伝説の犠打失敗」か」
イージーな送りバントを失敗した直後、光は絶望的な半泣き顔で慌てて走り出し、しかも滑って派手にズッコケてしまう。当然、アウトというかゲッツーだ。この世の終わりみたいな落ち込み具合で、光は一塁からベンチに戻る。
自由視点再生が可能になった最新の超高画質カメラ(球場内に約300設置)は、そんな光の半泣き顔を無駄にハイクオリティな映像で記録していた。
幸い、その後の打席でタイムリー2塁打を放ち、ミスは帳消しにしているが。
前日のお立ち台にて言い放った「小技も得意」というフレーズと、この犠打失敗の様子、そして光の半泣きと派手なズッコケ走がループ的に組み合わせられた複数のMAD映像が、合計で3000万再生というバズを果たす。
球団公式チャンネルもバズにあやかろうと、犠打失敗MADの終わりに「小技が得意と思っているのは本人だけ」「小技は下手くそ」という監督、コーチ、各選手のコメント(台本)を追加した動画をアップして、公式チャンネルの動画でトップクラスの再生数を誇る。
「あのバント失敗以来、一回もバントどころかエンドランのサインすらないけど」
「まあ、ニックネームが付かない選手が大半なんだから、割り切るしかないな。球団公認でグッズにも記載され、ウィキペディアにもしっかりと載っているし」
「ウィキペディア、そこそこ間違った情報書かれているよね。新越谷野球部に入ってからの初の練習試合で、場外ホームランを打った事になっているし」
そこからお互いの生活について話が盛り上がる。
「――やっぱりペナントレースを戦い切って、なおかつそのハードスケジュールの合間にトレーニングやデータ分析してレベルアップしていくのは、並大抵の苦労じゃないな」
「仕事、だからね。今の私にとっての野球は」
「プロ野球、か」
「芳乃ちゃんが怜ちゃんと理沙ちゃんの大卒プロ入りに太鼓判を押している。芳乃ちゃんの分析だから間違いないよ。だから4年後に同じ舞台で試合する事を楽しみにしている」
「光には悪いけど、今はそんな先の事は考えていない。プロ云々は4年になってから考える。ただ今のチームと仲間で野球がしたいんだ。母校の為にも勝ちたいし。野球だけじゃなく大学生活も充実しているしな」
「大学生活かぁ。ちょっと羨ましいかな、青春っぽくて。学生だけの寮生活もいいなぁ。それに怜ちゃん、高校時代よりも楽しそうに見えるし。高卒でプロに進んだのは後悔していないけどね。でも大学リーグにキャンパスライフかぁ」
大学進学だった場合、光は特待生で早大へ進む事が内定していた。
強豪大学とノンプロの誘いも多かったが、プロとの二面待ちで特待生枠をギリギリまで確保してくれたのが、早大だったのだ。結局お断りになったが。
「高校と大学では違った青春って感じかな。高校時代、最初は10人しかいない中でのキャプテンだった。光が入って11人になって、3年になったら1年が15人も入ってくれて」
「一気に賑やかになったよね。その代わりベンチ入りできない子も出ちゃったけど」
「そこはな。新越谷の今の1年、20人以上いて咲桜、美学、梁幽館に負けないレベルの連中が揃っている。「埼玉3強」から「埼玉4強」というより「埼玉3強」と「埼玉最強」って評判だ。OGとしては誇らしい」
「秋の新チーム、ほとんど1年がレギュラーらしいし、それで関東大会準優勝だから埼玉高校野球界は当分 新越谷時代が続くと思うよ。特に二遊間コンビの子たちは間違いなくプロに来る。正直いって守備だけならすぐにでもプロの1軍で通用しそう」
優勝の咲桜と並び、春の全国出場は決定的だ。
新越谷はこれで5期連続の全国。すっかり全国常連かつ優勝候補筆頭、つまり春夏春の全国3連覇を期待されている。
そして話題は詠深に及ぶ。
「ヨミちゃんらしい選択をしたと思っているけど、私としてはここで、また高校時代と同じく皆で揃って欲しかった」
「ウチに来ていたら珠姫はすぐに1軍で正捕手争いだ。ヨミは間違いなく即エース。菫と稜も最初は2軍だろうが、じきに1軍に定着するだろう。卒業後を考えれば「皇京大野球部の1軍」出身というブランドは強いと思う。でも、あの4人はそういうの興味ないだろ」
「だね。進んで弱小校に行って、また11人しかいかなった頃の野球を再現しようだなんて、これは戦ったら強敵だよ、怜ちゃん」
「生憎とヨミ達にも、他の大学にも負けるつもりはない。まずは先に、今年の春季リーグとトーナメント制覇で大学野球日本一になる。チャンピオンとしてヨミ達を待つよ」
高校時代を思い出し、怜は語る。
「新越谷時代、正直いって希とお前は毛色が違っていた。希とお前のバッティングを目にして、ああ、高卒でプロに行くやつはこういうヤツなんだって密かに思っていた。それとは別に、チームの主役はヨミと珠姫、そしてそれをサポートするのが菫と稜だった。私はキャプテンで理沙は4番だったが、チームの主役じゃなかった。あの当時は理沙と一緒に脇役に徹するって思っていたんだ。ヨミは凄い投手でその未来の為にも、って。でも、今は、今の私と理沙は少しだけ違う――」
130名以上いる仲間に対して、詠深の為の脇役では、申し訳ない。
新越谷時代の仲間と比べて、今の寝食を共にする家族は決して劣ってはいないのだから。そして詠深だって同じ気持ちの筈だ。
「そっか。そういう意味もあったんだ。ちゃんと高校時代よりも成長していたね。今の怜ちゃんは高校時代よりも頼もしく見える」
「皇京大は私のチーム、私が主役だ。そして理沙も。元・新越谷の小陽も揃っている。130名以上いる今の仲間たちが「私がチームの顔だ」と言ってくれている。だから高校時代みたく、ヨミと珠姫にチームの主役を譲りたくなかったのかもな」
「それでいいと思うよ。芳乃ちゃんから聞いている。今の2年生にとってのキャプテンは今でも怜ちゃんだって」
気が付けば時刻は午後4時を過ぎていた。
「もう行かなきゃ」
「残念だ。予定あるのか?」
「凛音と合流してメディア関係の仕事」
「忙しそうだな。休みは取れるのか?」
「怜ちゃんと理沙ちゃんの都合に合わせて1日、完全オフを作るよ。学校に挨拶をしに行こう。それとは別にみんなで集まる同窓会は芳乃ちゃんが仕切ってくれる」
メディア関係の仕事、スポンサー関係の付き合いや挨拶回り、野球関係の付き合い、それ以外は基本的に自主トレキャンプに備えてのトレーニング—―と、光のシーズンオフは休みなしだ。実家に泊まるのも僅かに1日との事。
野球を職業はまだいいかな、と光の多忙・過密なスケジュールを知り、怜は思った。
そして時刻は午後22時。
怜の部屋に理沙と小陽が揃っていた。
「ラインで連絡を取り合っている時の光は高校時代のイメージのままだったけど、実際に久しぶりに会ったら、すっかりプロ野球選手になっていたわね」
理沙がしみじみと言った。
怜も同意する。
「シーズン100試合以上もNPBトップレベルで戦っていれば、相応にレベルアップしているよな。今シーズン118試合スタメンだっけ? 凄い試合数だ」
「私達もコーチやトレーナーのお陰で、高校時代よりも飛躍的に伸びたつもりだったけれど、光は完全に別人への進化って雰囲気だったわ」
「夢と目標に向けて、光に負けていられないな」
小陽が笑った。
「その前向きな姿勢は、今朝の見習い4軍と何か関係しているの?」
「そうだな。みんなの協力あっての寮生活だと身に染みて実感した。私も来年度から新キャプテンとして新入生を迎える身だ。今よりもっとキャプテンらしくしないとな」
「引退した4年が退寮したら、もっと気楽にキャプテンっぽく振舞えるわよ。怜の新キャプテン、今だから言うけれど怜と理沙以外の全員を集めて、監督が是非を確認した。反対は4年生で5人だけかな。1年はもちろん現2年3年の反対はゼロよ」
「そうか。頑張るよ、キャプテンを」
「そんな怜の決意を祝して、光からの差し入れを食べましょうか」
理沙が紅茶を淹れる。
怜が冷蔵庫からケーキの箱を出した。
それを見て小陽が喜ぶ。
「アンリ・シャルパンティエじゃないの!」
「へえ、そんなに有名なんだ」
「インスタにアップするわ」と、理沙。
「こんな時間に油分と糖質の塊を摂るなんて、アスリート失格だな、私達は」
「今だけは普通の女子大生よ」
箱を開けた瞬間、理沙の手からスマホが落ちた。
3人とも愕然となった顔で箱の中を見つめる。
ケーキの代わりに、見慣れている来客用の饅頭が敷き詰められているではないか。
その上にはメモ書きが。
[ 高級ケーキ、ゴチでした、キャプテンwwwwww ]
◆間幕:菫と稜
11月中旬。
藤田 菫は川﨑 稜と共に市立図書館へ向かっていた。
そこで武田詠深、山崎珠姫と合流して勉強する。
受験勉強だ。
肌寒くなった道を2人で歩く。
「そういえばヨミのヤツ、本気で河川敷での事を思っていたのかな?」
稜の問いかけに、菫は肩を竦める。
「あの二遊間は私達が良かった、新入部員がいっぱい入ってこなければ、私とあんたがレギュラー落ちしなかったのに――とかいうアレ? 数の問題じゃないと思ったわね、正直」
「まさか本音じゃねえよな? 打ち合わせなしであんな事を叫ばれてビックリだった。珠姫をその気にさせる為の演技だよな? 流石にギョッとなったぞ」
「さあ? ま、あんたのアイコンタクトは伝わったわ」
詠深が叫んだ直後、どうする? と稜が動揺した目で問いかけてきたので、自分に調子を合わせろと菫はアイコンタクトしたのだ。その辺はツーカーで伝わる仲である。
菫としてもかなり引いたのは事実だ。
後輩たちだってレギュラーと試合で勝つことを目標に等しく努力しているのは、先輩として分かっているつもりだから。
「ヨミはヨミで中学時代ちょっとあったらしいし、鈍感なあんたと違い多感だし、真っすぐな子だし、ヨミなりに真剣なのよ。それに野球の意味が私達とは違うしね」
「なんだかんだで、プロを視野に入れて野球やっている側だしな、ヨミは」
菫はこの際だから「ある事」を確認しようと思った。
この流れならば自然に訊けるだろう。
「野球といえば、あんたはどうしてR大からの野球推薦の誘い、断ったのよ? せっかく野球部での活動が評価されて、向こうから声をかけてくれたっていうのに」
自分と稜のレベルで野球推薦なんて、ものすごく幸運かつ光栄な話だ。
稜は平然と言った。
「先生から聞いたのか。菫とセットでなら受けていたぜ。ヨミと珠姫には悪いけどな。推薦を断ったのは、そりゃ大学でも菫と野球を続けたかったからに決まっているだろ。私の野球は趣味だぞ。レギュラーとか控えとか関係なしにお前と一緒じゃなきゃ意味がない。それに菫だってS大の誘いを蹴ったのは、大学でも私と一緒に野球続けたかったからだろ?」
「半分は、ね」
「なんだよ全部じゃないのかよ」
稜が不貞腐れた。
菫は真剣に話す。
「本気の野球は大学で終わり。小学から大学で計12年もやれば十分。続けてもヨミと珠姫が作ったチームで草野球よ。ノンプロとか独立リーグなんて考えていないわ。だから野球に依存した道を選ぶつもりは最初からなかったのよ。つまりスポーツ推薦じゃなくて、社会学を専攻する。それから野球を義務にはしたくないわ」
「でも大学野球は就職活動で有利にならないか?」
「稜は就職活動でのアピールの為に大学野球するわけ?」
「んにゃ。充実していて楽しければ、それでいい。だから真剣にやる。ヨミと珠姫にも付き合う。それだけかな。就職かぁ。給料が高くて福利厚生が充実してれば、どこでもいいや」
「あんたらしい能天気さね。私はスポーツマネジメントの道に進むつもり。アスリートのスケジュール管理、権利管理、総合的なマネジメントをやりたいのよ」
「へえ? 菫に向いているかもな」
「せっかく高校野球で全国を経験して、現役のプロ野球選手ともコネがあるのよ。だったらそれを武器にして利用しない進路はもったいないわ。野球に依存はしないけれど、その経験は存分に活かさせてもらうわ」
「プロ野球選手――希と光先輩かぁ。すげえよな、大金もらって野球やるとか。私はそんな責任とプレッシャーの中で職業野球やるなんて、絶対にゴメンだぜ。菫が言った通り、確かに野球に責任を背負って義務でやるのは私達には「違う」よな」
凡人だという自覚はある。
非凡な存在を知っているからだ。
「覚えている? 高校1年の秋大会、フカトーの松岡凛音と対戦した時の事」
「一生の自慢だよな、私とお前、あの松岡凛音からヒットを打っているだぜ?」
「あんたがカーブを狙い打ちしたのは見事だったわ。でも私のヒットはまぐれ当たり」
「見てて分かった。お前、無理に早めに始動した上に、かなり上の軌道めがけて振ってたもんな。なのに当たった。当たってビックリした顔、今でも覚えているぜ」
「ボール、あまり見えていなかったわ。とにかく早めに振って当たればラッキーで、ボールの上を空振るつもりだったから。ホップしているんじゃないかと錯覚したわよ。しかも次のキャプテンから更に松岡凛音はギアを上げた。球速と球質が上がった。キャプテンと理沙先輩は修正が追い付かなった。明らかに普段よりも感覚を上方補正して振っていたわ」
「しかも球威に押されていたしな。ありゃバケモンだったぜ。たまたま序盤に2点を運よく取れたってだけで、ぶっちゃけ打線としては完敗だったよな。勝ったといえば勝った試合だったけど、私は「光先輩が完封したから結果オーライで、こりゃダメだろ」って内心で思っていた」
勝った負けたに関係なく、あの試合以上に内容的に封じ込められた試合はなかった。
それくらい「モノ(素質)が違った」という松岡凛音のピッチングだった。
「朝倉とか園川とか黒木なんかも速かったけど、なんつーか、松岡のはボールのポテンシャルが違うって感じのフォーシームだったもんな。スケール感っていうか。そりゃ、プロ1年目で17勝するわけだ」
「でも光先輩と希だけは、修正なしの素の感覚で松岡凛音のストレートに対応して、そして捉えていたわ。特に光先輩。大振りだからミスショットでのアウトはそこそこあったけれど、振り遅れ、スイングが球威に負けるシーンがなかった。キャプテンと理沙先輩の2人とはそこが明らかに違っていたわ」
「まー、あの試合を思い返すと、やっぱプロ行くヤツは素質が違うんだろうな。ヨミはともかく珠姫は大卒時にそのレベルまで届くんだろうか」
菫は首を横に振る。
「私達が心配しても仕方がないでしょ。スカウト的な視点で選手を見れるわけでもないし。一つだけ分かっているのは、私とあんたのポテンシャルは大学野球で一杯一杯な事だけよ」
「結局、落ち着くところに落ち着くよな。人数ギリギリだったから分不相応に高校の最初からレギュラーだった揺り戻しで、最後の夏は補欠。因果応報だった」
「高校野球で終わり、だったらちょっと悔しい因果応報だけど、大学野球まで考えたら私達を抜く後輩が入ってこないで最後までレギュラーよりも、結果としては良かったわよ。やっぱりより上手くなりたいもの、野球」
「うん、野球好きとして菫と同じ意見だ。レギュラー落ちしてからの方が明らかに充実していたよな。自分の守備がこんなにクソ雑魚だったなんて、上手くなる為にはマジで実感しておいて良かったよな。それになんだかんだで、大勢の後輩に見送られての部活引退の方がいい。私達が引退して後輩たちがまた人数ギリギリとか、悲しいのにも程があるぜ」
そこで会話が途切れる。
いきなり稜がとんでもない事を言い出した。
「お前がスポーツ選手のマネジメントだったら、私はスポーツライターにでもなってみるかな。お前からネタを提供してもらって」
「あんた教養学部を受験する筈じゃ」
「志望学科を変えるぜ。スポーツライターだから、うん、きっと文学部だな!」
大丈夫なのだろうか、と菫は軽い頭痛を覚えた。
◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その3
終了画面での視聴者プレゼントの告知を撮り終わり、いよいよ座談会か。
遥菜はそう思ったが――
「そうそう。座談会の前にVTuberとしての配信についてのお知らせだ」
(VTuberで配信までやるのかヨ)
「残念だが、予算の関係で私、陽、松岡、川原の4人分しかアバターを用意できなかった。これも視聴者プレゼントと同じで現時点での知名度を優先した」
遥菜は周囲を見回す。
当事者を除くと恋美(と酔いが回っている依子)以外の全員が安堵していた。
「ペナントレース中の空き時間に雑談配信やゲーム配信をやるのには、VTuberの方が適しているとサポート会社から提案されてな。動画だけではく生配信にも挑戦するぞ」
(いや、空き時間にはトレーニングか休養だろ)
依織が質問する。
「でもVのガワって高いんじゃないですか?」
「有名イラストレーターにデザインを起こしてもらい、それを専門業者にLive2Dモデルとやらにしてもらった。4体セットで総額1000万円という安さだ」
「え? 1体で250万円? 当然、3Dモデルも付いているんですよね?」
「3Dモデルって何だ?」
依織は悲し気な顔で視線を落とした。
(オイオイ、Live2Dだけで250万円は高くないか?)
遥菜の記憶が正しければ、安くて総額60万くらい、高くても総額150万くらいでいける筈だ。これが3Dモデルになると、値段がクォリティによって跳ね上がるが。
――ボッタくられている。
多くの者がそう思ったが、誇らしげな奈緒の前で真実を伝えられなった。
奈緒は大型タブレット端末を取り出した。
そしてLive2Dモデルの画像を表示させる。
「これが私のアバターだな」
奈緒のデフォルメキャラで、よく特徴が捉えられている。
立体的な文字が浮き出てきた。
命名:なおっち
「VTuber名は「なおっち」にした」
(わざわざパワーポイントで作ったのかヨ。ってか、なにが「なおっち」だ。「なおきんぐ」や「なおコング」の方が似合っている名前だろ)
続いて奈緒は陽のアバターを披露する。
これも陽そっくりで可愛くデザインされていた。
命名:ようちゃん
「そしてこれが松岡のアバターになるが、名前については松岡が決めてくれ」
「いいんですか?」
「ああ。やはり自分のアバターの名前は自分で付けないと愛着がわかないからな。他人に付けられた名前はイヤだろう?」
「それじゃあ「りおりん」でお願いします」
「いい名前じゃないか。凛音に「りおりん」――お前の顔にピッタリな凛々しくも可愛らしい名前だ。イメージ通りだな。よく似合っている」
そして最後に光のアバターだ。
これも光そっくりにデフォルメされている。
光が勢い込んで言った。
「私のアバターは「ひかりん」にします」
「いや、名前はもう決めている」
命名:ぎー太
「え? あれ? え? だって、あれ?」
(中田お前、つい数秒前に「自分で名付けないとアバターへの愛着云々」とか言っていたじゃないかヨ! 川原、露骨にガッカリしているだろ!)
「それにお前の顔は、光とか「ひかりん」とかいうイメージとは違う気がする」
「あはははは」
頑張って笑顔をキープする光の目から、光が消えた。
(おィィ、いくらなんでも失礼だろ!!)
遥菜は痛々しくて光を正視できなかった。
そして――やっと座談会へ突入だ。
開始前、奈緒は皆に注意する。
「不都合な場面は後の編集でカットするが、野球技術や評論、持論については特に気を付けて会話してくれ」
萌が言った。
「視聴者にわかりやすく、可能な限りかみ砕いて言うのですね」
「いや、野球技術とか評論に関しては引退した大御所たちの領分だから、この場での発言はなるべく避けてくれ。ほら、今って野球系YouTuber多いだろう? そういった大御所に「生意気だ」って目を付けられると色々と面倒だ」
(お前、目上には媚び売りまくりだナ)
「落合の私流チャンネルみたく、新作ガンダムやガンプラについて誰か語ってみてくれ」
依織が真顔で言った。
「流石にそろそろ、いきなりの無茶振りは止めて下さい」
(だんだんマジで怒ってきたな、コイツ)
まずは新人4人から意気込みと目標だ。
遥菜も含めて無難に話す。
「じゃあ、次はホークスの3人といこうか」
リーグMVPの凛音から抱負を語り始めた。
「個人成績はもちろん目標を設定しています。でも、それ以上に日本シリーズ二連覇が一番の目標です。今年はチームの皆さんに勝たせてもらった日本一だと思っています。ですから、来年こそ本当の意味でチームに貢献したいんです」
光も同意する。
「私も凛音と同じ気持ちです。首脳陣からは全試合スタメンおよび主軸を打ち続けて30本塁打とOPS.900クリアを期待されています。でも、それ以上にチームの先輩方に貢献したいんです。個人成績よりもチームが勝つのが第一、その先にリーグ制覇と日本一が来年も見えてくれれば、それでいいです」
呂律が怪しげな口調で依子が言った。
「私はこの2年、ずっとファームだったから1軍の日本一とか関係ないし」
凛音と光の顔が「しまった」という表情で固まった。
というか、全員が気まずくなる。
場の空気が一気に暗くなった。
「1年目、ファームで2割6分にホームラン8本を打って今年は1軍デビューできると意気込んでいたら、研究されて2割1分にホームラン2本、二軍ですらスタメン落ちして、年俸は500万円台までダウンだ。サラリーマンの年収500万円台より金なくて辛い。このままの成績であと2~3年ダメだったら、戦力外か育成落ちだよな、マジで」
(そんな深刻な話を、こんな場でしないでくれ)
「高校時代よりも投手のデータ量が10倍くらいあって、スコアラーが全部覚えろっていうけれど、高校時代はそんな細かいデータ野球なんてやってなかったんだよ。どんぶり勘定で野球やってたんだ。コーチは投手に研究されているから研究し返せ、って言うけどさぁ。なあ、川原。お前はデータとかどうしている?」
「それは、その、普通に相手投手とシフトのデータは試合前に全部覚えますし。自身の打撃データも詳細に分析して、フォームとタイミングのマイナーチェンジは常にやってます。苦手なコースと球種は先回りして潰していかないと。高校野球と違って相手にデータとして弱点がバレると、徹底的に狙われますし」
「そうか、そうだよな。松岡はデータとかどうしている?」
「私は甲斐さんのサイン通りに投げることを心掛けていますが、相手バッターの弱点と最近の傾向くらいは全部覚えています、光と同じで」
「やっぱり1軍で活躍するやつは、熊実みたいな野球じゃないんだな。高校野球、楽しかったなぁ。大雑把にプレーできて。あの頃に帰りたい。このまま戦力外だと高卒で世間の荒波か。こんな事なら大学野球を介して大卒になっておくべきだったかもしれん」
(この場にいる者、全員が高卒なのに、大卒が良かったとか言うなヨ!)
慌てて奈緒がフォローに回る。
依子に寄り添い、優しく肩を叩く。
「細かい事は気にするな。私も高校野球とプロ野球の違いに悩んだが、コーチに「お前は高校時代のままでいい。打率2割5分で良いと割り切り、難しい球は捨てろ」と。「甘い球を確実に打て、コンパクトに振れ、お前なら大振りは要らない」と言われてな。それで1軍に上がれて、気が付けば4番になりファンから「お前が必要、中田奈緒」と言われる様になったんだ。お前もお前のままでいい、かもしれん」
(ちょッ、最後に小さく「かもしれん」とか、保険をかけやがっタ)
「な、中田。ありがとうな、ありが――ウッ!」
げろげろげろげろ~~。
まだ二十歳になったばかりで酒を飲み慣れていない上に、飲み過ぎだった依子は盛大に吐しゃ物をぶちまけた。着弾点は奈緒だ。食事の席が阿鼻叫喚になる。
惨状に、依織がパニックだ。
「な、奈緒さん、服が服が! ゲロまみれに」
そんな依織を奈緒は冷静に諫めた。
「みんな落ち着くんだ。私の服なんかよりも、久保田の介抱が優先だ。ほら、久保田、まずは水を飲んでから、ゆっくりと横になるんだ。何も気にするな」
「奈緒さん、久保田さんの介抱は私がやりますから、とにかく服を」
「服なんてどうでもいい。久保田の体調が最優先だ。それに会話の内容は重過ぎるからカットしなければならないが、このトラブルはYouTube的にはイケていると思う。生配信だと大惨事だったが、吐しゃ物は編集でモザイクをかければ良いからな」
しかし依織はダメ出しした。
「いえ、このシーンは視聴者の為にも全カットするべきかと」
店舗スタッフと撮影スタッフが協力して、依子のゲロを掃除する。
依子は座敷の隅で横になって休んでいた。
そして奈緒は着替えの為に一時退席だ。
店のオーナー板長が言う。
「中田さんには大変お世話になっておりまして。去年のオフから個人的な付き合いもあり、贔屓にしてもらっています。今回のYouTube撮影に関しても、事前に来店して他のお客様へ自ら挨拶回りをしておりまして。とても礼儀正しく立派な人です。流石は若くして日ハムの4番打者になるだけの事はあります」
「そうですか、事前に奈緒さんが自分自身で挨拶回りを」
(小林のヤツ、なんか感動してやがるが、それって別に普通の行いだと思うゾ)
依織が感極まった声で言う。
「私は今の奈緒さんを誤解していたのかもしれない。梁幽館の頃の奈緒さんは、もういなくなってしまったのかもと。気のせいか、今の奈緒さんはお金お金お金お金、と金ばかり。梁幽館時代は真摯に野球のみに打ち込んでいたのに」
(そりゃ、高校時代は親が扶養してくれてるから、金の心配なんて要らないしナ)
「でも、私が尊敬する奈緒さんの本質は全く変わっていなかった!」
遥菜は周囲の面子を見回す。
全員(陽と依子を除く)が、感動した風の表情をしていた。
(こいつ等、将来は詐欺に引っかかりそうだナ)
オーナー板長が笑顔になる。
「本当に中田さんは立派な方なんですよ。当店にも陽さんと共に、サイン色紙とサイン入りユニフォーム、そしてお弁当を含めた数多くの球団グッズを寄贈して頂いております!」
「私も高校の先輩後輩という関係だけでなく、人間として奈緒さんを尊敬してます」
「はい。当店にも陽さんと共に、サイン色紙とサイン入りユニフォーム、そしてお弁当を含めた数多くの球団グッズを寄贈して頂いております!」
「素晴らしいですよね」
「当店にも陽さんと共に、サイン色紙とサイン入りユニフォーム、そしてお弁当を含めた数多くの球団グッズを寄贈して頂いております!」
「ええ、と」
「当店にも陽さんと共に、サイン色紙とサイン入りユニフォーム、そしてお弁当を含めた数多くの球団グッズを寄贈して頂いております!」
依織が黙り込む。
額にはびっしりと汗が浮かんでいる。
「当店にも陽さんと共に、サイン色紙とサイン入りユニフォーム、そして」
「あ、あのぉ!」
震えを抑えた声で、凛音が言った。
「さ、さ、差し出がましいかもしれませんが、この場の全員のサイン色紙とサイン入りユニフォーム、そして各球団の公式グッズを贈らさせていただければな、と。費用は全額、私が負担しますので。ほら、来年の年俸は私が一番高いし」
笑顔のつもりの微妙な表情で、凛音が申し出た。
オーナー板長は笑顔を輝かせる。
「ありがとうございます! いやぁ、なんか申し訳ないですね。ちょっとだけ催促したみたいな感じになってしまいまして。流石は中田さんのご友人だけある。催促する気なんて少しもなかったんですけどね」
「催促だなんて、そんな。催促されたなんて微塵も感じていませんから」
魂が抜けた感じの顔で、皆が首を縦に振った。
オーナー板長はご機嫌で厨房へと戻った。
ふぅ、というため息を由比が一つ。
メモ帳のページを破り、なにやら書いてから遥菜に手渡した。
変な文字が書かれている。
「田辺先輩、これは?」
「私のサインよ。今の件、私の分もアンタがやっておいてね、松井」
(こ、こ、こ、コイツ! 私に丸投げしやがったゾ)
そこで遥菜のスマホに着信が入る。
ディスプレイには[ 大友琴羽 ]
反射的に出てしまう遥菜。
「琴羽か? どうした?」
『食事会、どうなったのかと思いまして。そろそろ終わりの頃合いでしょうか?』
「まだ一次会だ。琴羽は何している?」
『亜莉紗ちゃんとの食事が終わったところです』
ちなみに琴羽と黒木 亜莉紗は慶應大学に進学する。
「亜莉紗もいるのカ」
『それはそうと、田辺先輩はどうでしたか? プロでも所属先が同じで先輩になるんです。間違っても失礼な――』
「そうだヨ、聞いてくれ、私の眷属! その田辺のヤツが!」
「田辺のヤツゥ?」
その声で、遥菜は我に返る。
由比が鬼の様な眼光で遥菜を睨んでいた。
(し、し、しまった!)
つい熱くなって状況を失念していた。
「ねえ松井。気のせいか先程から所々、この私に対しての不満げな態度と空気が感じ取れるのだけれど、それは気のせいかしら?」
『またやったのですね、遥菜ちゃん。とりあえず後でかけ直します』
通話が終わった。
ついでのこのピンチも終わってくれればと、遥菜は心の底から願う。
願いも虚しく、ピンチは継続中だが。
「め、め、め、滅相もありません先輩。尊敬する田辺先輩に不満なんて、そんな、ある筈がないじゃあリませんカ」
助けを求めて周囲の者に視線を送る――が、誰も視線を合わせてくれない。
というか、露骨に遥菜から視線を逸らしていた。
(くそ。薄情な連中め!)
ようやく奈緒が戻ってきた。
スポーツウェアに着替えている。
「どうした田辺。なにを怒っている?」
「いえ、松井が少々ね。生意気というか」
「何があったのは分からないが、先輩だったら後輩を守らなければダメだ。先輩という立場を利用するのも言語道断。お前は生意気と言ったが、私が知る松井は少しだけ口は悪いけれど決して悪気があるヤツではない。田辺も先輩として歩み寄ってはどうだろうか。他人に厳しくする以上に自分に厳しく、だ」
由比は苦笑しつつ、肩を竦めた。
「ま、中田がそう言うのならば無礼は不問にするしかないわね。もちろん言い付けは守ってもらうけれど。今後はうっかりと心の声を発音しないようにね、松井」
「は、はい!」と、頷く遥菜。
(助かったゾ。ひょっとして中田は良いヤツかもしれないナ)
依織が感激の声をもらす。
「やっぱり奈緒さんは奈緒さんだった」
「どうした依織。変なヤツだな」
「いえ、なんでもありません。それよりも手にしている服、随分と綺麗に洗濯しましたね。まるで新品じゃないですか。高そうな服なので心配しましたよ」
「いやゲロまみれのは流石に処分だ。これは新品だ」
「え? つまり新品がもう一着?」
「最後に私1人で撮影する予定だったが、このハプニングで今から撮影する事にした」
奈緒は服のブランドとスポーツウェアのブランドを紹介した後――
「当チャンネルに衣装提供して頂いているので、概要欄のリンクから購入できます。特典として「中田奈緒のYouTubeを観た」で全品15%オフになるので、視聴者の皆さまは是非とも購入してくれ」
依織の目が、死んだ魚の目になった。
――続く。
◆Chapter09:新越谷高校受験勉強部
市立図書館のロビーに、待ち合わせていた菫と稜がやってきた。
珠姫と詠深は10分前に2人で来ている。
「じゃあ、勉強しようか」
最初の挨拶を軽く交わしたのみで雑談はせず、4人はエントランス先のゲートを通り中に入ると、静かで集中できる2階のテーブルがある一画に行く。
調べものができるから図書館に来ているのではない。PC、テレビといった余計な物がない空間だからこの場を選んだ。なによりも雰囲気が静寂である。
黙々と問題集を解いていく。
4人だけで期間限定にて結成した「受験勉強部」である。受験難関校ではなく、かつ全員が合格圏内だからこその同好会的な集まりだ。芳乃の様な超高偏差値の難関校に挑戦する受験ガチ組にはそんな余裕はない。
ちなみに受験戦争は「地頭に優れている」部活組が部活引退して、受験勉強に本格参戦してきてからが本番になる。残酷な話だが、勉強オンリーだった組が伸び悩む中で、元部活組が勉強オンリー組を秋から冬にかけて成績をごぼう抜き、は珍しいケースではないのだ。要は伸びしろの問題である。
事実、芳乃もガンガン成績を伸ばし、東大理Ⅲと京大医学部の模試でC判定⇒B判定⇒B判定⇒A判定と合格圏内に捉えていた。
しばらくして、ふと稜が言った。
「そうそう、私、文学部に変更するから」
稜の台詞に詠深が驚く。
「どうして? 稜ちゃん教養学部だったよね」
ちなみに詠深と珠姫は体育学部である。
詠深の希望で、2人一緒に同じ学部同じ学科を選択した。野球以外でもなるべく一緒にいられるように、という意図だ。
「ちょっとスポーツライターになろうと思ってな」
菫が呆れた声を出す。
「ついさっき思い付いたのよ」
珠姫は感心する。
「そうやってすぐに決断して行動に移せるところが、稜ちゃんの長所だと思う」
「悩みがないだけでしょ」
菫の言葉に、稜は反論する。
「失礼な。この私だって悩んだ事くらいあるんだぜ」
「うそ。稜ちゃんが?」と、詠深。
「お前までもかよ、ヨミ。たとえば、だ。1年の夏大会が終わってから左打ちに転向しただろ? あの時は割と本気で悩んでいた」
「確か私と芳乃で「希に訊いてみたら」とアドバイスしたんだっけ」
「ああ。出塁率が悪かったからな。打順も最初は5番だったのが、6番に下げられて」
「で、1年の秋大会では、6番に留まるどころか9番か8番で上位に繋げる下位打線で固まったってオチだったわね」
「うるせー菫。それを言ったら最終的に私とお前はベンチウォーマーだったろ」
気を緩めると、つい野球の話題になる。
少し声が大きくなりがちなので、珠姫は釘を刺そうとした。
すると――
「司書さんに睨まれているわよ」
見知った人物が、珠姫より先に声をかけてきた。
菫がとっさに謝る。
「あ、すいませんでした」
詠深が目を丸くした。
「ええと、貴女は確か」
なかなか名前が出てこない様子に、菫と稜が気まずそうな顔になる。
とはいえ、珠姫も思い出せない。
彼女は苦笑しつつ名乗ってくれた。
「吉田美月よ。久しぶり」
姫宮高校の卒業生。姫宮とは公式戦以外でも練習試合を何度か行っていた。
美月は4番センター。兼任投手でもあった。
図書館だと込み入った会話は周囲に迷惑である。
せっかくの再会、という事で詠深たちは場所を近くの喫茶店に移した。
美月の紹介である。
1人500円以上の注文で2時間以上勉強しても良い、というルールが設けられている店なので、勉強場所にしている学生も多い店だ。BGMにジャズが流されているので、図書館ほど会話に気を遣う必要がないのが強みである。
採算度外視の趣味経営だから可能らしい。
稜が感心した。
「コーヒーにケーキ1つで2時間も粘ってオーケーとは、いい穴場を見つけたな」
他の面々も同意だが、美月は注意する。
「ただし昼と夜の食事時は混雑するから居座らないっていうのが暗黙の了解よ」
「それはそうですね」と、菫。
稜が美月に質問した。
「吉田さんって今、どの大学? それとも大学以外?」
「美月でいいわよ」
「じゃ、美月さん」
「浪人生よ。受験、失敗しちゃってね」
気まずい雰囲気になったのを悟り、美月は明るい声で経緯を説明した。
昨年――同じ姫宮高校の金子小陽と共に、皇京大野球部のセレクションに挑戦して合格を勝ち取った。しかし面接と小論文だけで入学OKな推薦枠とは違い、受験自体は一般枠で通過する必要がある。その受験当日、美月はインフルエンザにかかりコンディション最悪でテストを受けた結果、やはり不合格に終わってしまう。
滑り止めには合格していたが、どうしても小陽と同じ大学に通いたかった。
故に浪人を選んだのだ。
「夏の終わりまでは、今年も皇京大を受験するつもりだった」
声のトーンが落ち、美月はそこで口を噤む。
珠姫は確認した。
「つまり皇京は諦めた、というわけですね」
「うん。結果論だけれど皇京に受験失敗して良かったって思っている。卒業後の進路でどうしても皇京じゃなきゃダメってわけでもなかったし」
稜が言った。
「なんでだよ。なんか理由あるのかよ、美月さん」
詠深が辛そうに稜を遮る。
「稜ちゃん、それは酷だよ、きっと」
「武田さんの察しの通り、ううん、藤田さんと山崎さんも分かっているか」
美月は自分のスマホに「とある大学野球の記事」を表示させて、皆に見せた。
それは「金子小陽の特集」だ。
「――皇京3人衆」
稜も色々と察し、苦虫を嚙み潰した様な顔になる。
特待枠で入学した岡田 怜は即レギュラー。他の2名――強打の4番・藤原理沙、センス抜群の司令塔・金子小陽も5月頭には主力としてレギュラーに抜擢されていた。皇京大の育成システムでメキメキと頭角を現した3人はチームで不動の存在としての立場を確固たるものにし、野球部内で3人衆と呼ばれ、それがマスコミにも浸透したのだ。
特に、小陽。
新越谷出身でそれなりに有名だった理沙は1軍スタート。早期のレギュラー固定も期待通りで別に意外ではなかったのだ。しかし小陽は違う。全国には縁がない姫宮高校出身で完全に無名の存在。セレクション合格で3軍スタートである。
だが入部してすぐにコーチの目に留まり2軍に昇格。そこから3日の練習で他のコーチとトレーナー、なによりも監督が評価して1軍に昇格。で、理沙と共にレギュラーだ。
こんな素材がどうして無名のまま弱小の姫宮高校に埋もれていたのか。
理由は、新越谷高校の不祥事だ。
それが原因で姫宮高校に転校し、1年間も公式戦出場機会を奪われた。加えて地区3回戦レベルのチームでは、最後の夏も注目を浴びる事なく終えてしまう。
だが、大学野球であっという間に花開く。
しかも因縁があった新越谷高校出身の2名と共に。そんなストーリーがマスコミに受けた。大学側も3人組としてマスコミへの広告塔に起用、1年後期からは理沙と小陽に特別奨学金を支給して、トータルで怜と差がない同等の待遇にしている。残り3年以上も在籍するし、宣伝費として考えれば3人の特別待遇は費用対効果抜群だ。
順調にいけば大卒プロ入りを目されている怜と理沙とは異なり、小陽は卒業後はノンプロ(社会人野球)に進む予定で、早くも複数の企業が大学側に獲得の意思を非公式に伝えているとの情報だ。社会人野球チームのスカウトの多くは、小陽のプロ入りの意思なしという早期の表明を大歓迎しており、3年後は争奪戦になるだろう。
「仮に私が受験に合格していても、4人衆にはならなかった。私だけ2軍昇格が精一杯。大学側も学校の宣伝としての小陽の売り出しを考えれば、私の存在は邪魔だったかも」
自虐気味に言う美月。
「金子さんとは連絡を取り合っているんですか?」
珠姫の質問に、美月は首を横に振った。
「皇京を再受験しないってラインして、野球を続けるかどうか決めるまで、連絡を絶ちたいって私から小陽にお願いした。それきり」
稜が悲しそうに言う。
「なんでだよ。友達だろ。一緒に姫宮に転校して高校野球を最後までプレーした仲なんだろ。1学年違いでも同じ大学に行けばいいじゃないか」
「去年の受験前は小陽と話していた。大学3年の秋までは2人で1軍に上がれればいいねって。それを目標に一緒に頑張ろうって。でも私の目は節穴だった。一緒にプレーしてたのに、小陽の凄さを全く理解できていなかった。つまり、それくらい絶望的な差があった」
珠姫にはその言葉の重みが分かる。
同じチームだった中村 希の凄さを本当の意味で理解できていなかった。川口息吹、大村白菊の素質を見抜けていなった。1学年上の川原 光がNPBで主軸打者として通用する未来なんて想像だにしていなかった。それは彼女たちの潜在能力を見出せるだけの素質が、自分には備わっていないという残酷な事実。
選ばれし者と、そうでない者の絶対的な差。
(希ちゃんは分かっていた。光先輩の凄さを。だからこそあそこまで慕っていた。私は希ちゃん程には光先輩は凄いとは思っていなかった。怜先輩と理沙先輩と同程度の打者だと思っていた。結局、それが私という凡才と希ちゃんという天才の差だ)
自分が思う「ヨミちゃんは凄いピッチャー」は、彼女のボールを受けるキャッチャーだからこそ分かる事に過ぎなく、他のツール(野球的ファクター)についての審査眼など全く特別ではなかったという事である。
(そういえば、美学戦で諸積さんに3ラン打たれた時も、完全に諸積さんの力量を見誤っていたっけ。節穴だな、私の目)
「後輩として入学しても小陽に余計な気を遣わせるし、迷惑をかける。きっと岡田と藤原にも。今や大学野球の注目選手で名門皇京大の広告塔でもある小陽と、無名の浪人生の私。もう、住んでいる世界が違う」
菫が言った。
「ちょっと難しく考え過ぎじゃないですか? だってしょせんは学生野球ですよ。1軍とかレギュラーが全てじゃないと思いますけどね。確かに金子さんの1学年後輩は周囲の目を気にする必要があるかもしれないけれど」
詠深が菫の言葉に続く。
「私は美月さんの気持ち、わかる。やっぱり友達とはできるだけ対等でいたいって思うし、レギュラーがみんな友達だったら嬉しいなって。タマちゃんには後から叱られましたけれど。それは違うって。でも、気持ちとしては否定できない」
大きくため息をつき、美月はコーヒーを飲む。
気持ちを落ち着かせてから、
「そっか。私は小陽と対等でいる方法を模索していたのかも」
「あー、そういう事か。理解したぜ美月さん」
「あんた、言葉遣い、もうちょっとなんとかしなさいって」
「気にしないで、川﨑さん」
「稜でいいですよ。菫のことも菫でいいです」
「確かに菫でいいけれど、なんであんたが勝手に決めているのよ」
「うるせーな、細かいことは後回しだ菫」
「はいはい。――で?」
「美月さんは皇京に入っても、姫宮時代みたいに金子さんと一緒に野球ができないのが不満ってわけだ。別にレギュラー云々じゃなくってさ」
「そうね。小陽と一緒なら2人揃ってずっと2軍以下でも別にいいと思っていたのは、本当のところよ。2人一緒にレギュラーなんて高望みはしないけれど、2人揃って1軍だったら最高だなって」
「つまり私と菫、それからヨミと珠姫みたいなもんだな」
「あ、それで思い出した。えっと、どうして武田さん、珠大を選んだの? というか特待生じゃなくて一般受験するみたいだし。引退後の保険に大卒ってドラフト候補は何名かいたけれど、武田さんなら強豪大学を特待生かスポーツ推薦で選び放題だった筈」
去年の埼玉で最も有名なプロ入り見送りは、梁幽館の元4番で主将だった高橋友理だ。ドラフト指名確実視されていたが、プロ入りは大卒後と意思表示してプロ志望届は未提出だった。彼女は立大に進学し、1年生4番として東京6大学リーグの本塁打王に輝いた。
「ヨミのことはヨミでいいぜ。それから珠姫のことは、そうだな、タマキンで」
「え」と、驚く美月。
菫が稜の頭を引っ叩いた。
「面白くないわよ、その冗談。珠姫のことは普通に珠姫でいいと思いますよ」
「はい。そう呼んで下さい」と、珠姫。
「ヨミは皇京からスカウトの話があったが、珠姫にはなかった。理由はすでに息吹と白菊を予約済みだったから、流石に珠姫までは無理というか、皇京なら珠姫は一般入試しか無理だったんだよ。それは私と菫もだ」
むろん珠姫にも複数大学からスカウトはきていた。
実は明大からは最高条件の特待生という話も。
「ちなみに菫は「本気の野球は大学で終える」「野球に依存しない」という理由で、スポーツ推薦は考えていなかった。卒業後はスポーツマネジメントの道に進む。それは私も同じで、スポーツライターを目指す為に野球推薦は考えていなかった」
「うん?」と、菫が眉をひそめる。
「あれ、稜ちゃんって」と、詠深も首を傾げた。
珠姫は疑問をぶつける。
「菫ちゃんの将来は初耳だけど、稜ちゃんは昨日まで教養学部志望だった筈じゃ」
「細かい事はいいんだよ! つまりだ、ええと、なに言うか忘れちまったよ! とにかくヨミと珠姫、そして菫と私は一緒の大学に進んで一緒のチームで大学野球をやって、そんでもって怜先輩、理沙先輩、息吹、白菊がいる皇京大を倒す! それから大学野球日本一を目指す! NPBいっちまった光先輩と希はもうグラウンドでは会えないけれど、まあ、プロ野球選手になった2人からは色々と奢って貰えるかもしれないし! というか、怜先輩、理沙先輩、息吹、白菊もこのままだと大卒でプロ行きそうだから、最高じゃないかよ」
珠姫は混乱する。
結局、稜は何を伝えたいのだろうか?
美月も同じ様で、悩みながら、
「つまり、小陽を自慢して誇りに思えってこと?」
「違う! そうだけどそうじゃない!」
「滅茶苦茶よ、稜。あと静かにしなさい」
「ンだよ、菫~~。お前は分かってくれよ」
「無茶いわないでよ」
詠深が笑顔で美月に手を差し出す。
「私は稜ちゃんの気持ち、分かったよ。凄く伝わってきた。だから美月さん、私達と一緒に珠川大で野球をやりませんか?」
「貴女たちと一緒に?」
「私達4人、怜先輩、理沙先輩、息吹ちゃん、白菊ちゃんと別れたつもりはありませんよ。だって、大学野球で同じグラウンドに立てるんだから。チームメイトでなくなっても、今度はライバルとして一緒に野球、やれますから。野球、続けたいですよね?」
――野球、好きですよね?
「そっか、大学野球で同じリーグならば、今度は小陽のライバルとして同じグラウンドに立てる、小陽を目標に野球を続けられる、か」
美月は憑き物が落ちた様な表情になる。
稜が口を開こうとしたので、菫が慌てて止めた。
その様子に、珠姫は苦笑した。
「とはいっても、珠川大野球部に入る前に受験を突破する必要がありまして。だから来春解散予定ですが、まずは受験勉強部に入部しませんか?」
「うん、喜んで受験勉強部に入らせて貰うわ」
美月は笑顔で詠深の手を握った。
◆間幕:絶対王者
梁幽館高校の遠征用シャトルバスが新越谷高校に到着した。
正門を潜り、バス・トラック用の駐車場に停車する。
1軍とサポート要員の3軍がタラップを通り降りていく。
先頭の監督である栗田の次に下車したのが、新キャプテンである野村瑞帆だ。
5番ショートが定位置の5ツールプレイヤー。
来年度のドラフト候補である。
「久しぶり、瑞帆ちゃん」
見知った顔3名が瑞帆を出迎えた。
野球ユニフォーム姿ではなく学校制服を着ている。しかし、その制服は新越谷高校の制服とは違う。新越谷高校の者ではない。この場においては完全に部外者であった。
「どうしてお前たちが此処にいるんだ」
瑞帆は顔を顰める。
彼女の後にバスを降りる面子も、誰もが怪訝そうな表情を浮かべつつ、しかしその3名を無視してグラウンドへ向かっていく。たった1人を除いて。
「私のピッチングを偵察に来たのか」
梁幽館エース・斉藤小町が足を止めて言った。
「名目上は偵察だな、一応は」
東條蘭々はハンディカメラを掲げて答える。
長谷川美咲が補足した。
「今日、ウチはウチでフカトーとの練習試合があるんだけど、この3校合同の練習試合を偵察って名目で、レギュラーの京子ちゃんを一緒に連れ出せたわけ」
この3名――村松京子、東條蘭々、長谷川美咲は咲桜高校の野球部員だ。
蘭々は1軍中継ぎ投手、美咲は2軍の二塁手。
そして京子は3番センターのレギュラーである。
「お前たち、本当に仲が良いな」
1年2年と同じクラスとの事らしいが、チーム内での立ち位置はまるで違うのに、この3人の仲の良さは周知の事実となっていた。レギュラーである瑞帆と京子は試合を通じてSNS等で繋がった。その縁で瑞帆はすぐに蘭々、美咲とも知り合う事となる。
「ん? お~~い、詩織!」
美園学院のシャトルバスも到着していた模様で、蘭々が大声を張り上げた。
選手の列から、秋からの新キャプテン・4番キャッチャー渡邉詩織が駆け寄って来る。
「どうしてあなた達が?」
小町が言った。
「私達を偵察しに来たみたいだ」
瑞帆は即座に否定する。
「いや違うだろ、小町よ」
詩織は咲桜3人の意図を察した。
「別に今日の練習試合、ヨミ先輩に報せたり連絡を取ったりしていないけど」
京子がガッカリする。
「そんなぁ~~。息吹お姉さまに会えるかもと期待して新越谷まで来たのに。お姉さま、今日の練習試合の見学に来てくれれば良いけど」
「ねえ、詩織。ラインアドレス交換してよ」と、蘭々。
「というか、武田詠深経由で息吹お姉さまとSNSで繋がりたいぃ~~」
(いや、お前らのストーキングに川口息吹は迷惑していただろ)
詩織はため息交じりに言う。
「野球部を引退するまで「埼玉3強」同士で慣れ合うつもりはないから」
蘭々がツッコミを入れた。
「じゃあ詩織も同中の先輩後輩だからって、新越谷のエースに尻尾を振るなよ。あ、いや、もう元エースか」
(ったく、面倒クセー連中)
瑞帆は話題を変える。
「引退した3年生が来るのかはともかく、詩織ンとこのエースはウチに投げるのか? それとも新越谷に投げるのか?」
「エースは梁幽館相手に先発。新越谷には2番手よ。私じゃなくてメリー(八木監督)が決めた事だから」
「私は新越谷相手に先発だ」と、小町が意気込む。
「いや、クリカン(栗田監督)と相談して小町は美学戦の先発に変更だ。今ここで小町の成長を新越谷の新チームに体感されたくない」
小町は不満げになる。
しかし、今の新越谷打線に小町をぶつけても、最悪で自信を喪失させられる危険性があった。去年の春の全国、去年の夏の全国、そして今年の春の全国から夏の全国。夏が終わり武田世代が引退して秋から新チームが始動しているが、代を経る毎にレベルアップしている。
今年の夏の県大会。
梁幽館は新越谷に4対8で敗れた。エース武田から4点をもぎ取る健闘を見せたが、新越谷の超強力打線を抑えられなかったのだ。けれども夏の全国制覇を最後に川口・中村・大村という上位打者が引退。新チームになった秋こそは、と思っていた。
秋の県大会、新越谷に3対9で惨敗した。
互いに新チームになっていたが、力の差は広がっていたと認めざるを得ない試合内容である。しかも新越谷はローテーションの関係でエースは投げなかった。3得点のうち2点はラッキーによる点。正直いってショックだった。
京子も同調する。
「ウチも県大会と関東大会の決勝では、春の全国で当たる事を想定してBチームでいったからね。まだ、まともにはやりたくない」
Bチーム――主力の大半を引っ込めた控え中心のメンバーだ。
新越谷高校も、すでに関東大会進出が確定している県決勝ではBチームで、同じく春の全国に出場が決定的となった関東準決勝からはBチームで戦っている。
関東大会決勝こそ不運が重なり咲桜にリベンジを許す格好で惜敗したものの、県大会決勝および関東開会準決勝をBチームで勝つという選手層の厚さを示した。
県大会優勝で関東大会準優勝の新越谷。
県大会準優勝で関東大会優勝の咲桜。
来年春の全国は、埼玉から2校になってしまうが、その戦績と内容から新越谷と咲桜が選出されるのは確実視されている。逆に選考漏れだと物議を醸すのは必至だ。
蘭々があっけらかんと言う。
「Bチーム同士だと運よく1勝1敗だったけど、Aチーム同士だと今の新越谷相手は咲桜でもキツイよね。チーム力がちょっと違う」
瑞帆たち6名もグラウンドへ歩く。
梁幽館および美園学院の選手(主にレギュラー)たちが、グラウンドでアップしている新越谷の選手を観ていた。本当に試合前の軽い準備程度だが――
(レベルが高い)
瑞帆と詩織は来年のドラフト候補だ。
その「今の」瑞帆から見ても、新越谷高校の選手層の厚さは普通ではない。人数的な規模でいえば、まだ「埼玉3強」よりも少なくはある。2年生15人・1年生22人で合計37名だ。強豪校としては少ない部類だろう。対して「埼玉3強」は1年2年合計で50名を下回る年は稀である。
しかし—―現1年生(来年の新2年生)がとんでもなく精鋭揃いだ。
その上、現2年生もその1年生たちに引っ張られる形でレベルが格段に上がっている。
(ウチの1軍控えと、向こうの2軍上位が同じって感じか)
武田世代の引退をもって「新生・新越谷」第一世代は区切りが付き、今の新越谷は「新生・新越谷」第二世代として次のステージだ。
新越谷のアップが終わる。
彼女たちは自信と貫録に満ちていた。オーラを纏っている。
次は美園学院の番(アップ)だ。詩織が自分のチームの元へと駆けていった。
険しさを露わに、京子が真剣な顔で呟く。
「また強くなっている。全国4期連続出場で今年の春夏連覇――王者・新越谷」
◆Chapter10:母校凱旋
新越谷駅で怜と理沙は、光と合流した。
待ち合わせの時間丁度だ。通行人がチラホラとこちらを見ているが、地元出身のNPB選手である光に気が付いての事だろう。場所が場所なので、流石に握手やサインを求められたりはしなかった。
3人になってからタクシーを拾い、川口宅へ向かった。
芳乃に会う為である。
光と芳乃は密に連絡を取り合っていたが、直に会うのは怜と理沙と一緒で久しぶりだ。選手として大きく成長した3人のフィジカルに触れて、芳乃は喜び興奮した。
野球談議に花が咲いた、楽しいひと時であった。
後に予定されている同窓会もあるし、受験勉強も追い込みに入っている為、芳乃は怜たちの誘いを断る。一緒に『新越谷・美園学院・梁幽館3校合同の総当たり練習試合』を見学に行かないかという誘いだ。
「私が顔を出しても、今の部員や新しく入ったコーチが遠慮しちゃうから」
そう言って、芳乃は怜たちを見送った。
新越谷高校まで歩いて行こうと思っていたら、グランツーリスモが歩道に寄せてきた。
運転席のウインドウが下りる。
「駅で見かけてこの辺を回っていたんだけど、やっぱり貴女達だったか」
元・美園学院のセカンド、五十嵐優子だ。
優子が3人を新越谷高校まで送る、と申し出る。
怜たちは申し出を受けて、優子の車に乗った。
「色々と話したいから、少し遠回りしていいかしら?」
助手席の怜は快諾する。
久しぶりとなる新越谷の街並みも味わいたかった。
「約束の時間まで余裕あるから構わないが、随分と高いクルマに乗っているんだな」
「これ、なんていう車種なのかしら」
理沙の質問に優子は答える。
「グランツーリスモ。だいたい900万くらい」
「えっと、宝クジに当たったとか?」と、光。
「違うわよ。一括じゃなくてローンよローン。これでも会社員だから」
「え? 大学野球にいってないのか?」
怜は驚きを隠せない。
そういえば大学野球で優子のことは耳にしていなかった。
優子の評価と実力ならば、大学は特待生枠や推薦で一流強豪校を選び放題だった筈。それなのに、まさか高卒でサラリーマンをやっているなんて。そして社会人1年目からこんな高級車をローンとはいえ購入するとは。
「会社員は会社員でもノンプロ(社会人野球)に進んだから」
「ああ、そういうワケね」と、理沙は安堵した。
所属チームおよび企業名を優子は明かす。
優子が所属している企業は誰もが知る大企業だ。
「プロは考えていなかったし、大卒時にウチ並みの企業からノンプロのスカウトが来る保証はないと判断したの。キャンパスライフは棒に振ったけれど、院卒初年よりもずっと多い基本給で契約してくれた。もちろんボーナスや各種手当に手厚い福利厚生、退職金あり。本社勤務扱いの正社員で、引退後もチームにポストを用意してくれて、定年まで面倒をみてくれる。こんな好条件はウチだけだった」
「堅実な選択だな」と、怜。
「可能な限り長く現役を続けられて、かつ安定した高収入と引退後の保証もある。プロみたいな年俸億単位の夢はないけれど、セカンドキャリアを気にせずに野球に集中できる。ローンで欲しいクルマも買えたしね」
アナタ達、車は買わないの? と訊かれる。
怜は首を横に振った。
「国産車を中古で買う程度は可能だけれど、あまり必要ないしなぁ」
「怜に同感。買っても費用対効果は悪いわね」
「1年目からハドバンのレギュラー獲って、来年は高給取りな筈の川原さんは?」
「正直、高級車を買えるだけの余裕は、まだないよ」
「え。どういう事だ、光」
「怜ちゃん、私はドラフト下位指名だよ。契約金は1450万円しかなかった。個人事業主だから企業所属の五十嵐さんより税金も高いし、なにより相応に支出が多いの」
優子が言った。
「契約金はよくある噂通り「お世話になった人達へのお礼」で消えた、ってパターン?」
「中学時代の恩師には、ある程度。新越谷の方は向こうから先に断ってきた。学校としても藤井監督としても。だから、その分も兼ねて今日は寄付金を渡す」
約束というのは、母校へ訪問して理事長との面会である。
その面会後に3校合同の練習試合を見学し、藤井監督と後輩たちに挨拶する予定だ。
「契約金のほとんどは今シーズンの為の先行投資で消えた。具体的には、球団所属ではなくて個人で栄養管理士、専属調理師と契約したり、各種専門トレーナーとも契約した。それプラス、年間を通じての高額な特別レッスン料でほぼ1000万円がこの1年で消えたよ」
オールスター休みであったり本拠地にいる期間の休みを利用して、光は可能な限り身体のアップデートとメンテナンスおよびメカニカル改良を行っていた。これはメジャーリーガーなどでも一流選手は行っている事だ。アーロン・ジャッジなどが良い例である。
「球団所属の栄養士やトレーナーではダメだったの?」
「理沙ちゃん、それだと他のルーキーと同じレベルの成長と結果しか望めない。コーチからの技術的な指導はともかく、身体造りにおいては一切の妥協はしたくなかった。可動域と柔軟性を維持しつつ、シンプルにスピードとパワーの向上のみを追求したよ」
怜は息を飲む。
(なるほど。1年前とは別人なわけだ)
優子が感嘆する。
「ルーキーイヤーから契約金のほとんどを自己投資って、あまり聞かないケースね。だからこその1年目からの活躍なんでしょうが」
ある種、常人には理解不能な狂気じみた取り組みが「その道」のトップレベルには必要になる。その段階に来た時、なにもせずに現状維持のまま競争に敗れるか、あるいはブレーキを踏むかアクセルを踏むかが分水嶺だ。
「投手としてはともかく、打者としては『希ちゃんが慕ってくれる光先輩』のままでいたかったから。正直、高校時代も少しだけプレッシャーあったよ。打者として希ちゃんに失望や幻滅されたくないって」
「希ちゃん、か」と、理沙は苦笑した。
「私は打者として希ちゃんの気持ち云々というレベルじゃなかったから」
「私も理沙と同じだ。私も理沙も、光とは違って打者としては希に歯牙にもかけられないレベルだったと思うし、希から選手目線でどうこうという発想すらなかったよ。希に格下認定されていても、それが普通だと」
「私も諸積という天才を間近で見ていた凡才だから分かるけど、やっぱりプロ云々なんて考えなくて正解だった。天才の考えていることなんて理解できないし」
(プロ……か)
本当に今から3年後、希や光と同じステージで戦う覚悟ができるのだろうか、と怜は不安を覚える。高校時代や大学時代の今が、選手として楽しく充実しているから尚更。
打者として希に慕われる先輩――どころか、所属チームが違えば敵である。
いや、そもそも同じチーム内の生存競争に勝ち上がって1軍、そしてレギュラーに辿り着けるのかどうか。
そこから普段の趣味等に会話が移り、新越谷高校に到着した。
優子は校門前で3人を降ろし、自分は裏門から入れる来客用駐車場へと愛車を運転する。駐車後に美園学院の後輩たちに顔合わせに行く。怜たちとは彼女達の用事が終わった後にグラウンド周辺で合流して一緒に3校合同練習試合を観る。帰りも駅まで送る約束をしていた。
「岡田以下2名、入ります」
「どうぞ、待っていましたよ」
理事長室に入ると、理事長は笑顔で出迎えてくれた。
促されて来客用のソファに座る怜たち3名。
予想を遥かに上回ったこの1年の飛躍と結果・評価に、理事長から「是非とも1度、顔を見せに来てください」と連絡を受けての凱旋訪問だ。
寄付金を渡したかった光にとっても好都合だった。
この1年間についての内容および報告や、新越谷高校や野球部について会話・情報交換した後、光は封筒に入った小切手を理事長に差し出す。
「まだ少ないですが、どうかお納め下さい」
「ありがたくお受けいたします」
理事長は改めて語り出す。
「今とても多額の寄付金が集まっています。支援者・後援者も増え後援会の規模も拡大中です。野球部専門のトレーニング室の建設など更なる設備投資も予定していますし、全国へのスカウト活動および特待生制度も始めます。貴女方が起こしてくれた奇跡を無駄にせず、学校経営としてビジネスチャンスを逃さないつもりですよ」
新越谷高校は私立である。
元々から設備面では恵まれていた。
さらに資金と人材が集まってくれば、スポーツ面では公立校とは比較にならない。
今の1年生は新越谷野球部の躍進に惹かれて、自主的に日本全国から精鋭が集ってくれた、いわばご都合主義的なボーナスタイムに近い。そんな事はそうそう続かないのは明白で、今度は学校側から全国の有力選手をスカウトしにいく。
理事長との面会を終え、3人は職員室に寄った。
お世話になった教師たちに挨拶および手土産を渡し、グラウンドへ急ぐ。
そこでは練習試合とはいえど、公式戦となんら変わらない熱戦が繰り広げられていた。
◆EXTRA:瑞帆VS詩織
梁幽館と美園学院の試合は、大詰めを迎えていた。
最終7回の攻防。
先攻は美園学院で2対2の同点だ。
名門校3校の三つ巴戦という事もあり、観客の数は多い。
地元の高校野球ファンのみならず、新越谷の生徒、それにスカウトらしき者達も。
中堅校同士の公式戦より注目されている模様だ。
美園学院は背番号1のエースがスターターで、4回から3番手セットアッパーが、6回から2番手クローザーが継投、合計で3人のピッチャーを投入していた。
この試合に連勝が掛かっている。
1試合目で新越谷に5対4で勝利していた。けれども新越谷はBチーム。内容も運が味方して辛うじて勝てた、といったところか。こちらは先発2番手がスターターだったとはいえ、新越谷は先発3番手がスターターのBチームなのだから、内容的にも完勝したかった。
故に、この試合は意地でも落としたくないのだ。
対して、梁幽館は1試合目で新越谷に敗れていた。
こちらはベストメンバーの新越谷に当たり、4対0での完敗だった。よく4点で収まったという試合展開もさることながら、新越谷のエースと正クローザーから合計で散発4安打しか奪えずのシャットアウト負けという完敗中の完敗である。
故に、2連敗だけは避けたいところだ。
ツーアウト満塁のピンチ。
マウンドには先発ピッチャーのエース・斉藤小町が立っている。
それなりに安打を浴びつつ要所要所を締めるナイスピッチングだったが、相手打線が3巡目に入ってから明らかに捉えられ始めた。そして正念場の打者4巡目――
ついに小町は捕まる。
良い当たりを連発されて満塁のピンチが続く。ショート瑞帆のファインプレーでヒットを阻み本塁で刺したものの、失点していないのが不思議なくらいの打たれっぷりだ。
(もう小町は限界か?)
瑞帆はベンチを見る。しかし動く気配はない。
新越谷戦で1軍の投手を5名、使えるだけ使ってしまったという事もあるのだろう。残っているのは格落ち投手ばかりだ。一応、1名だけリリーフの準備はしている。しかし、もうここまできたらエースと心中する覚悟なのか。
バッターは4番キャッチャーの詩織だ。
プロ注目のスラッガー。長打こそ許していないが、タイムリーヒット2本を浴びている。つまり美園学院の2打点は詩織のバットから生まれていた。
カウントはワンボールナッシング。
2球目のフォーシームが、やや甘く入る。
詩織はフルスイング。
快音の残響と共に、高々と上がった打球がライトポール際へ伸びていく。辛うじてファールゾーンへ切れたが、飛距離は十分の凄まじい当たりだった。先代の4番・諸積恋美を想起させる威風堂々としたバッティングだ。
遅れて観客から歓声とため息。
(あっぶねぇ~~)
瑞帆は肝を冷やした。
ここでグランドスラムを浴びたらジ・エンドである。
小町の表情から闘志は消えていない。
思わず、瑞帆は声をかけた。
「がんばれ小町!」
その一言で、小町の闘志に火が付く。
インコース膝元へのスプリット。最高のボールだ。
この試合で1番の球を放ってきた。
詩織のスイングが始動。
シフトは引っ張りを想定して右サイドへ移動している。打ち上げればライトスタンドへのファールになる絶妙のコースと変化。一二塁間からセンターへの打球をフェアゾーンに入れれば、高確率で内野のシフトに引っかかる。
希レベルのバットコントロールがあれば、外野の前にポテンヒットを狙える。けれどもパワーヒッターである詩織には、意図してのポテンヒットは難しい。
スイングスピードは減速せず、詩織はステップをややオープン気味に修正。
引っ張るのではなく、コンタクトポイントを前方に修正しつつボールを押っ付ける。すなわち前で捌きつつ、打球を流し打ったのだ。
パワーレスな打者ならば逆方向なので打球速度は出ない。
しかし強打者である詩織の打球は違った。並の強打者の引っ張り打球よりも痛烈だ。
三遊間を強襲する火の出るような当たり。
中堅校レベルの守備力ならば一歩も動けない打球速度である。
サードの反応が若干、遅れる。それは致命的。
だが瑞帆はシフトの逆を突く超強烈な打球に反応。全国レギュラークラスの内野手であっても、ダイビングして止められれば超ファインプレーというコースへの打球――
けれども瑞帆はダイブせず、逆シングルでグラブにボールを収める。
これはポジションとしての難易度とは別次元の話。
動きのスピード、力強さ、ダイナミックな運動性能および運動能力の高さを見せつけた。メジャーリーグではチームの主役がこなす守備位置。チーム最高のアスリートが任される花形ポジション――ショートストップに相応しい華麗なパフォーマンスだ。
三塁ランナーと二塁ランナーは間に合わない。
瑞帆と二遊間コンビを組むセカンドは、瑞帆のことを分かっている。瑞帆ならばこのレベルの打球であっても「普通に」処理できると。故にカバーも迷いなく入っている。
「へい、ふたつ!」
体勢を崩したままのアクロバティックなスナップスローだが、正確かつ速かった。
二塁でのフォースアウトでチェンジ。ワンナイト満塁からのピンチを、瑞帆のスーパープレイの連発により辛くも無失点で凌いだ。
観客から声援が飛ぶ。
「流石、松井遥菜の後を継ぐ高校ナンバー1ショート!」
瑞帆が怒鳴り返した。
「松井がいた時だって私が高校ナンバー1ショートだ!」
見学している怜も瑞帆の動きに唸る。
「凄いな。高校生離れしているぞ」
光が付け加えた。
「うん、ポテンシャル的には松井さんに全く引けを取らないか、それ以上だね」
そして7回裏は梁幽館の攻撃。
先頭バッターは5番の瑞帆である。この投手に対しては試合での初打席(初対決)になるが、この程度のボールならばサク越えを狙えるという自信が、瑞帆にはあった。
(このひと振りでわからせてやる)
初球、読み通りのストレートが来た。
(誰が来年のドラフト指名に一番近いのかを!)
豪快かつハイスピードな鋭いスイング。
(いったー! バックスクリーン!)
サヨナラHRという結果を期待するが、打球はどこにも見当たらない。というか、ボールは詩織のキャッチャーミットに収まっていた。普通に空振りでワンストライクだ。「ナイピ」と、詩織がピッチャーに返球する。
(初球のホームラン狙いはダメだったか。まあいいや。もうちょいミート重視でコンパクトに振って、ツーベースから三盗を決めてスカウトにアピールだ!)
カウントが進み、ワンボールワンストライク。
変化球を待っていたタイミングだが、直球がきた。
(またゾーンに真っすぐか、舐めやがって)
「くらえ、詩織!」
バキィ! と瑞帆のバットがボールをぶっ叩く。
ちょっと力んでしまった為、イメージ通りではなかった。右中間か左中間にライナーを飛ばすつもりだったのだが――
「くはー、タイミング合い過ぎた」
センターど真ん中に打球が行ってしまった。そして角度が付き過ぎている。
詩織はデータ通りの結果に、少し悪い笑みを浮かべた。
「思い通り」と、呟く。
フラフラと上がった打球は、勢い的にはセンター定位置ほどで失速する感じだ。
しかしセンターは前進しようとして足を止めた後、逆にゆっくりと後退しようとするものの、「あれ?」という表情になり打球を追わなくなる。
「え?」と、詩織は戸惑いの顔に。
上空の風に乗ったのか、打球にスピンが効いていたのか、滞空時間の長い軌道を描き、ボールはセンター頭上どこかフェンスもオーバーしてしまった。打った本人が一番意外そうに驚き、そして喜びを爆発させる。
「よっしゃー! これでスカウト達にアピール成功だ!」
瑞帆のサヨナラ弾で、梁幽館が3対2で美園学園を下した。
◆間幕:京子、蘭々、美咲の絶望
珠姫は詠深、菫、稜の3名と共に3校合同練習試合の見学に来ていた。
試合の観戦よりも、母校に顔見せに来ている怜たちに会うのが本当の目的だ。
人だかりが凄い。
スカウトらしき人達もチラホラと。
それだけ注目選手が集まっているイベントである。
新越谷の新チームの主力にもプロ注や一流大学のスカウトが狙っている選手が多い。梁幽館と美園学院も同じである。埼玉高校野球界の頂点というか、全国レベルでみてもトップクラスが揃っていると言ってよい。
怜、理沙、光の3人とは問題なく合流できた。
美園学院OGの五十嵐優子も一緒だったのは意外であったが。
練習試合は、申し合わせた様に3チームが全て1勝1敗という結果に収まる。
「じゃあ、私たちは藤井先生や後輩たちに挨拶に行くから」と、怜。
観戦が終わり、人だかりも解散という空気。
後に予定されている同窓会でゆっくりと話そう――と、怜たちは野球部へ向かう。
3人共、この後の予定があるので珠姫たちとのんびりする時間はないとの事だ。
怜たちと入れ替わりのタイミングで。
「すいません、武田さん達ですよね?」
京子、蘭々、美咲の3人が珠姫たちの元へ駆け寄ってきた。
「ええっと、貴女は確か咲桜のセンターの」
「息吹お姉さまの大大ファンです!」と、京子。
「同じく息吹お姉さまの信者です!」と、蘭々。
「息吹お姉さまの超々ファンです!」と、美咲。
(面倒くさそうな人たちがきた)
珠姫は気持ちを顔に出さない様に努力する。
京子が質問した。
「あの、学校中を駆けずり回っていたんですが、息吹お姉さまはどこに?」
美咲も訊く。
「皆さんとご一緒な筈ですよね?」
稜が呆れ顔で回答する。
「息吹と白菊は埼玉にいないぞ」
「「「 えええぇぇええぇぇえええええええ!? 」」」
「皇京大の合宿に参加っていうか、もうあっちで寮生活を始めている感じだな。私達もほとんど息吹と白菊の顔は見ていない。学校側も認めているから、卒業まで高校にはあまり出席しない予定だぞ」
「そ、そんなぁ」と、京子はガックリする。
「でも京子ちゃん、蘭々ちゃん、息吹お姉さまの居場所が判明したから、今からでもあの可愛らしいご尊顔を拝見しに馳せ参じれば――」
「その通り! っていうか、私達3人の進学先が皇京大に決定した瞬間であった!」
「しかし今更ながら、やっぱり咲桜じゃなくて新越谷に進学しておけば」
そこで京子のスマホが着信音を鳴らした。
「はい、監督、京子です。……ええと、試合の映像とスコアブック、ですか? あ、そういえば練習試合の偵察でしたね。え、いえ、その、なんて言うか」
通話が終わり、3人は揃って青ざめる。
偵察の事をすっかり忘れていた。
「美咲ちゃん、蘭々ちゃん、今井監督がすぐに帰って来いって。凄く怒っている」
蘭々が絶望的な声を漏らす。
「あーあ、私たち死んだな」
◆Chapter11:それぞれの想い
ドタバタと場をかき乱しただけで、京子たちは珠姫たちの前から居なくなる。
嵐のような3名であった。
詠深は苦笑しつつ。
「息吹ちゃんも変な子たちに目を付けられて大変だねぇ」
「――お久しぶりです、ヨミ先輩」
美園学院のユニフォーム姿のまま、詩織がやってきていた。
どうやら少し前からその場に立っていた模様だ。京子たちの存在感が強過ぎて、その場の誰も詩織に気が付けなかった。
「あれ、詩織ちゃん。いつから居たの?」
「京子たちとほぼ同時でしたが、ちょっと話しかけ難い雰囲気だったので」
「今日は大活躍だったねぇ、詩織ちゃん」
詠深は中学後輩の活躍を喜ぶ。
詩織は珠姫たちにも頭を下げた。
「珠姫さん、菫さん、稜さんもお元気そうで」
「やっぱいいバッティングだな、詩織」と、稜。
「来年のドラフト候補だけあるわね」と、菫。
「ウチのドラフト候補も、渡邉さんみたく落ち着きがあればね」
近づいてきたのは、吉川和美と高橋友理だ。
梁幽館のOGである。和美は元エース、友理は元キャプテンで4番打者だ。
1年生にして立大4番打者となり東京6大学リーグ本塁打王の友理に、明大のエースに君臨している和美。この世代の埼玉球児は1年目から大学野球で成功している選手が多い。
稜が言った。
「吉川さん達も後輩の見学か」
友理はほほ笑む。
「戦力的には心配していないのですが、ちょっと悪い意味で個性が強いメンバーが多いって評判の新チームですから。栗田監督も操縦に苦労しそうです」
「心配はしていないけど、正直いって来年度と再来年度の全国は厳しいかな。後輩たちには私たち世代の無念を晴らして欲しいんだけどね。野村のワンマンチームに近いってのが弱点といえば弱点だ」
詩織が反論する。
「絶対王者と呼ばれる新越谷ですが、付け入るスキはあります。来年の春、いえ夏を制するのは私たち美園学院です。ストップ・ザ・新越谷を果たしてみせます」
「ま、その意気だよ後輩たち」
詠深に向き合い、友理が言い難そうに訊く。
「あの、春夏全国優勝投手である武田さんの進路、本当にマスコミに報じられている通りなのでしょうか? ちょっと信じられなくて」
詠深は立大からも特待生のオファーを受けていた。
大学とノンプロの誘いの中では、最高条件を提示したのが立大である。
「しかも珠大はスポーツ推薦ですらなく一般入試って」
詠深の選択は一部(主にネット掲示板)から「愚かな選択」と叩かれている。
それとは別に、メジャーを最短で狙う為の抜け道という邪推もあった。
「事実ですよ。廃止になっちゃって今は野球部寮とかはなくても、グラウンドと練習設備自体はちゃんとしています。4年生が引退して人数も13人しかいなかったりと、色々と前途多難ですけれど、そういった苦難も楽しみたいと思っています」
珠大は学生寮はあっても、野球部専用寮はない。
大学なのに監督とコーチが1名ずつ、しかもマネージャー0という大惨事状態である。トレーニング環境を考えて、詠深たちは一軒家を借りシェアハウスとして活用する予定だ。
「そういった環境も面白そうですね、ヨミ先輩」
「うん、野球部専用寮がない代わりに自分たちでシェアハウスをやるつもり」
「シェアハウスですか。もし進路が大学になるんだったら、京子たちじゃないけれど、私も名門大学ではなくヨミ先輩と同じ大学に行きたくなっちゃいました」
無邪気にみえるが「意思を秘めた」詩織の笑顔。
珠姫の心臓がギュッと傷んだ。
「ダメだよぉ~~詩織ちゃん。勿体ないよ。詩織ちゃんはきっとプロから指名される。だから皆の期待を背負ってNPBに進んで欲しいな、私は」
「ヨミ先輩がプロに行かなかった理由、わかります。だから私は新越谷を選ばずに美園学院を選んだ。中学最後の大会、本当はショートではなくてヨミ先輩の球を受けたかった。あのくそやろーをぶん殴ってでも、です。だけど高校では新越谷に入って珠姫さんに勝つ自信がなかったから、美園学院を選んだ」
――ヨミ先輩の正捕手に相応しい力を付ける為。
劇的なカミングアウトに、詠深は表情を改めた。
茶化して良い雰囲気ではないから。
汗が噴き出す。珠姫は心臓がバクバクするのを抑えられない。
詩織が詠深を真っすぐに見つめて言う。
「あと4年間はヨミ先輩を珠姫さんに預けます。でも、プロ入り後は私とバッテリーを組んで下さい。所属球団が同じならば、エースと正捕手になりましょう。球団が違うのならば、全日本代表の正捕手とエースとして国際舞台でバッテリー組みましょう」
「4年後、か」
「美園学院に入った時は、正直いって1軍に上がる自信すらなかったです。けれどもプロ注と評価されるところまできた今なら違います。NPBでヨミ先輩のキャッチャーになってみせます。誰もよりもヨミ先輩に相応しい捕手になってみせますから」
珠姫は詩織を直視できない。
(覚悟が、違う)
キャッチャーとしての能力で劣っているつもりはない。いや、捕手としての能力限定ならば珠姫は詩織を上回っているという自信がある。事実、周囲からの評価もほぼ同じ。
決定的に珠姫が詩織に劣っているのは、フィジカルとバッティング。
最後の夏、珠姫は背番号2だったが事実上の「詠深専用キャッチャー」だった。
エース詠深の球を受けるからという理由の背番号2。
他の投手が投げる時は背番号12の後輩が扇の要だ。その差は単純に打撃力である。
守備とリードが同レベルならば、当然、より打てる方を使う、それだけだ。
詠深は何も言わなかった。
否、何も言えないのか。
(こんなの断れないよね、ヨミちゃん)
「長居はできないので、これで失礼させてもらいます」
返事は4年後にお願いします、と詩織は去った。
珠姫をチラ見したが、少し申し訳なさそうに見えた。
「武田さん、愛されているなぁ」と、和美。
「詩織ちゃんがそんな風に考えていたなんて、初めて知りましたから」
「だけど、4年後に指名されたらNPBに進むんだよね」
一泊置いて、詠深は頷く。
「はい。詩織ちゃんに「皆の期待を背負ってプロに」と言った以上、私もチャンスが来たら逃げません。期待を背きません。指名されなかったら、無理にプロは目指しませんけどね」
その台詞は至極 真っ当なものである。
逆に「プロに行かない」と言われてしまったら、珠姫としてはショックだ。
今でも、詠深に最も相応しいのはNPBのマウンドだと信じているから。
けれど、詠深の言葉が珠姫にとって意味するところは――
和美は珠姫に向き直る。
「本当はこれを告げるのは、こんなに早くじゃなくて3年後のつもりだったんだけど、いい機会だから珠姫に聞いて欲しい」
「和美さん?」
「明大からの推薦、珠姫に蹴られた時は残念だったよ。梁幽館のスカウトと同じで、私が強く推したからね。もし特待生で明大を選んでくれれば、入学後に即正捕手だった」
ガールズ時代を思い出す。
和美のスライダーを捕れるのが珠姫しかチームにいなく、和美専用捕手としての正捕手だった中学時代。そして和美の退団と共に強打の捕手にレギュラーを奪われた。
新越谷高校に進み、詠深との再会を契機に再び野球に打ち込んだが、皮肉にも最後の夏はガールズ時代と同じ境遇になってしまった。
「高校時代に組んでいた依織はプロに進んだ。私は大卒後はノンプロにいく。もしも、珠姫がプロを目指さずに大卒後も野球を続けるのならば――」
最後に私と、ノンプロでバッテリーを組んで欲しい。
「私の理想は、現役の最後は珠姫とのバッテリーだ。私はもう一度、珠姫と組みたい。時間は4年もあるから、頭の片隅にでも入れておいて」
珠姫は詠深を見た。
詠深はちょっと困った感じの顔になる。
どうしていいか、分からない。
理想と希望と現実が、まるで噛み合っていないから。
珠姫と詠深――互いにソレを口にするのには、覚悟が足りな過ぎる。
気まずい空気を払拭したのは菫だった。
「大学入学前の受験生にそんな先の話をされても。ヨミも珠姫も、今は大学野球でテッペンを獲る事だけを考えなさいよ。そうじゃないと私と稜に失礼でしょ」
「そうだね、藤田さん。悪かったよ。今は大学卒業後の事よりも大学野球のグラウンドで会う事を考えるようにする。その時は絶対に負けないから、珠姫」
「行きましょう、和美」
友理に促されて2人は帰った。
稜が言った。
「やっと言えるんだが、怜先輩からショートメッセージきているぜ。OG会の奢りで焼肉店を貸し切りにしてあるから、私達も来ないかってさ」
「先輩達は予定あったんじゃ?」と、菫。
「光先輩も含めて予定変更して野球部の焼肉会に付き合うってよ。地元で1番の高級店だぞ。で、私達もどうかって話だ。まあ、お前たちが辞退しても私1人でもいくけどな」
もちろん4人揃って出席して焼肉を楽しんだ。
◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その4
「さて、と。ひと段落したことだし、サムネイルの撮影に入ろうと思う」
奈緒はそう切り出してきた。
遥菜にとってはどうでもいい。
もういい加減に帰りたいのだが。
「お前たちも知っていると思うが、YouTubeにおいてサムネイルは非常に大切なんだ。大袈裟ではなくサムネイルのクリック率が全てと言っても過言ではない」
依織が言った。
「単なる飲み会なので、工夫を凝らした方が良いと思います」
「案ずるな。ちゃんとコンサル会社のスタッフさんと打ち合わせ済みだ」
そして奈緒はタブレットに1枚のイラストを表示させ、皆に見える様に掲げる。

「――え?」
萌が遠慮がちに言う。
「あの、中田さん、表示させる画像を間違っているかと」
「いや、これで合っているぞ」
「確認して下さい。それ『ギニュー特戦隊』です」
「その通りだが?」
萌は視線を伏せた。
依織は絶望的な顔になっている。希は涙目だ。
遥菜は奈緒に確認する。
「つ、つ、つまり、この『ギニュー特戦隊』のイラストを中田さんが持った写真、をサムネイルにする、という解釈でいいんですね?」
声の震えを抑えられない。
奈緒と陽、(グロッキーの)依子を除く全員が、首を「ブンブン!」と縦に振った。
それ以外の解釈は断固拒否といった雰囲気だ。
不思議そうな顔で、奈緒が言った。
「私達でこのポーズをとって撮影するに決まっているだろう?」
(そんなコトを勝手に決めるなぁぁあぁああああああ!)
「おかしなことを言うヤツだな、松井は」
(おかしいのはお前の頭だよ、中田!)
絶対に嫌だ。ふざけているのか。
受け狙いで自分以外がやるのは構わないが、自分がやるのはイヤ過ぎる。
「もちろんギニューのポーズは私が担当しよう。残りの4つのポジションをくじ引きで決めようと思う。くじで外れた者はサムネイルに写れないが我慢してくれ」
むしろ写りたくない、と皆が思った。
奈緒を除く12名で4つのポジションだから、確率は3分の1だ。
(まあ、くじを外せば、助かるといえば助かル)
遥菜は他の面子の表情を探り見る。
間違いなく全員が同じ考えだろう。
自分が12分の8側になればよい、と腹を括っている顔だ。
スタッフがくじ引きの準備を終えた。
スタンダードに、筒から当たりならば赤い印のついた棒を引っこ抜く、あれである。
くじ引き開始直前に、由比が提案する。
「少し考えたんだけれど、中田。このポーズだと宴席メインと視聴者に伝わらないわ」
ハッとなる奈緒。
(流石だッ! 田辺先輩!)
なんとか中止の方向に誘導してくれ。
「だから中田がバストアップでビールジョッキを掲げた写真を差し込んで――」
(その調子だ! 田辺! 頑張ってくれ!)
今ほど遥菜は、由比を先輩として尊敬した時はない。
「言われてみれば田辺の言う通りだな。ふむ」
(よっしゃぁぁああああぁぁああ~~~~!!)
「田辺の提案を採用して、私はバストアップ写真で脇に写り『ギニュー特戦隊』のポーズは他の皆に任せる事にしよう」
「ぉぉおおおぉぉおおおおぉおいィ!」
(思いっ切り逆効果じゃないか田辺ぇぇぇええええ!)
確率が12分の5に上がってしまった。
「どうした松井? いきなり吠えて」
「あ、いえ、ちょっと喉の調整をしようと思いまして」
「そうか。発声は大事だから無理するなよ」
なんてこった。
こんな場所にのこのことやってきた過去の自分を殴りたい、と遥菜は思う。
(まあ、いい。要は外れを引けばいいんだ)
順番に筒から棒を引っこ抜いていく。
萌――色なし(外れ)
依子――色なし(外れ)
由比――色なし(外れ)
「くそ」と、思わず遥菜は舌打ちした。
せめて当たりを引いてくれ、この役立たず。
「まあ、負け惜しみくらいは見逃すわ、松井」
(地獄に落ちやがれ、田辺め!)
陽――色なし(外れ)
(あれ? あれれ?)
4連続で外れだ。
これで確率は8分の5になっている。
(気のせいか、当たり率5割を超えているゾ?)
智景――赤(当たり)
確率は7分の4に変動だ。
遥菜は強烈な不安と焦りに襲われた。
このまま自分の番まで待つのは、耐えられない。
「頼む、私に先に引かせてくれ!」
絶対に7分の3を引き当ててみせる。
そう決意してくじを引いた結果――
――赤(当たり)だった。
遥菜は頭を抱える。
やっぱり自分の番まで待てば良かった。
ちなみに当たりの面子は以下だ。
遥菜。依織。智景。光。恋美。
納得がいかない。
もう1回やり直して欲しいと心底から思う。
「良かったな、お前たち。これでサムネイルに写れるぞ」
安堵し切っている顔で由比が訊く。
「ところで中田、各ポジションはどうやって決めるの?」
「ジャンケンで勝った者から順番に選べる様にしようと思う。つまり1番の勝者はギニューを選べる、という事だ。5人ともギニューを目指して頑張ってくれ」
(うるせー、ギニューだけは絶対に御免だ!)
ジャンケンが始まる。
5人なので、準決勝⇒決勝の2回戦方式だ。
Aグループ:光、依織、智景
Bグループ:遥菜、恋美
準決勝は遥菜が勝った。
いや、勝ってしまったというべきだろう。
優勝するとギニューのポジションを押し付けられるのは確実である。
Aグループを勝ったのは光。
決勝は遥菜と光だ。
「「 ジャンケン、ぽん! 」」
遥菜はパー、光はチョキ――つまり光の優勝である。
(ふぅぅぅ~~、最悪の結果だけは免れたゾ)
もう妥協して、ギニューでなければ良しとしよう。
すると光が神妙な顔で言った。
「勝者から順番に好きなポジションを選べるとの事でしたが、私、実は小学生の頃からグルドの大ファンで。なので是非ともグルドのポーズをとりたいと希望します」
(な、な、なんだとぉぉぉぉおおおお!)
計算外の事態に、遥菜は激しく動揺する。
てっきり光がギニューで決定だと思っていたのに。
奈緒は笑顔で快諾する。
「そうか。考えてみればグルドは川原と同じでチビだもんな」
「あはははははは。別に身長に共感して好きってわけでは」
笑顔だが光の額には青筋が浮いていた。
「それでは次は松井が選ぶ番だが、ギニューにするか? それとも川原と同じく、ギニューの他に好きなキャラはいたりするのか?」
(し、しまったぁぁぁあぁあ!)
遥菜はギニューしか名前を覚えていなかった。
外のポーズをとりたくても名前を言えない。
他の面子を見ると、すかさずスマホで検索している。ちくしょう、薄情な連中め。
どうする、どうする、どうす――
「ぎ、ギニューでお願いします」
遥菜は半泣きになって項垂れた。
――続く。
◆Chapter12:同窓会
年末が近づいてきた今日この頃。
芳乃が幹事を担当した新越谷野球部同窓会が開かれていた。
この夏で引退した3年生8名と、卒業したOG3名、そして顧問の杏夏という面子だ。
浦和区元町のファミレスで集合して、かるく昼食を摂る。各自で好きな物を注文するし、特に値段制限などは設けていない、が――
「夕食は焼肉ですから、腹八分目でお願いします」
会計は全て芳乃が一括で払うので、先に釘を刺しておく。
クライマックスは高級焼肉店での食事。
普段から栄養管理を徹底しているアスリート達にとっては、貴重なチートデイでもある。
その焼肉が終わったら解散というスケジュールだ。
怜、理沙、息吹、白菊は明日の練習の為に大学の野球部寮に帰るし、光を除く他の面子は受験生だし、教師である杏夏が付いているとはいえ、光もまだ未成年なので夜遊びは厳禁だ。
特に来シーズンの準備に入っている希と光は、時間を無駄にできる立場ではない。12月に入ってからは、自主トレーニングがメインの日々となっている。
夜通しの同窓会は、全員が成人になってから、と決めていた。
つまり再来年の第3回からだ。
ホテル等の広い会場を借り切っての大掛かりな新越谷野球部OG全員の同窓会は、再来年、今の2年生15名が卒業生となってから別で行われる計画である。
そちらの方は後援会やOG会が主催の公式イベントだ。
このOG11人での同窓会は、ずっとこのメンバー固定で行っていきたい。
昼食を終え、カラオケで歌い、それからボウリング対決を楽しんだ。
これから年に1度だけの、かけがえのない時間。
時刻を確認し、詠深がしれっと言った。
「それじゃあ、後は希ちゃんと芳乃ちゃんの若いお2人で」
希が驚くが、これは芳乃の予定通りだ。
焼肉店で合流という事を確認し合い、芳乃と希の2人と、他の面子は分かれた。
「芳乃ちゃん、これからどうするん?」
「コースは決めてあるから、ゆっくりと散歩しよう」
浦和区の街並みを散策していく。
程なくして希は芳乃の左腕に、自分の右腕を絡める。
それに合わせて、芳乃は少しだけ希に身体を預け体重を寄せた。
肌寒い日なので互いの体温のぬくもりを感じる。
優しく穏やかな時間。終わりが来るからこそ、大切な今だと思えた。
歩きながら、この3年間の思い出を語り合う。
「希ちゃんは高校生活で心残り、ある?」
希は一瞬だけ言葉に詰まった後――
「――ないよ」
(本当に?)
すでに周囲は薄暗かった。
もう冬だ。
芳乃が設定している目的地が見えてくる。照明が点いているという事は、準備は問題なく整っている。照明は照明でも窓からのぞく室内灯の明かりではない。
空を彩るナイター用の照明だ。
市営浦和球場。
「草野球でもやっとるん?」
「ちょっとだけ見学していこう、希ちゃん」
合流時間まで余裕があるので、希は疑問に思うことなく芳乃に連れられて球場内に入る。ナイターで草野球が行われていると思っていたが、静寂だ。
2人はグラウンドへと踏み入った。
芳乃が告げる。
「今年だけの「特別な」同窓会をやろうと思って」
希の両目が大きく見開かれた。
高校1年の夏の終わりから、何度も何度も夢で見た。対左投手がスランプになった。光に救ってもらうまで、悪夢の様に希を苦しめ、縛り付けた、あの記憶が蘇る。
マウンドの上には、あの時と同じ姿。
大野 彩優美が其処にいる――
彩優美は希に言った。
「最初で最後、私と貴女の同窓会、そして餞別代りの送迎会を始めましょうか」
「芳乃ちゃん、これは」
「あのスランプを克服した後でも大野さんに勝ち逃げされたこと、希ちゃん、ずっと気にしていたよね。大学野球で大野さんの情報だけは細かくチェックしていたの、気が付いていたよ。だからみんなに協力してもらって、この同窓会を企画したんだ」
ベンチから詠深たちが姿を見せた。
全員、新越谷のユニフォームに着替えている。
新越谷OGだけではない。
柳大川越からも正捕手だった浅井 花代子と、この夏に引退した大島 留々もいた。
2人、いや彩優美を含めた3人は柳大川越のユニフォーム姿である。
杏夏が主審、1塁コーチャーに詠深が入る。
以下、各ポジションだ。
ピッチャー:大野 彩優美
キャッチャー:浅井 花代子
ファースト:藤原 理沙
セカンド:川口 息吹
ショート:川﨑 稜
サード:大村 白菊
センター:岡田 怜
ライト:川原 光
レフト:大島 留々
見学は菫と珠姫、そして芳乃だ。
菫が言った。
「息吹がセカンドに転向したのは知っていたけれど、サード白菊とはね」
芳乃は頷く。
「肩は強いからね、白菊ちゃん。コンバートとしては正解だと思うよ」
珠姫から渡された金属バットを、芳乃は希に差し出す。
希が使っていたバットだ。
「もちろん勝負を受けるよね、希ちゃん。勝っても負けても高1夏の無念を、心残りを払拭してから、新越谷から福岡へ、NPBへと羽ばたいて欲しい」
希は頷き、バットを受け取った。
「希、ユニフォームに着替える?」
「メットとプロテクターだけでええ」
希はヘルメットを被り、右腕のガード、右足に自打球用のプロテクターを着けた。
そして軽くストレッチをして素振り、ゆっくりと左打席に入る。
その間に、彩優美は投球練習を済ませた。
「ルールは?」と、希。
「3打席勝負よ。投手も含めてエラーの場合はノーカンで仕切り直し。安打・四死球で1打席でも出塁すれば貴女の勝ち。3タコで私の勝ち。これでどうかしら?」
「それでええよ」
菫が言った。
「3打席勝負、か。5打席勝負よりもピッチャー有利じゃない?」
「でも5打席勝負だと打者勝利条件が5の2以上になるから、そうとも限らないよ」
珠姫が言う。
「どちらにせよ他のバッター8名を挟んでの3打席勝負じゃないから、試合での3打席勝負とは勝手が違ってくると思う。特にピッチングの組み立て」
「その通りだよ、珠姫ちゃん。1打席勝負を3回繰り返すのではなく、3打席をワンパッケージとして投球を組み立てる、少なくとも私ならそう考えるよ。そして打者側も同じ。別に3打席全てヒットが必要じゃない」
第1打席――初球。
内角やや低めにフォーシームが決まる。
ノーボールワンストライク。
菫が驚く。
「速い。私が知っていた高3の時の大野さんじゃないわね」
「高3時と比較して、今の大野さんは平均球速が10キロ近くアップしているからね」
高校球児としての彩優美は、正直いってトップ・オブ・トップに類する投手とは言い難かった。県大会準決勝で咲桜打線に打ち砕かれるレベルだ。
だが、今の彩優美は大学野球界で間違いなくトップ・オブ・トップの投手の1人。
「今年、楽全イーグルスにドラ2指名されたエースが卒業して、大学3年からは文句なしに早大のエース。高校時代は指名されても支配下は厳しく、よくて育成枠だった。でも、今の成長した大野さんならば2年後はドラフト上位を狙える」
第1打席――2球目。
外角低め寄りだが真ん中付近へのカットボール。
甘いコースに、希はほぼ反射的にジャストミートする。
右中間への大飛球だ。
早くも勝負ありか、と思ったが怜が快足を飛ばしながらギリギリでランニングキャッチ。怜の守備範囲に助けられる恰好で、辛くも彩優美はアウトをとる。
「ねえ芳乃、今のは失投?」
「違う。大野さんは狙って甘い球を投げたと思う。打者が投手に慣れた第3打席に今のボールは絶対に投げられない。確実にやられる。でも第1打席で初見の球種なら、いくら希ちゃんのミート力でもそれなりの確率で守備範囲内に打球がいってしまう」
「私も芳乃ちゃんと同じ見解かな。大野さんは試合ではできないギャンブルをしたんだよ。そして大野さんは賭けに勝ち、希ちゃんは第2打席、一気に苦しくなった」
希は早打ちに失敗した。
よって第2打席は球数を投げさせて第3打席に繋げる必要がある。第2打席も早打ちしてしまうと、アウトになった場合の最終打席が不利過ぎるのだ。
第2打席――
シュートを中心に、彩優美は厳しいコースを突いてくる。
好球必打を控え、際どいコースはカットで対応する希。
タイミング、球速、球筋、キレ、変化の具合を観察していた。
ツーボールツーストライクで、7球目。
彩優美が投じたのはスライダー。しかもあの夏、希が打ち取られたコースとスピードをほぼ完璧に再現している。球速と変化のキレが落ちたが、これも彩優美の狙い通り。
覚えていない筈がない、と。身体があの時と同じ打ち方をすれば――
希もあの夏と同じ様に、されどより綺麗なフォームかつ力強くボールを捉えた。
あの時との違いは、ボールを拾った打ち方ではなく、しっかりと振り切った点。
センター前へ、美しい弧を描いてドライブの利いたボールが吸い込まれていくが、これも怜がスライディングキャッチしてしまう。打球が綺麗に伸び過ぎた。そしてセンター真正面にいったのも不運だ。仮に、もう少し右か左に打球が逸れていたら、怜は全速のスライディングで突っ込んでこられなかっただろう。
なによりも、投げた瞬間にシフトを敷いていた。
「追い込まれたわよ、希」
芳乃は動じない。
「大丈夫。希ちゃんは落ち着いている。打席内容はいい。なによりも希ちゃんはこの第2打席は割り切っていた」
珠姫が言った。
「第1打席で大野さんが賭けに出た様に、希ちゃんも第3打席の為にデータ集めと、大野さんの投球に慣れる事に専念したね」
希はこの第2打席で、映像と実物との感覚的差異を完璧に修正した。
ゾンッ!
空気が、雰囲気が、希の周辺が威圧的に重くなる。
投手へのプレッシャーが倍増。集中力がレッドゾーンに入ったのだ。
ピリピリとした空気に、彩優美が薄く笑む。
第3打席――初球。
なんと彩優美は先程と全く同じボールを放ってきた。しかしスピードだけは高校時代ではなく大学2年である今のレベルで。
ギリギリまでボールを引き付けた希はフルスイングし、ロケット弾の様な打球がライトスタンドのポール際まで伸びる。がしゃぁああん! フェンス最上段に直撃したが、ファール。安打製造機ではなく飛距離を求めた強打者の打ち方である。
高校時代の彩優美は、もう自分に通用しない――と希は威嚇的に示した。
珠姫が言った。
「完璧な当たりだった。希ちゃんに大野さんは通用していない」
菫も同意する。
「ファールで命拾いしたわね、大野さん」
「一応、希ちゃんが使っていた金属バットを持ってきたけれど、今の希ちゃんに馴染んでいるプロ仕様の木製じゃなかったのが、大野さん的にはラッキーだったと思うよ。今使っている職人さんが造った中村希モデルの木製バットならライトスタンドに運んでいた筈」
第3打席――2球目。
外角へのクロスファイヤーが決まる。
爆裂じみた捕球音が響く。これまでで最速のフォーシーム。
だが、希は確信をもって見送っていた。
菫が驚愕する。
「は、速い! 今の球速って、スピードどれくらい出ていたの?」
「これが今の大野さんのマックスだよ。このストレートのコンビネーションだけで、あの夏の咲桜打線ならば力と速度のパワーピッチで捻じ伏せられると思う。それだけのボールを今の大野さんは持っている」
本格的に彩優美が鍛え始めたのは、朝倉智景が入部した高校2年生の夏から。つまり本当の伸びしろと成長曲線はもっと後の選手なのだ。大学1年を過ぎ、ようやくフィジカルアップの芽が、本当の意味で出始める時期を迎えている。
「ストライク!」と、杏夏がコール。
「ボール半個分、スレスレでゾーンを外れていたよね芳乃ちゃん」
「うん。手を出してもフェアゾーンに飛ばすのは難しいコースだから希ちゃんは見送ったけれど、スピードとキレ、そして球威に圧倒されて先生は思わずストライクにしちゃったね」
「こんなボールをここまでとっておいたなんて」
「たぶんね、菫ちゃん、1打席勝負の繰り返しだったり、試合だったり、2打席勝負だったら大野さんはここまで出し惜しみしなかった。でも投手有利から打者有利、スターターがここから本番と言われる打者3巡目に相当する3打席目の希ちゃんは、どんなピッチャーだって抑えるのは難しい」
「うん、この第3打席にピークをもってくる最高の筋書きだよ、大野さん的には。今の2球目はボール判定でも良かったんだと思う。でも、誤審でノーツーになって、大野さんが圧倒的に有利になった」
「そして解禁する。希ちゃんも分かっている」
ゾンッ!
今度は彩優美のボルテージが臨界点を突破する。
彼女の周囲が重々しいオーラで揺らめいている様だ。
希もそれを真っ向から受けて立つ集中力。
芳乃が息をのむ。
「いよいよ来るよ、大野さんの魔球が」
「魔球?」と、菫。
「大学2年の春から投げ始めた、ううん、身に着けた魔球だよ。でも肘への負担が大きい為1試合につき数球しか投げていないから、未だに大学野球マニアやプロのスカウトしか大野さんが投げられると認知していない――魔球だよ」
「じゃあ、希ちゃんも」
「当然、知っているよ、大野さんの魔球」
変化球には亜種がある。
フォークの亜種と言えるスプリット(SFF)が有名だろう。詠深の「あの球」もジャイロスライダーの亜種――ナックルスライダーがベースだ。通常のスライダー回転ではなく、ナックル握りによりジャイロ回転を与えたボールで、ジャイロスライダーよりも高速かつ斜め下に大きく曲がり落ちる軌道のスライダーを実現している。
そのスライダーも、高速スライダーと分類される亜種、縦スラと呼ばれる亜種、よりストレートに近く手元で鋭くカッティングするカットボール(カッター)と呼ばれる亜種など、本当に様々な亜種が存在するのだ。
彩優美が投げた球種自体は、スライダー。
一定以上の球速。
一定以上のスライダー回転のスピン量。
一定以上の変化角度。
一定以上の横へのスライド量。
これ等条件を満たしつつ、ほぼ落ちない軌道を描くスライダーは、魔球と呼ばれる。
その名は――スイーパー!
希のインサイドからクロスファイヤーじみた急角度でアウトへ逃げていく、高速かつ大きな変化で横滑りしていく魔球。箒で真横に一掃するかの様な軌道は、まさにスイーパーの名に相応しいウイニングショットだ。
カットしにいけば、間違いなく微かに腰が引けて追いスイングでの空振りになる。
しかし希は迷いなくベストスイングをぶつけた。
ぎゃん! とボールが弾かれ、真後ろのネットにファールチップが当たる。
タイミングは合っている。
でも希ですらバットの先端でコンタクトするのが精一杯で、前に飛ばせなかった。
3球勝負で決められなかった彩優美は怯まない。
希が嬉しそうに壮絶な笑顔になる。なんて凄い変化球だ、と。
菫の声が震えていた。
「な、なによ、今のお化けスライダーは。高速で真横にエゲツなく曲がった」
珠姫が悔しそうに唇を噛む。
「実際に目にするのは初めてだけど、たぶんスイーパーってやつだよ、菫ちゃん。認めたくないけど、このスイーパーってボールはヨミちゃんの「あの球」より」
「大学1年までの大野さんじゃ、そもそもスライダーをスイーパー化させるだけのスピードと球威がなかったからね。ただしオーバースローやスリークォーターに比べると肘への負担は少ないけれど、多投は厳禁だよ。高確率で肘の靭帯をやってしまうから」
しかし、彩優美はスイーパーを連投する気配だ。
「待った待った! こんな変化球、私じゃ無理だ!」
キャッチャーの花代子が匙を投げる。
高校時代にバッテリーを組んでいた女房役の彼女であっても、彩優美のスイーパーは手に余る変化球だった。事実、ミットの位置がボールの軌道に追い付いていなかった。希が空振りしていたら、確実にパスボールしていただろう。
緊張感に水を差されて、彩優美が苦笑した。
「そうね。この続きはプロの1軍のマウンドから再開しましょう」
「大野さん」
希は嬉しそうに頬を紅潮させる。
「本当のことを言えば、この場で貴女に引導を渡してもらうつもりだったのよ。私じゃ朝倉と同じプロは無理なんだって。そう諦める踏ん切りが欲しかった。でも、皮肉にも逆にいけそうな気がしてきたわ。私でも後2年あれば、私だって朝倉と同じ場所に立ってまた貴女と戦える、今日の勝負はそんな手応えがあった。初めて自信を得たわ」
「先にプロの1軍で待っとるよ」
「ええ、待っていて。たとえドラフトで支配下指名されなくても、独立リーグを経由してでも、育成契約からでだって、どんなルートでも貴女と同じグラウンドに辿り着くから、必ずこの勝負の続きをしましょう」
2人は自然に歩み寄り、かたく握手した。
留々が大歓喜して彩優美の背中に抱きつく。
「大野さんの決意、きっと朝倉さんも喜んでくれるッスよ!」
「隠す意味のなくなる大学4年の秋まで黙っておいて。朝倉には今の自分に集中して欲しいのよ。それから留々」
「分かっているッス。粉骨砕身、大野さんのプロ入りまで大学でサポートするッスよ」
「違うわよ。アンタも卒業後、NPBに来なさい」
「え?」と、留々は固まる。
「今年だってプロからの調査書3通きていたし、育成指名の話だってあった筈。スカウトからの評価は私よりアンタの方が上でしょう?」
「いやいやいやいや! 正直プロなんて無理ッスよ無理。それに育成契約って年俸250万で契約金0とかが普通ッスよ。バイト以下ッス。無謀ッス。嫌ッスよ。仮に支配下契約だってドラフト4位以下だと長期的に人生設計や生涯賃金を考えると――」
育成契約――育成ドラフトだと順位はほぼ関係ない。支配下登録を勝ち取れば、その時に契約金は貰えるが、育成契約だと僅かな支度金しか支給されないのだ。そして育成から這い上がって1軍で活躍できるのは100人に1人程と言われている。投手はともかく野手はかなり分の悪い賭けだろう。
「空耳が聞こえるわね。早大を卒業後、アンタもNPBに来なさい」
「実は大手スポーツメーカーに就職するのが希望ッス。野球は大学で引退予定ッスから。未練なしッス。早大野球部はその為の人脈作りの為でもあるンスよね。自分は野球で飯を食っていくなんて、とてもとても」
「ごちゃごちゃ何か聞こえるわね。早大を卒業後、アンタもNPBに来なさい」
彩優美に睨まれ、留々は観念した。
「了解ッス。でもプロ志望届の提出と支配下指名があった場合に限定ッス。育成契約とか、卒業後に独立リーグやノンプロでプロを目指すルートは、流石に勘弁して下さいッス。野球引退と大企業への就職を許して欲しいッス」
「ま、順当にいけば、留々なら支配下の下位指名は期待できるでしょ」
「ホント、その場合は人生レベルで責任とって下さいッスよ、大野さん」
「はいはい。責任とってあげるわよ」
彩優美の留々のやり取りに周囲は笑った。
希も晴れやかな顔をしている。
芳乃は満足だった――が、
ただ1人だけ笑っていない人物、珠姫に気が付き少しだけ不安を覚えた。
◆EXTRA:YouTuber中田奈緒 その5
(だ、騙された)
目の前の絶望に、遥菜は愕然とする他なかった。
体育会系的な上下関係のしがらみで、YouTubeチャンネル『中田奈緒の埼玉魂』とやらに事実上の強制参加となってしまう。なんでも遥菜は「メンバー」とやらの1人らしい。
初回の動画に使うサムネイルでは『ギニュー特戦隊』のポーズまでさせられた。
それもド真ん中でギニューのポーズだ。屈辱であった。あれを全世界に晒されると想像すると、頭を抱えたくなる。自分は未来の日本代表ショートなのに。いずれはメジャーリーグにポスティングで移籍して5年200億円超えの大型契約、流石にメジャーでもショートは無理っぽいからメジャーではセカンドに転向、そしてワールドシリーズで優勝、スポンサー料だけで毎年10億円、オリンピックやWBCで金メダルを獲り栄光を掴み、ピークアウトした晩年はNPBに復帰し、ファンに惜しまれつつ引退後はライオンズの松井監督爆誕という(予定の)未来に対して、あんなのは黒歴史だ。
実は今日、奈緒からYouTube撮影の招集がかかっていたのだが、仮病をでっち上げて拒否していた。非常に遺憾であるが、これから先も招集がかかる度に仮病になる体質になった。これは遥菜的に不変かつ決定事項である。
そこへ高校時代のチームメイトにして遥菜の眷属――大友琴羽から誘いが来た。
共通の友人、黒木亜莉紗と3人揃って遊びに出かけようという主旨だ。奈緒の件は説明すれば分かってもらえる筈。口裏合わせは簡単だ。
そうして誘われた温水プールに、遥菜は出向く。
笑顔で奈緒が歓迎してくれた。
「どうやら体調は全快したみたいだな、松井!」
悪意ゼロの純粋な笑顔だったが、遥菜の心は痛まなかった。
奈緒が遥菜の嘘を信じ切っている事に罪悪感を抱く余裕はない。
やられた。ちくしょう!
遥菜は頑張って引き攣り気味の笑顔を作る。
「あ、はい。ご心配をおかけしましたが、大丈夫でス」
メンバーの中に混じって琴羽と亜莉紗も立っているが、遥菜が視線を向けるとバツが悪そうに目が合うのを避けた。裏切られたのか、否、売られてしまったのか。由比がその隣にいるが、ニヤニヤと嫌な笑顔だ。
向こうの方が一枚上手だった模様である。
(くそ。田辺のヤツめ~~)
「松井、着いてさっそくで悪いが、お前のXとインスタでチャンネルの宣伝してくれ」
「宣伝?」
遥菜は自分の公式アカウントを確認する。
ドラフト1位指名で1万3千まで増えていたフォロワーが、4万まで爆増していた。
(ま、まさか)
話の流れ的に心当たりは一つだ。
ヤホーニュースのスポーツ一覧を開く。
案の定、『日ハムの4番、中田奈緒が公式YouTubeチャンネルを開設!!』というニュースが一覧の中にあった。今朝のニュースだ。トップニュースでなくて本当に良かった。
記事本文を読むと、最初の動画公開は来週予定とある。
リンクからチャンネルホームに飛ぶ。
まだコンテンツはゼロ状態で、奈緒の顔アップのアイコンに、奈緒・陽・凛音・光の4人が並んでいる集合写真がバナー画像として設定されていた。
――すでに登録者数8万人を超えているではないか。
「どうだ、大したものだろう?」と、誇らしげな奈緒。
「コンサル会社が契約している弁護士に、肖像権とグッズ売り上げの利益配分率などの権利関係を各所属球団に対してクリアにしてもらうのに、少しだけ時間がかかった」
永遠に解決してくれなくても、遥菜的には歓迎だったのだが。
「チャンネル公式Xおよび公式インスタも、コンサル会社に運営してもらっている」
奈緒はそこで思い付いた様で、光と凛音に向き直る。
「そうそう、お前たち2人。来シーズンも順調な成績を残せたら芸能事務所とメディア関係を任せるマネジメント契約をしておいた方が色々と都合がいいぞ。格安の仲介料で私が紹介してやろう」
凛音は申し訳なさそうに言う。
「あ、実は複数の芸能マネジメント会社からすでにオファーを受けています」
光が補足した。
「とりあえず来シーズンのオフに選びますって、私も凛音も返事しています」
(フッ。上手くルーキーイヤーから1軍で活躍できれば、私も芸能事務所からマネジメント契約のオファーが殺到するんだろうナ)
天才・松井遥菜の名が日本中、いや全米中の野球ファンに轟く来年が楽しみで仕方がない。
チャンネル公式Xを確認する。
ひと目でガックリきた。
トップの固定ツィート(ポスト)の画像が、よりにもよって『ギニュー特戦隊』のポーズであった。しかも、もの凄い勢いで拡散している。
コメント数もどんどん増えていた。もう手遅れだ。
(わ、私のイメージが)
遥菜は泣きたくなった。
デジタルタトゥーとして、遥菜の『ギニュー特戦隊』のポーズは刻み込み済みだ。
他は座談会の切り抜き動画も公開されている。
それらも良い感じにバズっていた。
遥菜は自分のスマホのメッセージとメールの通知画面を開く。
ドラフト1位指名時には知り合い、関係者、アドレスを知っているファンから合計で900以上のお祝いが届いていたが、メールだけで既に1500通を超えている。チャンネルホームの概要欄を確認すると、普通に遥菜のメールアドレスが公開されていた。
いくらなんでも拡散し過ぎである。
(プライベート用のメールアドレスを新しく作らないとな)
「それから各自、初回の出演料はちゃんと振り込まれているよな?」
遥菜は未確認だ。
依子が言った。
「本当に20万円ももらっていいのか?」
「心配するな。諍いが起きない様に全員が同じ金額だぞ。むろん私の取り分も20万円丁度だ。基本的にチャンネル管理しているコンサル会社さんが利益と税金を管理しているから、その点は承知しておいてくれ」
由比が質問する。
「コンサル会社が赤字になったらどうするのよ?」
「元々私名義のGoogleアカウントではあるが、チャンネル運営権を私に譲渡してもらって、私が個人的に新しい撮影者・動画編集者を雇いニリューアルで継続だろうな。そうなったらセルフブランディングを主目的にして、採算は度外視にする予定だ。年間数百万円程度の赤なら私が資金補充して維持可能だと思う。それでダメなら諦めて放置するしかないが」
(ちゃんと考えているんだナ)
奈緒は皆を見回して言葉を続ける。
「まあ、チャンネル運営については心配するな。メンバーに被害は及ばない様にする。それよりも初回で撮れた映像を確認して、気になった点が1つだけあってだな」
依織が冷たい口調で言う。
「それは案件、案件、案件、案件とひたすらお金を前面に押し出していた事でしょうか」
「そこは問題視していないぞ」
「問題視して下さい」
「そうか。少しだけ前向きに検討しておくことにするが、私が言いたいのは、各自の名前の呼び合いの仕方だ。私達はメンバー、親友、いわば家族的な関係になった筈だ」
(お前と家族になった覚えはねーよ、中田)
1回食事というか撮影しただけなのに、随分と距離を詰めてくるなと思った。
「というわけで、これからは名字で名前を呼ぶのを禁止にする。ただし陽は陽の方が音感が良いので、陽のままで」
(それ、お前の都合じゃねーか?)
依子が言った。
「分かった。これからは奈緒と呼ばせてもらう」
「ああ、改めてよろしくな、依子」
奈緒と依子はガッチリと握手だ。
光が少し照れくさそうにほほ笑む。
「私も川原呼びよりも名前で呼んでもらう方が好きかな。親戚や友人、知り合いも光って名前は凄く似合っているねって言ってくれているし、自分でも気に入っている名前だから」
(川原のヤツ、VTuberの名前を『ぎー太』にされた事、根にもってやがるナ)
「そうそう、川原は視聴者の認識のためにも世間に浸透しているニックネームで呼ぶことにするからな。だいたい川原を「光」とか呼んだところで視聴者の大半は「誰だよソレ」状態になる。以前から名前で呼んでいる凛音はともかく、他のみんなは視聴者とファンのことを考えてくれ」
恋美が朗らかに言った。
「それもそうですよね。じゃ、これから川原さんはギータさんで!」
光は悲しみに満ちた笑顔で、恋美に応える。
「うん、ファンが第一だよね。これから私も諸積さんを恋美ちゃんって呼ぶから」
(いや、光って呼んでやれヨ。なんか川原が哀れに思えてきたナ)
由比が遥菜に話しかけてきた。
「じゃあ、今更かもしれないが、私もお前を松井ではなく遥菜と呼ぶ」
「それなら私も、田辺先輩をこれから由比と呼び捨てに――」
メキメキメキメキィ
「お前、先輩である私に喧嘩を売っているのか、は・る・な?」
アイアンクローを決められて、遥菜の頭蓋骨が歪む。
「痛い痛い痛い痛い! ほんの冗談です、由比センパイ!」
(洒落が通じない奴だな、田辺は!)
それから各自のSNSで相互宣伝などを行った。
で、前置きを終えて撮影に入る。
「では、用意してある着物に着替えてくれ」
小紋、紬、振袖と揃っている。
確認するまでもなく案件としてスポンサー提供されている代物だ。
遥菜は紬に着替えた。
「今から正月用の動画を撮るからな」
プールサイドには和室のセットが作られており、そこで座談会とゲームをやる。
基本的に地上波のTV番組であっても、年末年始の番組は生放送のスポーツ中継を除き、前撮りしてあるので、これ自体は特に変な事ではない。
『ロシアンルーレット雑煮』なるゲームで、ワサビ入りの餅を食わされた時は殺意が湧いたが、遥菜はどうにか我慢した。せめて由比を道連れにしたかった。なんで由比はワサビ入り餅を回避して無事なんだ。納得がいかない。
羽根突きもやった。
このYouTubeの件の発端となった由比に恨みをぶつけるべく、遥菜は対戦相手に由比を指名してボコボコにしてやろうとしたが、逆にフルボッコにされて顔面を墨だらけにされた。泣きたい気分だった。どうしてこんな酷い目に。理不尽すぎる。
琴羽が遥菜を労う。
「ちゃんと先輩に花を持たせていて、安心しました」
「ま、まぁな」
(田辺のヤツ、なんであんなに羽根突き強いんだよ!)
腹が立つ事に、他の面子がなんだかんだでYouTube撮影に慣れて、馴染んできている様子なのが、遥菜としては超気に入らない。
元旦用の動画を撮り終わり、次は水着に衣装替えしてのプール動画だ。
確認するまでもなく水着もスポンサー提供の代物で、案件である。
亜莉紗が萌の水着姿を目にして感激した。
「とてもお美しいです、萌様!」
「え、様?」
「し、し、失礼しました! どんな罰でもお受けいたします!」
「? 普通にプールを楽しみましょう?」
その光景に、遥菜は歯ぎしりした。
(亜莉紗が私を売ったのは、園川の水着が見たかったからカ)
まあ、いい。
とにかく今の最優先は由比をボコってやる事だ。ゲームでの勝敗に先輩後輩の忖度は関係ない。こうなったら何が何でも憂さを、いや恨みを晴らす。
最初のゲームは、水面に浮かべたビート板の上を渡って、どこまで忍者みたいに水面を歩いていけるのかを競う、割とYouTube的によくあるアレである。
依織が奈緒に言った。
「奈緒さん、これって絶対に最初の一歩で沈んでしまいますよね」
ビート板の浮力を考えれば、物理的に当然だ。
「その通りだ。だが、そういうオチの動画は腐る程にあるからな。よって今回は試行錯誤を重ねて趣向を凝らしてみたぞ」
奈緒は皆に説明する。
最初は口径の大きい筒で下から支柱として固定しようとしたが、それだと転倒時に怪我をする危険性が高い。よって、物干し竿程度の棒というか物干し竿そのもので下から固定し、ビート板との接続部にはジョイントを付けた。このジョイントが回転する事によって、転倒して水面に落ちても安全というわけだ。
そして、プールサイドへの転倒と激突を防ぐため、中央のコースに設置されていた。
「しっかりストレッチして、怪我だけは絶対にしないでくれよ」
2人ずつで対決していき、負けた方は罰ゲームだ。
遥菜はまたしても対戦相手に由比を指名した。
由比も承諾し、第1戦目での対決となる。
先攻は遥菜となった。
(先に最長記録を出して、田辺にプレッシャーを与えてやる!)
いざチャレンジという段になったのだが。
「本当に申し訳ございません!!」
従業員の1人が出てきて、いきなり土下座した。
「私の手配ミスで、温水装置の修理が間に合いませんでした! この責任は退職する事によって償いますので、どうか、どうか弊社の批判だけは!!」
その従業員は退職願を頭上に掲げる。
温泉プールの管理責任者が驚く。
「そ、そんな事情があったから、君は昨晩1人でセッティングをしたのか」
「昨日、業者が修理完了したというのも嘘です。書類も偽造しました」
「じゃあ、水温メータにも細工を?」
「はい、細工しています。だって事前に中止になってしまうと、こちら都合でのキャンセルに。ここ最近は利用者も減っているし、それだけは避けたかったんです。私1人が責任をとって退職するだけで、プールを使わずに撮影してもらえれば、起死回生の宣伝になるかと」
温水プールでプールを使わずに、いったい何しようっていうんだ。
遥菜だけではなく、この場の者ほとんどが心の中でツッコミを入れた。
奈緒が優しく言った。
「どうか立ち上がって下さい。それに貴女が退職する必要なんてありません。このまま撮影だって続行しますし、御社の宣伝だって任せて下さい」
「な、中田さん!」と、感激する従業員。
「心頭滅却すれば火もまた涼し、という言葉をご存じだと思います。少しばかり水温が低いくらい、何の問題もありませんから!」
「「「「「 え? 」」」」」
奈緒以外の誰もが自分の耳を疑った。
さらに次の瞬間は、自分の目を疑う事となる。
なんと奈緒はプールに飛び込み、見事なクロールを披露したではないか。
50メートルを素晴らしいフォームで泳ぎ終えた奈緒は、水から上がり笑顔になる。
「この通り、少し冷たい程度ですが問題なしです!」
温水プールの職員たちは困惑一色に染まっていた。
(な、中田のヤツはバケモノなのか!?)
真冬に冷水で泳いで平然としている様に、遥菜は戦慄を覚える。
水際で恋美がしゃがみ、水面に手を入れた。
「なんだ。意外と大して冷たく――な」
恋美の顔が凍り付き、ゆっくりと手を引き抜く。
そのリアクションで誰もが悟った。
やはりシャレにならないレベルで冷たいのだ、と。
奈緒が遥菜を促す。
「時間も押してきているし、まずは遥菜からチャレンジしていくぞ」
「え、ええと」
死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、これ死ぬってば。
「あの、中田さん。やっぱり無理なんですよ。私が退職願を出せばそれで」
泣きそうになる従業員。
泣きたいのは遥菜の方だ。
(退職願を人質は卑怯だろ、おい!)
遥菜はかなりの無理をして、その従業員に笑いかける。
「も、問題ありません。大丈夫ですから!」
言ってしまった。
口にしてしまった手前、もう後には引けない。
状況(退職願)が状況なので、他の者も止められなかった。誰だって自分の言葉で人の人生を壊す負い目なんて勘弁である。犠牲になるのは自分ではなく遥菜だし。
「頑張れ、遥菜!」と、奈緒はご機嫌だ。
心臓麻痺だけは避けなければ。
遥菜は胸と背中に水をかけたが、予想通りの冷たさだ。超冷たいが我慢して入念に心臓付近を冷水に慣らしておく。でないと、心臓麻痺であの世逝きになってしまう。事故ったら退職願どころではなくなるし。
遥菜はスタート地点に立つ。
クリアさえすれば水面に落ちずに済む。
しかし、到底できそうにない。
練習なし、ぶつけ本番で50メートルを渡り切るのは、遥菜の卓越した身体能力をもってしても無理だ。というか、ぶっちゃけ人間には不可能だろう。
遥菜は覚悟を決めた。
少しでも爪痕残して死んでやるゾ。
全速力でダッシュして、飛び、最初のステップをクリア。
二歩目もいけた。
かなりシャフトが撓む感触があるが、想像よりもしっかりと踏める。
推進力を前へ、前へ――
(割といける!)
人間、死ぬ気になればなんだってできる。
そんなボンバイエな名言が、遥菜の脳裏にリフレインした。
いくら水が冷たかろうが、渡り切ればノーダメージだ。
そうすれば――
(そうだ、私がクリアすれば、田辺のヤツにもチャレンジさせられるゾ)
欲が出たのが運の尽きであった。
それに素足で着地時のグリップが弱いのも大きかった。
どっぼぉ~~ん!
あえなく水中に落下する遥菜。
(うぉぉぉぉぉおお! つ、つめたいぃぃぃぃぃ)
誰か助けてくれ、と遥菜はもがく。
しかし誰も来てくれない。薄情な連中め。
あまりの冷たさに、まともに泳げないのだ。辛うじて心臓は動いてくれているが、手足の感覚が抜けて、思った様に動かせない。とにかく最寄りのプールサイドへ。
(中田、中田はこの冷水でも泳げたよな!?)
視界に奈緒が映るが、「ナイスリアクションだ」と喜んでいる始末だ。
救助を諦めて、遥菜は自力でプールサイドに辿り着く。
生きている心地がしない。
「しっかりして下さい遥菜ちゃん!」と、琴羽が急いで水から引き上げる。
亜莉紗がバスタオルで遥菜の身体を入念に拭く。
職員が用意してくれたヒーター3つの真ん中に、遥菜は体育座りだ。
喋ろうとしても歯の根が合わない。
「ガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチ」
翻訳:さむいさむいさむいさむい、どうしてわたしがこんなめに
「そんなに冷たかったのか?」と、奈緒。
「ガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチ」
翻訳:あたりまえだろ、わたしをとうしさせるきか、このあほが
「う~~ん、唇も真っ青だし、これ以上の続行は危険みたいだな」
例の従業員が泣き崩れる。
「やっぱり私のせいで台無しに! こうなったら退職願で責任をとって」
「いえ、良い画が撮れましたので、これはこれでハプニングとして使います。遥菜のリアクションを楽しむ目的のドッキリ企画ということにしますので」
奈緒がみんなに向き直って宣言する。
「よし! ここからはプールサイドで水鉄砲を使ったサバゲーをやるとしよう」
「ガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチ」
翻訳:だったら、さいしょからさばげーをやってくれよ、ふざけるな
「遥菜も休憩が終わったら参加してくれ」
「ガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチ」
翻訳:そんなよゆうがあるようにみえるのか、むりにきまってるだろ
凍える遥菜を放置し水鉄砲サバゲーを楽しむ面々を見て、遥菜は決心する。
絶対にこのグループから脱出してやる、と。
――おわり。
◆Chapter13:年末年始
12月30日――
つまり明日は大晦日である。
皇京大学硬式野球部専用学生寮。
怜は理紗と共に、息吹と白菊の2名を探していた。夕飯に誘うためだ。各自の個室にはいなかった。スマホも反応なし。今までの経験則から時間的に部屋の中に置きっ放しという事だ。つまりラフなスエットで個室の外にいる。たぶん一緒だろう。となると、大広間である共用部屋2室――談話室かゲーム室のどちらかの可能性が高い。
談話室には居なかった。
此処はなんと20畳の広さがあり、52インチのTVも設置されている。しかも自販機の飲み物は紙コップ1杯オール50円という安さ。
というか、怜・理沙・小陽といった特待生待遇の学生は、学内の自販機全てをフリーで使えるカードを支給されている。使用金額はチェックされているので、非常識な使い方をすれば没収されてしまうが。
残るはゲーム室だ。
流石にゲームセンターみたいな共用部屋ではなく、15畳の広さにビリヤード台と麻雀卓、そしてゲーミングPCおよびプレステ5、そしてゲームモニターが置かれている。
ゲーム室に入ると――
息吹と白菊は1年生の千恵(4軍)、2年生の美里(2軍)と一緒に、桃鉄――桃太郎電鉄をプレーしている。
キングボンビーを押し付けられた白菊が、半泣きになった。
現在2位であるが、ここから大逆転されそうだ。
「お前たち飯にしないか?」と、怜。
声掛けに、息吹が振り返る。
「あ、キャプテン」
白菊はホッとした顔で言う。
「では、ここでゲーム終了ということに。私は2位でフィニッシュです!」
「「「 そんなわけないでしょ 」」」
残る3人は声を揃えた。
セーブして、食事後にゲーム再開だ。
息吹と白菊は12月初旬の約束通り、年末年始を野球部寮で過ごそうとやってきていた。高校の2学期終業日を終えて、そのままこちらに来ている。来年1月5日まで滞在予定だ。
理沙は嬉しそうに言う。
「息吹ちゃんと白菊ちゃん、まだ入学前なのにすっかり寮に馴染んだわね」
引退済みの4年生とは流石に距離はあったが、3年生以下の学生とは完全に打ち解けていた。2人とも全く遠慮なしのノンストレスで過ごしている。
「1人部屋の自室もありますし、もう結構な日数を過ごしていますから」
「はい。先輩の皆さま方にはとても良くして頂いて、楽しく過ごせています」
なお、練習は29日で打ち上げになっている。
練習再開は来年1月4日からだ。
その間、学生が許可なしで使える練習設備はトレーニング室のみ。
食堂で夕飯を摂った。
寮則としての基本は同学年同テーブルとなっている。2軍以下は特にだ。しかし学年下側が構わなければ、先輩後輩が同じテーブルに着く事は黙認となっている。要は「嫌な先輩」と無理矢理な同テーブルを避ける為のストッパーとしての規則である。
よって、同じ出身高校の先輩後輩、そして学年を超えて気の合うグループでの席も、割とそれなりにあった。この野球部は、改革的な取り組みが奏功した結果、昔じみた体育会系的な上下関係はほぼ消滅している。むろん何軍に属しているかというヒエラルキーは、色々な面(主に待遇や寮生活の役割)で大きく影響しているが。
怜、理沙、息吹、白菊の他に桃鉄をやっていた千恵と美里も同テーブルだ。
食後の談笑の最中、館内放送が流れた。
『あ~~、寮にいる全学生に告ぐ。今から10分以内にトレーニング室に集合してくれ。繰り返す。寮にいる全学生に告ぐ――』
怜は怪訝な顔になる。
「全学生か。何かあったのか?」
「集まるのトレーニング室なんですね、キャプテン」と、息吹。
「広さ的にそこじゃないと狭いからだろ」
食堂にいる学生が揃って大移動した。
トレーニング室はぎっしりと人で埋まっている。
だが、怜の想像よりは人が少ない。計100人前後か。
けれども、もうこれ以上は増えそうもない気配だ。
「風間先輩、人数少なくありませんか?」
風間(3年生・1軍)が答えた。
主な守備位置はライトで、準レギュラーといったチーム内の立ち位置だ。
「実は今年に限り、4年生たちが全員帰省してしまってな。だから例年より人数的には少なくなっている」
言われてみれば、確かに4年生が1人もいなかった。
「どうしてです? なにかトラブルでも?」
「新キャプテンのお前と、そして新チームそのものに遠慮したんだろ。引退した4年が残っていたら、まだ2年になる前のお前がキャプテンって、お前が遠慮しそうだからな。安心しろ。私達3年は来年の年末年始まで寮生活もできる限り付き合うつもりだ」
「そうですか」
4年生に気を遣わせて申し訳なかったな、と怜は思った。
理沙が訊く。
「それで、全員を集めた要件は何でしょう?」
「うん、何名かから話を聞いているんだが、どうも昨日辺りから不審人物が寮に潜伏しているかもしれない、という事があってな」
そこで数名の部員が挙手して、次々と語り始めた。
なんでも「幽霊めいた人影」を夜中に目撃した、と。
追いかけた者もいたが、見失った、否、消えたらしい。
「幽霊って、おい」
怜の声と顔が引き攣る。
聞いて面白い話ではない。
風間が言った。
「とにかく各自、自室に戻って貴重品の確認をしてから、また此処に集合してくれ」
部屋のドアと机の引き出しには鍵が付いている。
小まめな施錠が推奨されているのだが、ぶっちゃけ、ほぼ誰も鍵を使っていない。ここ何年も部員同士での貴重品トラブルなど起きていないから、全員が安心し切っていた。施錠されているのは、機械室や電気室などの設備系、そして未使用の部屋のドアくらいだ。
――10分後。
再びトレーニング室に全員が集う。
貴重品の盗難はゼロであった。
怜が提案する。
「防災センターに行って事情を説明して、寮内の監視カメラの録画を確認してもらうというのはどうだろうか。潜入者がいれば、どれかのカメラに映っている筈」
「盗難品があれば警察に被害届を出してから監視カメラの再生手続をとれるが、被害や事故が現在進行形で起っていないと、まず無理だ」
無理という台詞に、理沙は不満の声をあげる。
「どうしてです?」
「プライバシーの問題でけっこう面倒なんだよ。事件らしい事件は起こっていないし、それに寮内の監視カメラって、防犯よりもパワハラ・イジメ抑止で設置されている」
息吹が言う。
「でも、犯人の目的が盗撮とかだったら?」
「この野球部寮って、大学のパンフレット、大学のホームページ、なによりも野球部公式YouTubeチャンネルで様々な寮生活の映像も色々と公開しているから、盗撮目的もあまり考えられない。私達には寮で撮られて困ることも別にないだろ。念のため、集合をかける前に共用トイレと浴場で隠しカメラや盗聴器を探したが、そんなの見つからなかったしな」
各自の個室にトイレがあるので、共用トイレの使用頻度は少ない。
それに簡易シャワー設備も個室にはあるのだ。大浴場は大浴場で人気はあるが、仮に盗撮したところで見つからずに撮れる画角は限られているし、露天風呂とは違って間取り的に見つかるリスクが高いだろう。
白菊が言った。
「盗難目的にせよ、盗撮目的にせよ、普通に考えたらわざわざ野球部寮を選ばずに、一般学生寮を狙いますよね。こちらを選ぶメリット、ないですから」
部員の中の誰かが、ヒステリックに叫ぶ。
「ゆ、幽霊よ! やっぱり幽霊だわ!」
「幽霊が出たんだ」という幽霊派。
「変質者だって」という非幽霊派。
「変質者の幽霊だ」という極少数のハイブリッド派。
この3派閥が意見を交わし合うが、結論が出ないまま解散となる。
なにしろ被害ゼロなので、これ以上はどうしようもなかった。
――‥‥……
「……ッ!」
――夜中になり、怜は睡眠から覚めてしまった。
幽霊が気になり、よく眠れなかったのだ。
やっと少し眠れたと思ったら、すぐに起きてしまうとは。
時刻を確認すると、まだ深夜1時である。
(こういう時、1人部屋だとキツイな)
住み慣れた部屋の筈なのに、不気味だ。
というか、正直いって怖い。幽霊が。
「たまには昔を思い出して、高校での合宿みたいに理沙と寝るか」
怜は新越谷時代が懐かしくなった、と自分に言い聞かせた。
そうだ、理沙も共感してくれるに違いない。
隣の部屋――理沙の個室のドアを小さくノック。
「どうしたのよ怜、こんな夜中に」
「高校時代の合宿みたく、たまには一緒に」
「真夜中に起こして、ふざけているの?」
ドアを閉められた。
ガチ切れしていた。
(どうしよう。いや、こんな時こそ遠慮しないでキャプテンに相談だ!)
と閃くが、4年生は全員帰省している。
そもそも既に代替わり済みで、怜自身がキャプテンだった。
「高校といい大学といい、どうして私がキャプテンなんだ」
しかも両方とも2年生次からである。
キャプテンでない時間が1シーズンあっただけで、またキャプテンに逆戻りだ。
(風間先輩に頼る、のは、やはり迷惑だよな)
ヒタ、ヒた、と冷たい足音。
怜が音の方を見ると、白い衣装を着た黒髪の少女っぽい人影が――
(え、本当に幽霊?)
窃盗犯とか盗撮犯みたいなイメージではない。
幽霊を目撃してしまい、怜は恐怖で固まる。
廊下の角へ幽霊は消えた。
と思ったら、戻ってきて死角から「ぬぅ」と顔を出す。
(ゆ、ゆ、ゆ、幽霊だぁぁあぁあああ)
怜は自室に逃げ込む。
無駄かもしれないがドアの鍵をかけるのを忘れない。
そして布団の中で丸くなった。
(頼む、このまま朝になってくれ!)
ガチャガチャとドアノブが回される音。
見間違いではなかった。侵入しようとしている。
(け、警察を呼ぶか?)
幽霊だと正直に言って来てくれるだろうか。無理だろう。不審人物だと嘘をつくのはありだろうか。いや、それだと大騒ぎになって他人に色々と迷惑が掛かってしまう。幽霊が怖くて嘘を言ってしまった、と打ち明けた後の警察の反応を想像すると――
小さい音と共に、ドアが開いてしまう。
(幽霊によるオカルトパワーの前には、ドアの鍵など通用しないか)
絶体絶命だ。いや、諦めるのは早い。
怜は呪文を唱え始めた。
「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、エロイムエッサイムエロイムエッサイム」
ゆっさゆっさと布団を揺すられる。
怜は恐怖で固まった。
もうダメかもしれない。こんな形で人生が終わってしまうとは。
「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、エロイムエッサイムエロイムエッサイム」
「あの~、岡田さんですよね?」
幽霊に名前を知られている!
という事は、ピンポイントで狙われているのか。
「いえ、私は決して岡田 怜などという者ではありません。人違いです」
名前が怜で、霊に消される、か。
皮肉な人生の終着駅だ。
「人違いでもいいですから、ちょっと助けれくれません?」
「それは貴女様が成仏を望んでいると解釈してもよろしいのでしょうか?」
(よし、生存ルートが見えてきたかも!)
「私、東條蘭々ですけど、覚えています?」
「え?」
布団を跳ね除けて確認すると、枕元にいたのは幽霊ではなく蘭々だった。
――10分後。
息吹の部屋で、京子・蘭々・美咲の不法侵入者3人組が揃っている。
蘭々だけ共用トイレに行ったら、迷ってしまったとの事だ。照明を点けるわけにもいかず、困っていたら運よく怜と遭遇したという経緯である。
白菊が言った。
「あの、どうして私が叩き起こされて、この場にいる必要があるのでしょうか?」
息吹は眠そうに答える。
「特に意味はないわ。でも、白菊も巻き込まないとちょっと癪だったから」
「単なる巻き添えですか」
怜が3名に詳しい事情を訊く。
「どうして不法侵入なんてしたんだ? 普通に犯罪行為だって分かっているよな?」
京子は項垂れつつ話す。
「息吹お姉さまが此処にいらっしゃると知って、どうしてもその可愛らしいご尊顔を拝見したくなってしまって、それで我慢できずに」
美咲も付け加える。
「咲桜野球部の練習が年内終了になるまで、こちらに来られなかったんです」
白菊が確認する。
「ええと、貴女達は29日に忍び込んで、未使用の部屋のドアの鍵をピッキングで開けて潜伏して、食べ物も食堂から拝借していた、と」
怜は疑問をぶつける。
「昨日から潜伏していたのは分かったが、目的が息吹に会う為だろ。それなら隠れていたんじゃ意味がないんじゃないか?」
蘭々が口を滑らせた。
「ちゃんと昨夜、息吹お姉さまお部屋に侵入して超カワイイ寝顔をスマホで撮影しましたから。それから下着上下1人1セットずづ2万円で購入済みです」
息吹はタンスを確認した。
アンダー用の引き出しを開けると。
下着代です、と記入された封筒が3つ。中にはそれぞれ2万円が入っている。
「お金は要らないし、私の下着、返してくれない?」
3人は声を揃えた。
「「「 え、いま身に着けているんですが 」」」
「あ、やっぱり2万円で売却するわ」
怜は再度、疑問をぶつける。
「それにしたって、どうして不法侵入なんだ?」
「部外者は入れないじゃないですか」と、京子。
「なに言っているんだ? 普通に1泊7500円でゲストルームに泊まれるぞ。野球部のHPに案内があるだろ。電話やネットから半月前から予約可能で最大3泊可能だと。この寮には外部者宿泊用の部屋は3つある」
3人は揃って目を丸くした。
そのリアクションで充分だ。
「あのな、勝手な思い込みで突っ走るなよ」
蘭々は愛想笑いを作る。
「それは次から気を付けるとして、私たち岡田キャプテンと知り合いで本当にラッキーでした。今回はこのまま見逃して、明日からゲストルームを貸してください」
「ホントにキャプテンと知り合いで助かったぁ~~」と、京子。
「キャプテンと知り合いでなければアウトだったね」と、美咲。
3人は笑顔で頷き合う。
イザとなれば許してもらえる、と高を括っていたのか。
怜は残酷な現実を教える事にした。
「いや、私に侵入者のお前たちの処遇の判断をできる裁量権なんて、ないぞ」
「またまたぁ、キャプテンといえば野球部員の頂点にして、選手内の最高権力者。当然、この野球部寮においてキャプテンの権限と裁量権は――」
「――それ、普通に寮長の領分だ」
「寮長って?」と、美咲。
「キャプテンは寮長でもある、っていうパターンですよね」と、京子。
「キャプテンが寮の頂点ではないという、意外な展開」と、蘭々。
3人とも大量の冷や汗をかき始める。
目が泳ぎまくっていた。
息吹は盛大なため息をつく。
「なんて非常識な。寮の管理責任者と防火管理者は資格を持った大学職員が務めて、その職員と連絡をとりあって実際に寮の自主管理をしているのが寮長よ。例外なく最高学年の学生が務めるわ。副寮長はその1コ下の学生が、寮長の補佐をして仕事を覚え、来年度の寮長になるの」
白菊が付け加える。
「何軍とか関係なく、割と人気なんですよ寮長。就職に有利になるからって。先代の寮長は4軍だったみたいですし。実務をこなしているだけあって、権限も強いです。副寮長は寮長が指名して、その学生が受けた時点で成立ですね」
蘭々は食い下がる。
「で、で、で、でも! キャプテンと寮長って立場的には互角くらいだと思います」
「お前が思っても現実は変わらないぞ。寮生内のヒエラルキーは寮則とは無関係の、単なる慣習・伝統に過ぎない。つまり寮内において私は単なる一学生だ」
「し、し、し、しかし! キャプテンだって野球部で色々な実務をこなしている筈で」
白菊は真顔で伝える。
「高校時代、怜先輩のキャプテンとしての仕事は、キャプテンとして慕われて、キャプテンと呼ばれて、相手校のキャプテンに挨拶して、先攻後攻のジャンケンをして、それから整列の時に先頭にいるとか、円陣や練習の声掛けとか、背番号を決めて渡すとか、それくらいでした。下級生の指導も芳乃さんが練習メニュー決めて、光先輩が担当していました。私はキャプテンが芳乃さんより実質的立場が上だったシーンを見た記憶がありません」
現実を認めたくないのか、京子は往生際悪く――
「知っています。高校時代、実質的にチームを仕切っていたのは息吹お姉さまの双子の妹君だと。でも、大学時代の今、芳乃さんはいません。すなわち今度こそキャプテンとして」
息吹が遮る。
「その役割は小陽先輩の仕事だから」
「つまり大学時代の今、怜先輩のキャプテンとしての仕事は、キャプテンとして慕われて、キャプテンと呼ばれて、相手校のキャプテンに挨拶して――」
「ストップ白菊。ストップな。うん、分かっているから。本当に色々と自覚しているから。その台詞を最後まで言うのは事実陳列罪だと思うぞ」
「あ! 高校時代と大学時代とで、怜先輩のキャプテンとしての違いがありました!」
怜が輝くような笑顔になる。
「本当か、白菊! 教えてくれ。お前から見て、私はどんな風に高校時代とキャプテンとして違うんだ?」
「背番号8から背番号10になりました!」
「白菊。いや、お前に悪気がないのは分かっているんだけどな」
高校野球は1桁背番号=守備位置、大学野球はキャプテン=背番号10である。
怜は割と本気で落ち込んだ。
それから怜たちは侵入者3名の身柄を、寮長である風間の元へ連行した。
3人はたっぷりと1時間、風間から説教を食らう。
正座したまま、何度も土下座だ。
警察沙汰だと立派な不祥事なので、3人ともガチ泣きで反省していた。
知り合いであり悪気はなかったので、3人は今回の件を表沙汰にする事は許してもらう。3軍4軍の学生に混じって寮の雑務や年末年始の手伝いを引き受ける罰は受けるのだが。
「未来の後輩だから、これくらいで勘弁してやるか」
「ご迷惑をお掛けしました、風間先輩」
「いいさ、キャプテン。京子は咲桜でレギュラーだろ? 貴重な戦力を確保できたしな」
夜が明けて、年末年始。
寮長と副寮長で協議した結果、この件は他の学生には黙っている事にした。
大晦日からゲストルームに泊まりに来た(という建前の)3名に対し、色々と察した学生もそれなりにいた様子であるが、余計な口出しはしないでくれた。
理沙は京子たちの宿泊を喜んだ。
「大歓迎するわよ。でも、最近は幽霊が出るかもって噂があるから、夜中は部屋から出ない方がいいと思うわ」
小陽は何かを言いかけたが、怜に視線を向ける。
黙っていてくれ、と怜は苦笑を返した。
◆Chapter14:希の開幕
3月4日、卒業間近。
この週の土曜日が高校卒業式である。
そして、この3月4日――NPBオープン戦において、希の所属球団である福岡ハードバンクHが今年度の初戦を迎える。対戦相手は、同一リーグの楽全プラチナイーグルス。
無事に珠大への進学が決定した詠深たちは、菫の家で揃っての試合観戦だ。
場所は菫の自室ではなくリビングである。
ペナントレース開幕が3月29日。
レギュラー確約でそこへピークをもっていく者。その開幕へ1軍の生き残りをかける者。開幕レギュラー当落選上で上層部へのアピールが必要な者。この時点で1軍にいる選手たちは大きく分けて、この3通りに別れている。
今年度のドラフトで入団したルーキーで、まだ1軍に残れているのは僅か2名、ホークスの中村 希とライオンズの松井遥菜だけであった。他の新人たちは全員が、理由は様々であっても開幕2軍スタートが確定している。
即戦力を期待されていた大卒上位組、ノンプロ組ですら1軍の壁は高く厚かった。
育成ドラフト組の支配下昇格もゼロだ。
昨年度のドラ1組では、マリンスターズの園川 萌が開幕1軍を確定的にしている。シーズン中に先発ローテ入りのチャンスを掴めるのか否かは、今後次第だろう。
TV画面を見つめながら、詠深が言った。
「あの諸積さんでも2軍スタートだって思えば、希ちゃんはよくここまで1軍に残っているよねぇ。やっぱり希ちゃんは凄いよ」
菫が意見する。
「とはいっても、試合に出られるファームで実戦経験を積む方が普通に大切でしょ、高卒組にとっての一年目は。諸積さんもファームで結果を出せば、上でチャンスは貰えるわよ」
逆に言えば新人が開幕1軍スタートであっても1軍の試合に出場できなければ、2軍に戻ってファームの試合で実戦経験を積むルートだ。ベンチでお地蔵化しても成長は期待できないからだ。
「とりあえず紅白戦では打率は上位だったよね、希ちゃん」と、珠姫。
「でも、希にとってはここからが正念場だ」と、稜。
オープン戦で結果を出せなければ、すぐに2軍行きの立場である。
スタメンが発表された。
希の名前はなかった。
光は3番センターの定位置でスタメン出場である。
そしてオープン戦開幕投手は、凛音だ。
昨年までのエース・千賀がポスティングでメジャーに移籍した為、凛音の開幕投手は内定と公式に発表されている。怪我や故障がない限り高卒2シーズン目での開幕投手だ。
凛音は今日、3イニングを投げる予定である。
先発ローテ確定組、レギュラー確約の主力組は、完全にペナントレース開幕に向けての調整目的でのゲームとなる。現時点で調子はピークではない。照準はペナント開幕だ。
1回表、ワンナウトでランナー一塁。
背番号9――光の登場曲『アイドル』が流れた。
オープン戦第1打席はサードへのファールフライに倒れる。打ち損ねだ。6球目でのミスショットであるが、光は納得した表情をしていた。
====================================
130.名無し@NPBハドバンすたじあむ
お~~、良い感じやん、ギータ
131.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ギータ、バット振れてる
132.名無し@NPBハドバンすたじあむ
バット、確か去年より長くしたんだろ?
133.名無し@NPBハドバンすたじあむ
>>132
せやで。重さもアップや。でもスイングは鋭いしタイミングもいい
まだ一打席の印象だが、普通に去年より良く見える
134.名無し@NPBハドバンすたじあむ
豪快なマン振りが持ち味だからな、ギータは
135.名無し@NPBハドバンすたじあむ
打ちそうな雰囲気あった
====================================
珠姫が真検な眼差しをTV画面に向ける。
「シーズンオフでフィジカルアップした体を実戦に馴染ませる、暖機運転の段階だろうけれど、キャッチャー目線で凄く怖い空気だった」
菫も同意する。
「主力はこの時期、生きたボールに目を慣らすのが目的で、内容だけで結果は二の次だろうけれど、いい感じでスイングしていたわね」
稜が言う。
「開幕に向けてチェック項目を1つ1つクリアしていくって感じしているな」
凛音は無難に1回2回と0点に抑える。
2回ワンナウトから二塁打を許したが、7割以下の力でボールのスピンとフォーシームの走り具合、そしてコマンドの精度を確認している様子だ。この時期にしては球速は充分すぎる程に出ている。凛音にしてはやや物足りない数字だが大台を連発だ。
彼女も2シーズン目という事もあり、光と同様にルーキーイヤーよりも遥かに落ち着いていた。顔つきもエースの自覚がある感じだ。
稜が呆れる。
「やっぱ速いな、松岡は。全力で投げたらマジでNPB最速が出るんじゃね?」
詠深も同意した。
「うん、出ると思う。少なくともNPB最速に近いスピードをコンスタントに出せるよ」
高校2年の秋から投手に転向。すなわち投手キャリア4年未満での、この圧倒的なパフォーマンスは完全に天性の物だ。肩と肘が使い減りしていないのも大きい。
珠姫が言った。
「負けてない。ヨミちゃんの球速も上がっているよ。球速そのものは劣っていても、スピン量とキレ、なによりも球の伸びは松岡さんにだって劣っていない」
「ムキになるなよ、珠姫」と、稜は苦笑した。
そして、3回の表にソレは起こる。
甘く入った初球チェンジアップを引き付けて、光は豪快にフルスイング。確信歩きする中、高々と上がった打球はバックスクリーンに飛び込んだ。
====================================
278.名無し@NPBハドバンすたじあむ
うぉぉぉ!ギータwwwwwwwwwwwwwww
279.名無し@NPBハドバンすたじあむ
いったぁぁあぁああああああああああああああああ!!
280.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ファァ~~~~~~~~~~~~~~!!!!
281.名無し@NPBハドバンすたじあむ
きたぁああああああああああああああああああああぁ
282.名無し@NPBハドバンすたじあむ
キターーーーーーーーーーーーーーーー!!
283.名無し@NPBハドバンすたじあむ
きたぁ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!
284.名無し@NPBハドバンすたじあむ
いったぁぁーーーーーーーーーーーーーーーーー
285.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ギータ(*^_^*)キタァァァーーーーーーーーーーーーーー
286.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ファーーーーーーーーーーーーー!?
もうオープン戦1号とかwwwwwwwwwwwwwwww
287.名無し@NPBハドバンすたじあむ
そのホームランはシーズンにとっておけwwwwwwwwwww
288.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ギータwwwwwwwすげえwwwwwwwwwww
289.名無し@NPBハドバンすたじあむ
相変わらずの絶対マン振りスタイル
290.名無し@NPBハドバンすたじあむ
>>135
預言者がいた
よくあんだけフルスイングできるわ、川原
291.名無し@NPBハドバンすたじあむ
打ったギータより、マーさんの棒球の方が気になった(*'ω'*)
292.名無し@NPBハドバンすたじあむ
光ちゃん最高!!
293.名無し@NPBハドバンすたじあむ
>>292
誤爆すんな( ゚Д゚)クソガ
カノジョ自慢かよ、タヒにやがれ
294.名無し@NPBハドバンすたじあむ
長期離脱なければ、今年も20本は打ちそうだな
295.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ワイ将、40本を期待したいでござる
296.名無し@NPBハドバンすたじあむ
>>295 >>296
40は無理だと思うが、無難に30前後は打つと予想
297.名無し@NPBハドバンすたじあむ
やっぱギータのバッティングは華があるわ
298.名無し@NPBハドバンすたじあむ
>>292 >>293
ギータの下の本名だよ、忘れんなwwwwwwww
====================================
3回裏の守備で光は早くもベンチに下がった。
凛音は予定通り3イニングス目も行くようだ。
「光先輩、2打席で引っ込んじゃうんだ」と、詠深。
「ホームラン打ったし今日はこれで十分なんだろ」と、稜。
「調整に徹している感じね、光先輩」と、菫。
「あ、希ちゃんだよ!」
珠姫が3人に注目を促す。
光の他2名交替だ。シフト変更で、希がレフトの守備に入った。
初戦から途中出場でチャンスをもらう。それだけ期待されているのだ。
====================================
311.名無し@NPBハドバンすたじあむ
お、ドラ1の中村が出るぞ
312.名無し@NPBハドバンすたじあむ
やっぱり一塁じゃなくレフトか
313.名無し@NPBハドバンすたじあむ
こいつ高校の時、確かファースト専だっけ?
314.名無し@NPBハドバンすたじあむ
元々外野もやれたはず
315.名無し@NPBハドバンすたじあむ
プロで新人から一塁専はなwwwwwwww
316.名無し@NPBハドバンすたじあむ
紅白戦での外野の守備指標はそこそこだった
317.名無し@NPBハドバンすたじあむ
守備指標がそこそこレベルなら、やっぱ打たないと
318.名無し@NPBハドバンすたじあむ
打撃はマジでいいぞ、中村
====================================
3回の裏、凛音は無失点に抑えて予定消化だ。
初の開幕投手に向けて、順調な調整ぶりをアピールした。
なお、希に守備機会はなかった。
詠深、菫、稜は気軽にTV観戦している。
新越谷コンビの応援も含めて楽しんでいた。
けれども珠姫は真剣というよりも、どこか思いつめた感じで見ていた。
そして5回の表――
ツーアウト、走者一二塁のチャンスで希の初打席が回ってくる。
『2番、レフト中村、背番号7』
3球目、バックドアのカットボールを希はジャストミート。
左中間への綺麗なシングルがタイムリーになる。オープン戦の初ヒットおよび初打点をマークし、ランナーはなおも一二塁。チャンスは続く。
希のヒットに詠深、菫、稜が歓声を上げた。
====================================
742.名無し@NPBハドバンすたじあむ
やるやん、流石はドラ1
743.名無し@NPBハドバンすたじあむ
守備と走塁はともかくバッティングは本物だ
開幕レギュラー狙うとか、大口野郎って思っていたんだけどな
744.名無し@NPBハドバンすたじあむ
すげえなコイツ
打撃技術、普通に1軍でも通用している
745.名無し@NPBハドバンすたじあむ
今のって、かなり難しい球じゃなかった?
746.名無し@NPBハドバンすたじあむ
ワイ氏、中村の開幕2番レフトに1000ペリカ
747.名無し@NPBハドバンすたじあむ
レギュラー争いしている連中では、明らかに中村が一歩リード
748.名無し@NPBハドバンすたじあむ
開幕から夏場くらいまでは普通に3割以上打つんじゃね?
749.名無し@NPBハドバンすたじあむ
判断するの早いと思う
750.名無し@NPBハドバンすたじあむ
希はバッティングに関してはケチの付けどころないぞ
751.名無し@NPBハドバンすたじあむ
即戦力っていうスカウトの評価通りだな、巧いわ
752.名無し@NPBハドバンすたじあむ
順当、高校でコイツだけ別次元の打撃技術だったし
753.名無し@NPBハドバンすたじあむ
まだ春だってのに、プロ1軍の球速に対応しているぜ、中村
====================================
光と凛音が下がり、希の打席も当分は回って来ない。
TV観戦は一息ついたといった感じだ。
稜と菫はアイコンタクトする。
それで意思疎通はできた。
菫が詠深を誘う。
「ヨミ、ちょっとコンビニまで付き合ってくれないかしら。稜と珠姫は留守番をお願い。買ってきて欲しい物があるなら言って。1人500円までなら驕るわ」
「ヨーグルト、無糖で」と、稜。
「私はいいかな」と、珠姫。
詠深と菫が姿を消し、タイミングを見計らって稜は珠姫に話しかけた。
「3校合同練習試合での事、まだ気にしてるのかよ」
「私はどうすれば良かったのかな」
「身体造って打撃をレベルアップさせてプロ目指すか、吉川さんの誘いに乗ってノンプロに進むか、大学卒業したらガチの野球は辞めるかの三択だろ」
「どれでもいいんだよ、ただヨミちゃんと野球ができるのだったら」
「じゃあヨミに言えよ。大学卒業したらノンプロで一緒のチームに入って、引退するまでバッテリーを組もうって。ヨミなら快くオーケーしてくれると思うぜ」
「ヨミちゃんはプロでスターになる投手。だから、その選択肢は採れない」
「だったら逃げるなよ、その決意がつかないから、そんな湿気た顔してんだろ。でも、珠姫の中では答えは出ているから、光先輩や希をそういった目で見ていた。私達は他人事って感じで気楽に見ていたけどな」
「――タマちゃん」
リビングのドアが開く。
詠深がそこにいた。
「おい、菫」
「ごめん、稜。ヨミに意図がバレて連れ出せなかった」
「だからって盗み聞きかよ」
「ありがとう、菫ちゃん稜ちゃん。タマちゃん、話があるからちょっと川沿いの遊歩道まで行かない? そこで私の気持ちを話すよ」
その場所の意味を、珠姫は即座に理解した。
高校1年の春だ。
珠姫が全国を目指す詠深に対して「どこまで本気なの?」と確認した場所。
その時、詠深は「けっこう本気だよ、私は」と応えた。
目的の場所に着き、珠姫の方から口を開く。
「あの時とは、随分とお互いの立ち位置が変わっちゃったね、ヨミちゃん」
しかし詠深は心底から不思議そうに――
「私とタマちゃんはあの頃から何も、少しも変わっていないよ。私は同じだから。好きな人と一生懸命に少しでも長くやりたい、ってね」
「現実的には大学で、残り4年で終わり、だよ」
「なんで? 2人揃ってNPBで同じチームに進めればベストだけど、それが叶わないんだったら、2人でアメリカに渡ろうよ」
想定外だった選択肢に珠姫の目が大きく見開く。
「アメリカって、まさかマイナーリーグに挑戦?」
「うん、一緒に同じチームのトライアウト受けよう。シングルAからスタートで。アメリカの独立リーグでもいいかな。メキシコでも台湾でも、可能性があるところに殴り込み掛けよう。2人で世界相手に挑もう」
「どこまで本気、ってヨミちゃんだから、本気中の本気か」
「2人してメジャーリーグに昇格すれば、タマちゃんが見たがっているプロでスターになった私を一番近く、ホームベースから見れるからさ」
「もし、失敗したら?」
「その時はやるだけやったんだから、悔いなんてないかな。私の実力が足りなかった結果。希ちゃんや光先輩だって許してくれると思う。他のみんなもね。吉川さんには悪いけれど、NPBはタマちゃんと一緒限定っていう後付け条件を加えさせてもらうよ」
「バカだね、ヨミちゃんは」
「こうやってタマちゃんと話して、正直いって大学野球を終えたら2人でアメリカに行く気満々になっちゃった。詩織ちゃんには悪いけど、ドラフト候補に挙がっても「タマちゃんと同じチームじゃなかったらNPB拒否」って言っちゃいそう。酷いね、私」
「もう言うつもりでしょ、その顔」
「うん、今日から英会話の勉強をしようって思った。2人なら絶対に最高に楽しいよ、場所が日本じゃなくってもさ」
「私も和美さんには悪いけど、ヨミちゃん以外の正捕手は嫌だな」
「27歳。渡米して5シーズン2人で頑張ってメジャー昇格が無理だったら、潔く本気の野球は引退して菫ちゃん稜ちゃんと草野球チームを作ろっか」
「嫌だよ、あと9年でヨミちゃんとの本気の野球が終わりなんて。だから2人でメジャー昇格しよう。大学野球日本一を目指しつつ、アメリカで通用する様に鍛え上げよう」
2人は菫の家に戻った。
ずっと手を繋いだままで。
ちなみに、その試合で希は3安打をマーク。
珠姫も他の3人と一緒に大はしゃぎだ。
未来の話になるが――
希はオープン戦で首位打者となり目標の開幕レギュラーを手に入れ、一度も2番打者の定位置を奪われることなく、リーグ2位となる打率3割4分8厘(チーム1位)、OPS.913(チーム1位)、ホームラン12本を記録する。新人王は交流戦開けから4番に定着した諸積恋美に奪われてしまったが。松井遥菜も8月からのレギュラー奪取に成功した。
そして光は打率2割9分5厘、OPS.901、ホームラン31本をマーク。
新越谷コンビの活躍は、詠深と珠姫にとって励みとなった。
◆Last-Chapter:卒業式――たまよみ(珠✕詠)
いよいよ卒業式を迎えた。
詠深たちは自分たちのクラスで、それぞれの級友と最後の時間を楽しむ。
SNSでの繋がりは残っていても、同じ進路に進まなければ疎遠になっていくだろう。今日の様に多くの者が揃うのは同窓会だけになる筈だ。
担任からの挨拶。
そして体育館へ移動し、卒業式が始まった。
諸々の挨拶を終え、卒業生代表がスピーチをする。
詠深は(制服姿も終わりか)と、そんな事をぼんやり考えていた。卒業証書授与。自分のクラス以外の友人・知人が受け取る姿に、寂しさを覚える。
「蛍の光」を歌い終え、体育館から退場し、再び各々の教室へ戻った。
担任教師が別れと祝いの言葉を贈り、クラス解散だ。
真っ先に向かう場所は決まっている。野球部の部室前だ。去年は在校生として怜たちを待っていた。今年は立場が逆になっただけだ。
後輩たちに会う前に、新たな野球部OGとなった卒業生8名が集まる。
一番最後は希だった。
「遅そうなって、ごめん」
オープン戦での活躍もあり、握手と記念撮影の総攻撃にあっていたのだ。
そこへ杏夏がやってきて、8名だけの記念撮影をしてくれた。
データはすぐにスマホに転送だ。
それから、37名の野球部後輩(とマネージャー5名)たちに最後の挨拶および記念撮影。野球部に入部希望である30名ほどの新1年生(予定)も、詠深たちを見に来ていた。彼女たちはちゃっかりと希と記念撮影もした。
予定していた行事を全て終え、いよいよ高校生活、最後の時だ。
校門までは一緒である。
惜しむ間もなくあっさりと校門に着く。野球部で時間を食っていたので、他の卒業生はすでにいなくなっている。3年間を過ごした此処から出ると、今までみたいには、もう戻らないし通わない。ここは母校という名の過去になる。
足を止めた8名の中で、最初に離れたのは希と芳乃だ。
芳乃が言った。
「車で希ちゃんを駅まで送って、私はそのまま東京のマンションに行くよ。希ちゃんと光先輩とはこれからも密に連絡を取り合うし、会える時は会う予定だから、何かあったら遠慮なく連絡してね」
「じゃ、みんなも頑張って」と、希。
2人は近くのコインパーキングに向けて歩いて行った。
川口姉妹同士の会話は最後までゼロだった。
稜が苦笑する。
「あっさりとしたもんだな、あの2人」
「湿っぽいよりいいでしょう」と、菫。
白菊が息吹を促す。
「私達も行きましょう、息吹さん」
「そうね白菊。正直いってとっくに大学野球に生活は切り替わっているし、今日は卒業証書を受け取りに来ただけってのが本音。みんなとはこれからも会うだろうし」
「キャプテンと理沙先輩と共に、グラウンドで会えるのを楽しみにしています」
白菊は腰を折って一礼し、息吹は軽く右手を上げた。
目には微かな闘志。
軽やかに笑んだ2人は、反対車線に停車していた大村家の使用人が運転する外車に乗り込む。彼女たちも去った。もう新しい仲間が家族なのであろう。
別れではなく、門出といった空気だ。
そして残った4人は同じ道を行く。
稜がサバサバと笑う。
「ンじゃあ、私と菫は家に帰ってから美月さんと合流する。ヨミと珠姫、2時間後、駅前の駐車場で待ってるからな。運転の順番はジャンケンで決めようぜ」
大学生活用のシェアハウスを契約済みなだけではなく、共同出資で購入したワゴン車を納車したばかりである。そのワゴン車でシェアハウスに行く。本格的な引っ越し作業をしなければならない。
そうして校門前にいるのは詠深と珠姫のみ。
涼やかな風が吹き抜ける。
自然に微笑み合っていた。
「さて、と。これからも一緒に歩いていこうか、タマちゃん」
「そうだねヨミちゃん、行こうよ、どこまでも2人で一緒に――」
見上げると、紺碧の青空が広がっていた。
FIN
◆EPISODE:後日談 ~27歳の秋~
山崎珠姫、27歳の秋。
今日は久々の完全休日だ。
天気も快晴。
思えば、この1年間は、まさに激動の日々であった。
待望の休日の午前中、珠姫は詠深とキャッチボールをしている。
高校3年の秋にキャッチボールした、あの河川敷で。
あれから、高校卒業から約9年の歳月が過ぎていた。
「ナイスボール」
詠深の球を受ける。だいぶイイ感じになってきた。
嬉しそうな詠深を見て、珠姫も心が躍る。
「お~~、やってるなぁ2人共」
車道からそう声をかけてきたのは、停車した赤いフェラーリの助手席から降りてきた稜である。稜に続いて、運転席から菫も姿を見せた。
「最近、身体を動かしていないんだから、あまり無理するんじゃないわよ」
「明日から、またスケジュールがギッシリなんだから頼むぜ、稼ぎ頭」
詠深と珠姫は現在、大学卒業と共に菫が立ち上げたマネジメント会社の正社員だ。その会社名は『アスリートマネジメントSUMIRE』である。
菫が社長、稜は副社長兼専属スポーツライター。
立ち上げ時から松岡凛音、川原光、中村希といった人気プロ野球選手とマネジメント契約を結べた事により、とんとん拍子で会社は大きくなり、起業5年目で従業員12名を抱えている。新越谷の後輩でNPBに進んだ者や、光と希のコネから契約に漕ぎつけた大物NPB選手や他分野の世界的アスリートとも仕事ができていた。
藤田 菫といえば、今や業界内でも名が通っている敏腕経営者、やり手社長だ。
稜が言った。
「手術した肩の調子はどうだ? ヨミ」
「痛み的には問題ないかな。名医になったよね、芳乃ちゃん」
芳乃は東大医学部卒業および医師免許を取得。研修医を経て独立開業(大卒時には自身が医院長の病院を設立済み、つまり在学時から開業準備はしていた)している。まだキャリアは浅いが、執刀やリハビリも含めて評判は上々であった。開業資金は希と光が共同出資している。スタッフや機材も十分だ。希はプロ引退後、野球界には残らずに芳乃の病院で働くつもりだという。
菫の会社の大株主の1人も光であった。
それから光だけではなく息吹も。
大学時代、高校時代に戦った多くの選手が、今やプロ野球選手として活躍中だ。
特に、新越谷時代の同期達――
希と光はハードバンクの絶対的主力および人気選手である。
共に今シーズンの推定年俸は3億5千万円だ。
怜、理沙、白菊も1軍の戦力として頑張っている。
3人共、年俸は1億円を超えていた。
なにより息吹。
10球団競合のドラフト1位。1年目からショートのレギュラーとして活躍し、新人王を獲得。2年目から3年連続セリーグ首位打者&盗塁王、最高出塁率。プロ4年で5億円まで膨れ上がった年俸をこの先も支払うのが困難と、ポスティングでメジャーに移籍。
メジャー移籍1年目から首位打者・盗塁王・リーグMVPと驚異的な結果を残す。セカンドへのコンバートが予想されていたが、ショートの守備指標も及第点だった。
まだFA権を獲得していないので年俸6億円だが、FA権を獲得した暁には1年40億円超えの大型複数年契約が確実視されている。
そんな中――
詠深と珠姫はプロ野球選手ではない。
菫が感心する。
「かなり様になっているわね、ヨミの左投げ」
詠深はニヤッと笑う。
「草野球デビューに向けて、準備はバッチリだよ」
かつての面影がない左投げの直球を受け、珠姫が言った。
「ナイスボール」
大学4年の秋――
詠深たちは念願の大学野球日本一を果たし、ドラフトを待っていた。
12球団のスカウトからの評価を高校時代よりも上げた詠深は上位指名が確実視されていた。そして珠姫はドラフト候補に名を連ねる程に、結果を出し実力を伸ばした。
堂々と「2人が同じチームでなければ渡米してマイナーリーグ」と公言する。
詠深と珠姫の意思に応えたのが、ハードバンクだ。
必ずセットでの指名、詠深2位・珠姫3位を公言した。
これには希と光も喜んだ。
そしてドラフト当日。
次々と1巡目1位に息吹が指名されていく中、ハードバンクが1位で詠深を指名。
詠深以上に珠姫が喜ぶ。詠深単独1位は確実。そして1巡目2位で珠姫を指名する球団がハードバンク以外にある筈がない。
つまり、揃ってのNPB行きは確定したも同然。
1巡目1位、最後の球団の指名――
『1位 山崎珠姫 捕手 珠川大学』
2人は抱き合って号泣した。
その様子を、マスコミは歓喜の号泣と報じる。共にドラフト1位で念願叶ってのプロ入りだ。コメント拒否も喜びのあまり言葉が出ないからだと。
しかし、そこからの2人の行動は早かった。
卒業を待たずに即日で大学を中退してしまうと、すぐに渡米したのである。
賛否両論で、日本国内は荒れに荒れた。
だが、詠深と珠姫には関係なかった。
マイナーリーグは1年半で卒業。
メジャー昇格を決め、そのまま定着して迎えた26歳の秋。
つまり去年の秋である。
その日は、ワールドシリーズ優勝がかかった大一番。
レギュラーシーズンで、詠深はサイヤング賞の最右翼という活躍をみせた。
珠姫もチーム正捕手として充分な成績を残している。
SP詠深、スタメンマスク珠姫だ。
詠深は試合前、こっそり珠姫だけに打ち明けた。
「ゴメンね、タマちゃん。実はもう、肩、限界っぽいんだ」
信じたくない告白。
「肩? 肘じゃなくて?」
「うん。肘なら手術で復帰可能かもしれないけれど、この肩の痛み方は、手術してもたぶん、もう、メジャーで通用するレベルには戻らないと思う」
「いつから?」
「夏の終わり頃から、かな。肘だったら来シーズンの復帰を最優先したけど、今年のチームはワールドシリーズ狙える状態だから、このチャンスを逃したくなかった。最初で最後のチャンスだと思ったから。このシーズンに全てを賭けたかった」
珠姫は何も言えなかった。
知ってしまえば、詠深を裏切ってでもチームに報告していたから。
「悔いはないよ。渡米してから全力で駆け抜けた。武田詠深のメジャーリーグ編はこの試合で最後。引退して日本に帰ったら、左投げに転向して次の草野球編を始めるよ。でも、タマちゃんは後10年はメジャーでやれる。だから私の分もメジャーで頑張って」
珠姫は怒りを込めて言う。
「逆の立場だったら、ヨミちゃんは独りでメジャーに残る? 私は1日だって忘れていないよ、高校3年のドラフトの日。ヨミちゃんは私と野球を続ける為にNPBに進まなかった。私もあの時のヨミちゃんと同じ気持ち」
詠深は笑った。
「そっか、じゃあ一緒にメジャーリーグ編を今日で完結して、2人で日本に戻って新章・草野球編を始めようか、タマちゃん」
そして――試合は2対0で最終回ツーアウト。
得点は珠姫の2ランHRだ。
観客は沸騰している。何故ならば――
ここまで1人のランナーも許していない、パーフェクト・ピッチング。
背番号43が躍動する。
詠深らしい、楽しみつつ暴力的な投球が光っていた。
ワンボールツーストライク。
珠姫の要求は強直球。
これがメジャーリーグで受ける、プロの舞台で受ける、詠深の右腕からの最後の球。
今までで最高のボールが珠姫のミットに収まった。
空振り三振、ゲームセット。
ついに世界の頂点だ。
ワールドシリーズ制覇、それも完全試合達成で。
両腕を突き上げ、詠深は夜空に吠えた。
超満員の歓声が地鳴りを生む。
珠姫の視界が涙で揺らぐ。
この光景だ。高校3年のあの日から、珠姫は誰よりもこの姿を見たかった。
一番近いホームベースからマウンドの詠深の栄光を見たかった。
プロでスターになった詠深――
世界一のピッチャー、武田詠深!!
高校1年の夏、梁幽館に勝った時の様に、珠姫は詠深に向かって駆けた。
詠深は珠姫を抱き留める。
すぐに2人は他のチームメイト達に、もみくちゃにされた。
そこからの約1年間は激動の日々だった。
2人揃っての電撃引退。
武田詠深 ー背番号43ー
ダイヤモンドバレッツ所属:実働2年半
メジャー通算41勝(引退26歳)
通算防御率1.95 通算WHIP1.08
通算QS率8割5分 通算奪三振率10.3
レギュラーシーズン ノーヒットノーラン2回
ワールドシリーズ パーフェクト1回
サイヤング賞1回
ワールドシリーズMVP1回
オールスター出場1回(SP)
アマチュア時代:大学野球日本一、U22日本代表、U22アマチュア世界大会優勝、高校春の全国優勝投手、高校夏の全国優勝投手
経歴:新越谷高校(卒業)⇒珠川大学(中退から卒業認定)⇒ヒルズボロ・ロップズ(A)⇒リノ・ビーシズ(AAA)⇒アリゾナ・ダイヤモンドバレッツ(MLB)
球団は、チームを25年ぶりの世界一に導き、渡米する経緯および渡米してから引退に至る過程とその輝かしい実績に敬意を表し、背番号43を永久欠番とする事を正式に発表。
詠深の右肩の手術とリハビリ。
手術とリハビリは成功したが、やはり本来の球速とスピンは戻らなかった現実。しかし詠深に落胆はなくサバサバしていた。
日本帰国後はTV出演、講演、インタビュー、トークイベント、様々な対談企画、YouTubeのコラボ――嵐の様な忙しさ。菫の会社の世話になる事になったが、自分達のマネジメントを自分達でする羽目に。
「ナイスボール」と、珠姫。
中学地区優勝レベル相手なら通用するかなぁ、と感想して詠深に返球した。
稜が上機嫌で言った。
「ヨミか珠姫の単独講演は300万円から。2人セットなら500万円から。この条件で2年先まで予約ビッシリだぜ。いやぁ~~最高最高」
「世間が私とタマちゃんに飽きてメディアの仕事がなくなったら、私も他の社員のみんなみたく選手のマネジメントがしたいなぁ」
野球以外の道を知り体験する事が、想定よりも早い段階から叶い、プロ引退のタイミングとしてはベストだったのかもと、最近の珠姫は思っている。まだ全員で16名の零細に過ぎないが、これから自分たちの力で会社を大きくしていくという目標もできた。
菫は冷静に言う。
「予定ビッシリは数年だろうけれど、ヨミと珠姫の伝説と偉業を考えると、メディアの仕事が暇になる日はたぶん数十年は来ないと思うわよ。だって、単なる記録じゃなくてそれだけのストーリー性だもの」
「私が書いたヨミと珠姫の本、4冊ともバカ売れだしな。会社と折半とはいえ印税ガッポガッポで、お前たちには感謝しかないぜ」
稜はセカンドハウスとなる高級マンションを、現金一括で購入したばかりである。
スポーツライターとして有名になり、他の著書も芋ずる式に売れていた。
「私は野球がしたいってだけで、有名税とかお金とかは、もう辟易だよ」
実働年数が僅かとはいえ、メジャーでの活躍とその後のメディア仕事の収入で、詠深には軽く数億円の貯蓄はあるが資産管理が面倒なので、手元に1億円だけ保険として残し、残りは全て菫に委ねてしまった。もしも会社経営がピンチになったら社員を守るために使って欲しいとも伝えていた。多忙で月給の90万円すらほとんど余る。インセンティブの取り分(月2000万円以上)は全て会社に還元していた。
「そうだね、ヨミちゃん。世界の頂点で戦えたのは良かったけれど、なんだか今の日々の方がホッとしているかな。正直もう、あの頃に戻る気にはなれない」
メジャーリーグはもちろんNPB球団からも、珠姫現役復帰の要望が強い。
しかし珠姫にその気は一切起きない。だって詠深がいないから――
「うんうん。メジャーリーグで活躍するのは松岡さんや息吹ちゃんに任せて、私達はまたこの4人で、希ちゃんやキャプテンの試合を生観戦しに行こう」
「悪いけどヨミ、NPBの観戦リポーターや、渡米しての来シーズンの息吹への単独インタビューはTVの仕事として入っているから、そのつもりでいてね。珠姫もNPB秋季キャンプのTVリポーターと、来シーズンから解説の仕事ジャンジャン入るから」
「菫ちゃんは鬼社長だ」と、苦笑する詠深。
詠深は珠姫にカットボールを投げた。
「ちゃんと曲がったかな?」
「全然ダメ。単なる棒球だよ」
珠姫は詠深に返球する。
2人一緒なら、こんなにも楽しい。
ただのキャッチボールでもだ。
これからもずっと、詠深と野球をしていこうと思った。
『球詠アフター』AFTER

◆EXTRA:続・YouTuber中田奈緒(前)
YouTubeチャンネル『中田奈緒の埼玉魂』は9年目を迎えている。
メンバーの1人である松井遥菜は、未だにグループを脱退できないでいた。
遥菜は脱退したいのに、そんな彼女を差し置いてグループを抜けてしまった者もいる。誰もがそれなりの理由があった。
1人目は愛甲。プロ入り5年目に戦力外通告。
YouTubeチャンネルも含めて全てを1から出直したい、という彼女の希望に、奈緒は愛甲のセカンドキャリアに対して、コネと援助の限りを尽くした。愛甲は今、某企業の企画営業職として充実の日々を送っている。
遥菜としても、今もたまに連絡を取り合う友人関係を続けている。
2人目は朝倉智景。
智景と同じ球団に入った大野彩優美、大島留々の『ドラゴントリオ』チャンネルに、引き抜かれてしまった。Wエースとなった彩優美と智景。切り込み隊長として活躍の留々と、3人揃って1軍の主力だからこそだ。奈緒は快く送り出した。
その時、自分も送り出すというか、解放して欲しいと遥菜は強く思った。
3人目と4人目は園川 萌と諸積恋美。
表向きは球団側の事情という体裁になっているのだが、実際はメンバーの中でYouTube視聴者の人気がイマイチだったかららしい。1軍のセットアッパーとして定着の萌と4番打者として好調の恋美。YouTuberとして人気が出なかったのは、セルフブランディング的に好ましくなかったという訳だ。
不本意ながら遥菜はメンバーの中でも人気は上位である。理由は分からないが。
そして新規メンバーはゼロである。
翌年から埼玉県の高卒ドラフト組は、誰1人として近寄ってこなかった。
加えて、大卒ドラフト組・社会人ドラフト組からも敬遠される始末だ。
現在、チャンネル登録者数――813万人。
遥菜的に悲しい事に、チャンネルはビジネスとして大成功を収めている。
現在進行形で上手くいっている。専属の撮影・企画台本・編集スタッフ5名が本業として成り立っているレベルだ。チャンネルスタッフ用のマンション一室も確保している。
YouTube関連から収入は、遥菜個人で年間約4000万円の取り分があるのだが、年俸4億円+個人スポンサー料年1億5千万円の遥菜にはどうでもよかった。
今日の撮影のメインコメンテーターは遥菜だ。
奈緒はスケジュールが合わずに、後で合流する予定であった。
カメラの前で遥菜が言った。
もうキャリア9年なので慣れたものである。
「本日のスペシャルゲストは、みんなお馴染み、アメリカ メジャーリーグ ダイヤモンドバレッツの元エースピッチャー武田詠深さんだぞ」
「こんにちは、武田詠深です」
詠深はにこやかに挨拶した。
「先日データストックから発表された、1万人が選ぶ日本人が好きなプロ野球選手ランキング、3年連続の1位という偉業、おめでとうございます」
「いやぁ~~、もう「元」プロ野球選手だから、今年の1位は恐縮ですね」
(そうだよ! なんでお前が今年も1位なんダ)
ドラマチックなストーリーが受けたのか、1位が詠深・2位が珠姫が続いている。
遥菜のランキングは3年前から12位⇒15位⇒13位と推移していた。
納得がいかない。
ルーキーイヤーからレギュラー奪取、そこから高水準の成績をコンスタントに残し、去年と今年は2年連続でのトリプルスリーを達成。せめて5位以内に入って欲しかった。
「現役の方に悪いから、来年は候補から外して欲しいですね」
光が言った。
「現役と引退選手は分けた方が、確かにいいかもしれないね」
「光先輩、先日のトークイベントでは色々とフォロー、ありがとうございました」
メンバーの多くが1軍の主力である為に、チャンネル開設当初に比べるとスケジュール調整が難しくなっている。全員が揃うのは、年に2~3回が限界であった。
なお、希はスケジュールの都合がつかず今日は欠席している。
この場は遥菜と光で回す台本だ。
「それってギータさんと希、武田さんと山崎珠姫さんの新越谷OG4人が揃った、福岡で行われたハードバンクホークスのトークイベントだよな?」
「はい。気軽に詠深で良いですよ。同学年だし高校時代対戦しているし」
「じゃあ、このチャンネルの流儀に倣ってヨミで」
「私も遥菜ちゃんと呼んでいいですか?」
「どうぞどうぞ。で、現在のヨミはタレント業がメインの活動なのは周知の事実として、肩書としては会社員と聞いているんだけど」
「タレントっていう自覚はないんですけど、現役時代にお世話になった方々への恩返しって感じですね。所属している会社は、高校大学と野球部のチームメイトだった菫ちゃんが立ち上げて社長をしているマネジメント会社です。これでもサラリーマンですよ」
光が宣伝する。
「その会社『アスリートマネジメントSUMIRE』は、このチャンネルのメンバーもマネジメント契約を結んでいるので、この動画をご覧になっているプロアスリートの方、興味を持ちましたら概要欄のリンクからホームページに飛べますよ」
「じゃあ、ヨミもアスリートのマネジメント業務をやっているんだ?」
詠深は苦笑した。
「それが私とタマちゃんは自分たちのスケジュール管理で一杯一杯ですね。世間の熱が冷めてタレント業が暇になったら、私も一般業務に挑戦予定です」
「それだけではなくヨミちゃんは、草野球チームを立ち上げたんだよね」
「はい。来シーズンから地元の草野球公式リーグに殴り込みをかけますから、興味がある人は是非とも応援よろしくお願いします。サウスポー投手として生まれ変わったニュー武田詠深が見られますよ!」
「左でどれくらい投げられるんだ?」
「あははは。プロレベルどころか高校野球でも全国レベルだと通用しないかと。練習も就寝前にタマちゃんや稜ちゃんとの個人練習メインです。チーム練習はほぼ無しで、試合でぶつけ本番ですからね」
「動画の後半では、ヨミちゃんの左投げに対し、私と遥菜ちゃん、そして後で合流する奈緒さんが対戦しますよ」
「よ~~し、奈緒さんと一緒に高校時代のリベンジだゾ!」
「5打席で1回でも打ち取ったら私の勝ちルールでお願いしますね」
(さて、いよいよだ、な)
ここから遥菜は、奈緒からのミッションをこなさなければならない。
「ええ、と、頼んでいた物、持ってきてくれたかな?」
遥菜の台詞に、光も視線を落とす。
またいつものアレか、と諦めている。光用の台本にはなかった。
「浅ましい」「セコい」「クレクレ乞食」「集り集団」「見苦しい」「恥知らず」とアンチにけなされている、当チャンネルではお馴染みの恒例企画だ。
詠深はそれを披露する。
「これがワールドシリーズのチャンピオンリングです」
「うわぁ、何度見ても凄いって思うよ」
「ギータさんは前に見た事あるのか」
「うん、高校の同窓会で。全ての野球人にとって憧れだからね、これ」
遥菜は不自然に話題を変える。
「そうそう、奈緒さんに言いつけられていた、恒例のプレゼント企画のお知らせを忘れていた。スタッフさん、持ってきてくれ」
(くそ。またアンチ共にボロクソ叩かれるのカ)
「奈緒さんの通算300本塁打のサイン入りバットとボール、ギータさんと私の通算250本塁打のサイン入りバットとボール、陽さんの通算200本塁打のサイン入りバットとボール、そして希の通算150本塁打のサイン入りバットとボール、それぞれ視聴者の皆さんにプレゼントするからナ!」
光がいたたまれない表情になった。
ここからおねだりする流れだが、いくらなんでも物が物だけに――
詠深が爽快な笑い声をあげた。
「あはははは! じゃあ、私のチャンピオンリングもお土産として、最後に視聴者プレゼントにしちゃってください」
「マジか、ヨミ!」と、遥菜。
「ホントにいいの、ヨミちゃん?」と、光。
「うん。最初からそのつもりで持ってきていたし。映像や記念写真は大切に取って置いているけれど、記念品やサイン入り用具とかは全部、欲しがっている人に寄贈しちゃったんだよね。それで最後に残ったのがこのチャンピオンリング。これだけは受け取れないってみんなに言われてさ」
「そういえば、ヨミちゃんの家、記念品とか用具の棚がなかった。てっきり専用の一室があるものだとばかり」
「記念写真を飾っている部屋はありますけど、物は本当に何も残していません。今の私には必要ないから。というか、光先輩の家だってYouTubeの視聴者プレゼントのせいで、記念品用の棚、スッカスカじゃないですか」
「そうなんだよね」と、光は苦笑するしかなかった。
対談はつつがなく終わり、いよいよ奈緒が待つ「とある」場所へと移動する――
後半へつづく。
◆番外編:息吹のキモチ ~26歳の冬~
川口息吹、26歳の冬。
今シーズン限りで息吹はNPBを去り、ポスティングシステムにてMLBへ移籍する。
挑戦という気持ちは薄い。どちらかといえば、主に財政面のチーム事情でメジャー移籍せざるを得なかったのだ。想定を上回るハイペースで増え続ける息吹の高年俸を、この先も同じペースのアップ幅で支払い続けるのは無理、と球団側から伝えられてしまう。頑張っても後2年でチーム総年俸を考えてもギブアップだと。
パリーグへの移籍話もあったが、交流戦を考えると国内ではなく海外球団へ息吹を高値で売り飛ばしたいというビジネス面もあった。
来シーズンから所属球団が変わる。
横浜ベイヒーローズからニューヨーク・メシアズに。
海外生活に気乗りはしないが、もうNPBに居場所がないのも肌で感じていた。
これ以上、日本で無双してもファンは喜ばない。
凄まじい数のファンから届く「もう日本でやる事はないから、メジャーに挑戦して欲しい」という希望と期待。代理人に「契約条件を下げてでも横浜に残る」とオーダーすれば残留は可能かもしれないが、誰もが白けるだろう。それは息吹が望む事ではなかった。
キャプテン――岡田 怜との野球もこれで終わり。
同じベイヒーローズで6番センターの主力である怜とも、来年から離れ離れだ。
ハードバンクの松岡凛音もMLBのボストン・ブルーソックスに移籍するが、凛音は本人が強く希望してのメジャー挑戦である。
(あーあ、新越谷1年生の頃に戻りたいな)
タイムスリップできないかな、と息吹は妄想しながら目的地に着いた。
ちなみに場所は福岡である。
真新しい立派な建造物。
名前は『川口スポーツクリニックセンター』。
新米ドクターでありながら、芳乃が自らをオーナーとして開業した中規模の病院だ。
医院長は芳乃。
副医院長は研修医だった頃の息吹の師匠である。
場所が福岡なのは、希が九州出身なのと福岡ハードバンクに所属しているからだ。
(やっぱり希はメジャーに興味なし、か)
希と光、両者ともにメジャー移籍の声が掛かっていたが、希は興味がないと即答し、光はメジャーで通用する自信がないし生涯ホークスが希望、と断っていた。2人とも年俸面では銭闘する意思はなく、かつハードバンクはNPBでも屈指の資金力を誇る。
(希は、芳乃と光先輩の傍で野球ができれば、それで良いっぽいもんね)
交流戦でドラゴンレイズの大野彩優美との対戦も、希は楽しんでいる。
希の居場所はMLBではなくNPBだ。
受付にて、見舞いの為の入館手続きを済ませて、息吹は506号室へ行く。
五階建ての最上階で、最もグレードが高い個室だ。
入院患者は息吹を大歓迎した。
「お~~、息吹ちゃん、久しぶり!」
「元気そうね、ヨミ」
「元気元気、明日から本格的なリハビリ開始だよ」
包帯でガチガチに巻かれている右肩を見せる詠深。
お土産を渡し、息吹はベッド脇の丸椅子に腰かけた。
「珠姫は?」
「昨日から埼玉だよ。タマちゃんはタマちゃんで忙しいから。私はここでコッソリと療養するしかない身だけどね」
「肩腱板と関節唇がかなり損傷していたヨミは、引退は仕方がない選択かもしれないけど、怪我も故障もなくこれからピークを迎えるまだ若い珠姫がメジャー引退は、常識的に考えてとんでもない事だものね。色々な関係者が大パニックでしょ」
「代理人さんからの連絡が凄くて凄くて。もう代理人さんとも契約解除したんだけどなぁ。タマちゃんだけでなく私にも復帰を勧めてくるし、タマちゃんの引退は馬鹿げているって。まあ、実際に馬鹿げていると私も思うけど」
「復帰の道は探らないの?」
「無理じゃないかな。マイナーリーグ時代の1年半は本当に過酷な環境でさ。メジャー昇格のためにかなり無理をした自覚あったから。だから精密検査の結果にも納得だよ。本当にボロボロだったからね。メジャー昇格時のメディカルチェックはクリアできたから油断したというか、今年の夏くらいから一気にガタがきた。左投げでまた痛みなく野球ができる様になってくれれば、それで十分だし御の字」
「そっか、無理か。メジャーで対戦できると思っていたから、残念」
「左投げに転向して草野球に挑戦するよ。息吹ちゃんもプロ引退したら、草野球に来なよ。そこで楽しく対戦しよう。試合終わったら一緒にBBQとかしてさ」
明るい詠深の笑顔。
こんな風に笑えるのが羨ましい。
本当は五体満足で故障がない自分が、好条件でメジャーに移籍する自分が、詠深どころか、どのNPB選手にだって羨ましがられる立ち位置なのに。将来の夢がメジャーリーグという高校球児だって沢山いるのだ。
息吹は無理に笑ってみせた。
「悔いはないって感じね」
「プロ野球選手、メジャーリーガーとしては「やり切った」って思っているから。それに私の野球そのものに終わりはないし。草野球で物足りなくなったら、その時はその時で指導者の道を模索するかもね」
「今後の予定は?」
「球団からコーチ留学の為のポストを用意してくれるって話が来ている。他にも多くの芸能事務所、ノンプロや母校、あ、大学の方ね、からコーチの誘いとか、色々なところから声を掛けてもらっているから、タマちゃんと2人でじっくりと考えたいかな」
大学4年時のドラフトの後、卒業を待てなかったので退学届けを出して、強引にアメリカに飛び出した詠深と珠姫であった――が、メジャー昇格を決めた年のオフに「退学届けは不受理だった、卒業証書と学生表彰および学長賞と理事長賞を贈りたいから、1日だけ来校してくれ」と大学側から連絡がくる。もちろん大卒の学歴はマイナスではないので、ありがたく頂戴した。というか、メジャー昇格のニュースが日本に駆け巡った翌日から、大学HPの卒業生著名人欄に詠深と珠姫が、ちゃっかりと追加されていた。
詠深と珠姫2人だけの卒業式と表彰式は、大学側が招いたマスコミが大勢いた。
「そうね。焦る必要はないわね。困ったことがあったら言って。少なくとも金銭的な援助はこれからいくらでも可能だから。って、ヨミと珠姫ならそんな心配は余計なお世話か」
詠深が心配そうに言う。
「息吹ちゃん、なんだか元気ないね。これからメジャーリーグだっていうのに」
息吹は肩を竦めた。
「気のせいよ。ま、あっちで2割5分とかで等身大の現実を示したら、ファンが私に見ている幻想も冷めるかもね。私は希みたいな天才とは違うから」
何か言いたそうな詠深を振り切り、息吹は病室を辞した。
そして少し迷った末に、院長室にも寄る。
伝えなければならない件もあるし、やはり会うべきだろう。
けれども双子の妹には、今の心理状態を見抜かれるかもしれない。そう思うと、あまり気が乗らないのも事実だ。SNSで連絡は取り合っているので無理に会わなくても――
「久しぶり、芳乃。順調そうね」
「うん、順調だよ。お姉ちゃんの方はこれから色々と大変そうだね」
「医師と経営者、希と光先輩のアドバイザーも兼任しているアンタの方が大変でしょ。私は極論すれば、野球をやっていればいいだけだから」
「NPBでの日本一は叶わなかったけれど、メジャーリーグで世界一、期待しているから」
「大学時代は、アンタ、本当に私達じゃなくてヨミ達を応援するし、NPBじゃ日本シリーズに進出できなかったし、なかなか上手くいかないものね」
本当は世界一よりも、怜と日本一になりたかった。
芳乃が自慢する。
「ヨミちゃん達からの大学日本一のウイニングボール、私の宝物だからね」
「そういえば、私は芳乃にNPBでの記念品とかあげたことなかったわね。何かいる? 欲しい物なんでもあげるわよ」
絶対に漏らせない本音――もう息吹にとってはガラクタ同然だ。
生涯で1タイトルも獲れないで引退する選手がほとんどである。だから絶対に口にできないが。捨てるわけにいかないから、取って置いているだけ。
「ん~~、今更そんな事を言われても困るかな。希ちゃんからも特にもらっていないし。まあ、希ちゃんはYouTubeの視聴者プレゼントで記念品の大半が消えているけど」
「8年続いているの、凄いわよね、あれ」
「登録者数700万人を突破だっけ」
「でも途中で、メンバーの愛甲さん久保田さん田辺さんが戦力外通告とか、厳しい現実も見せてくれているわね」
「久保田さんは高校時代に対戦しているから、残念だったね」
愛甲は1軍0安打、久保田は1軍7安打、田辺は1軍77安打で終わった。
珍しい結果ではない。通用しない選手は4~6年でひっそりと消えていく。
「ヨミと珠姫も引退だし」
「終わりは必ず来るよ。ヨミちゃんと珠姫ちゃんの2人にとってのプロ野球選手としての終わりは、あそこがゴールだった。長期的に見たら、無理に現役や野球界にしがみ付くよりも良いと思う。どんなに長く現役でいられても引退後の人生の方が長いんだから」
「野球に限らず、スター選手が引退後に破滅する話は後を絶たないしね」
そう考えると、医師という終わりのない道を進む芳乃は凄いと思う。
妹は天才で、自分は天才ではない。
「引退後、なにしようかな」
「お姉ちゃんの実績なら、現時点で怪我とかで引退したとしてもNPBのコーチ、どの球団からも引っ張りだこでしょ。メジャーで成功すれば、それこそ選択肢は。でも下手に門外漢のビジネスには手を出さない方が良いとは思うよ」
「そうそう、危うく伝え忘れるところだった。私の資産管理、芳乃に任せるから。もう顧問弁護士と税理士には伝えているわ。この病院のために好きに使ってくれても構わないわよ。税金対策さえシッカリしてくれれば、それでいいわ」
芳乃は苦笑する。
「お姉ちゃんのお金に手を付けなければならない状況って、経営者として失格だから、私のプライド的にそれは絶対にないかな。でも、これから先のお姉ちゃんの収入を予想したら、資産管理用の会社、ちゃんと立ち上げて管理しておくよ。運用は堅実第一で」
「任せたわ」
「何があっても、お姉ちゃんが世界中を敵に回しても、たとえそれが希ちゃんであっても、私だけはお姉ちゃんの味方だよ。だって私達は双子なんだから」
「ありがと、芳乃。今日は湿気た顔を見せて、ごめん」
そうして息吹は病院を後にした。
ここは福岡。横浜よりは人目を気にしなくて良い。
(いや、周囲も遠慮しているだけかも)
こんな気持ちを隠し切れない表情だろうから。
野球ファン以外にも知名度はそれなりに、いや、トップクラスである方だ。
データストック調べによるプロ野球選手人気ランキングでは、毎年5位以内をキープしている。今年は1位・詠深、2位・珠姫、3位・光、4位・凛音、5位・息吹だった。
(あの希が16位、か)
おもしろくないのは、怜がトップ50から外れている事。
怜は53位であったが集計方法に偏りがあるのではないか。そもそも引退済みの選手が多数ランクインしているのは根本的に間違っている。
「冴えない顔しているな、息吹」
「キャプテン」
怜が――いた。
病院から出てすぐの歩道で、待ち構えていた。
なんとなく分かってしまった。
嫌な感じばかりが強い。
息吹はぎこちない声で言う。
「福岡にいたんですか。だって今日は東京にいる筈じゃ」
「うん、芳乃から連絡をもらって急遽、な。もうそろそろ限界だと思うから、息吹を頼むってお願いされてな。息吹に現実を思い知らせる事ができるのは、私だけだって」
「現実って、なんですか」
「いい加減に目を逸らさずに、現実を受け入れてくれって事だよ」
「だから、現実って――」
怜は冷酷に告げる。
「息吹、もうお前は私や理沙どころか、希だってとっくの前に選手として超えているっている現実だ」
全身を震わせた息吹は視線を落とす。
懸命に顔を上げるが、笑顔を作ろうと努力している表情は明らかに壊れていた。
キャプテン、ハ、ナニヲ、イッテイルンダ?
みっともなく震える声で、息吹が応える。
縋るように言った。
「バカの事を言わないで下さいよ。希は私とは違って天才バッターですよ。希どころか、キャプテンにも私はまだまだ及びません。未熟だから、もっともっとキャプテンに指導してもらって、1人前になれる様に鍛えてもらわないと――」
景色がひび割れていく。
足元がぐにゃぐにゃと歪む。
いつからか、現実が――狂い始めた。
高校1年生の頃、キャプテンに野球を習い始めた。自分はまるっきり素人だった。
高校2年生に進級して、初心者の自分は経験者の後輩にレギュラーを奪われると思っていたが、そうはならなかった。少しは上手くなっていたかも。
高校3年生、キャプテンがいない野球部で、なぜか周囲は自分と希が同格であるかの様に扱い始める。過大評価も凄いなと思っていた。
大学に進学し、再びキャプテンと野球ができる喜び。でも、まだまだだ。もっともっとキャプテンに鍛えてもらって、少しでも追い付かないと迷惑になる。
そして大学3年の秋、キャプテンはドラフト2位でプロ入りを決め最高の気分だった。理沙先輩もドラフト4位でプロ入りだが、キャプテンとは別チームになる。残念だ。
大学4年の秋、いや、もっと前からか。12球団のスカウトが必死にアピールしてくる。キャプテンと同じチームのスカウトだけでいいのに。
史上最高のドラフト1位10球団競合。不思議だ。実感は皆無だけれど、運よくキャプテンと同じチームに。それだけが全てだ。白菊もチームは別だが、ドラフト3位でプロ入りできたのは、良かった。ヨミと珠姫が強引に渡米して、日本は大騒ぎになる。
プロ1年目からショートのレギュラーとして試合に出られた。でも、キャプテンはレギュラーではない。同じ1軍なのに、どうして私だけレギュラーなの?
プロ2年目にキャプテンもセンターのレギュラーに。また一緒に試合に出られる。キャプテンと一緒は最高だ。シーズンが終わると、なんか色々とタイトルを獲っていた。
プロ3年目――周りが煩い。キャプテンと試合に出て野球ができれば、それでいいのに。オールスターにどうしてキャプテンが出られないのか。1人では意味がない。なにか周りが言っている事を理解できなくなってきた。脳がバグる。
プロ4年目――メジャーメジャー騒がしいな。今年も去年と同じ様な成績だった。ああ、ホームランは26本から24本に減ったが、自分は出塁型でホームランバッターではない上にまだまだパワーレスだし。キャプテンに叱られると思ったが、叱ってくれなかった。もっと頑張れば褒めてくれるかな?
なんの為に、野球を――
「もう1回、高校1年からやり直せたら」
あんなにも野球が楽しかった。
ただ全国に行けたらって。
プロとか微塵も考えてもいなかった、あの頃。
「それが無理なら、大学1年からやり直せたら」
夢のような楽しさだった大学の寮生活。
プロどころか、別にレギュラーでなくても良かった。
大学もNPBも、ただキャプテンの背中を追っていただけ――
怜があるYouTube動画を再生した。
音声だけが聞こえてくる。
『なあ、希。お前と同じ新越谷出身の川口息吹が、セリーグで2年連続の首位打者を獲ったが、もしも同じリーグだったら希は打率で勝てるか?』
『まず勝てんやろうね、奈緒さん。正直いって今の息吹ちゃんは、私よりずっとレベルが上の選手やもん。そして息吹ちゃんはまだまだ本気やない。天才やと思うよ』
全身から力が抜ける。
息吹は両耳を塞ぐと、膝をついて項垂れた。
もう――嫌だ。どうしてこんな事に。
「去年の時点の会話だ。今年、例年より不調の希は3割1分に終わり、お前は3割8分台をキープして、3年連続の首位打者そして3年連続の盗塁王だ。1番ではなく中軸を打って長打狙いのバッティングをしていたら普通に三冠王という打撃指標だった」
「高校1年に戻りたい、です」
「私の来季の年俸は1500万円アップの1億2800万円だ。上出来というか私だとこの辺が限界っぽいな。希は来季推定で3億5千万円だっけ。希と光は全部1発サインだから、交渉すれば本当はもっと貰えるんだろうけどな。人気選手の希と光は、私とは違い年間スポンサー料も億単位だ。私はスポンサー料、実は800万しかない。で、この金額の差が私と希の選手としての価値の差だ」
「お金の話も、もう嫌です。芳乃に全部投げちゃいます。変ですよ、私の年俸、キャプテンどころか希より上とか。気が付けば海外の敏腕代理人が売り込んできて契約させられているし。私は最初から今までお金の為に野球はやっていないのに。10年で200億とか300億とか、訳が分からないです。スポンサーから入ってくるお金も、どんどん増えていって、正直いって怖いです。もう引き返したいです。引退したヨミと珠姫が羨ましい。あんな風に笑えるヨミが」
心と体と現実のバランスは、もう限界だ。
これなら、こんな現実ならば、下手クソなままの方が幸せだったのに。
怜は無理矢理に息吹を引き上げ、優しく抱きしめる。
「出逢って、もう10年か。10年だよ」
「はい、10年経ちました」
「思い出すと懐かしいな、10年前。私は高2でお前は高1。2人とも子供だった」
「あの頃に戻って、やり直したいです。できれば何度でも何度でも」
「高1のお前はスポーツ未経験で、モヤシみたいに貧弱な身体だった。注目選手になっていた大学1年の時点でも、まだまだ筋量不足のヒョロヒョロだった。でも、プロ入りしたお前のフィジカルはアスリートとして1人前になっていた」
「私の身体なんて、まだまだ弱いですよ」
「それが今や、私よりもずっと強靭なフィジカルになっている。最高の身体になった。メジャーリーガーと戦える、私なんかとは違う本物のフィジカルだ」
息吹は何も言えない。
自分を抱きしめる怜のフィジカルと自分のフィジカルの差を感じてしまうから。
筋肉の厚みと筋肉の密度が、体幹が、しなやかさが明らかに違う。
「認めろ、息吹。今こうしてお前を抱きしめる私の身体を、どう感じる」
「嫌です。認めたくないです」
「現実を見て、前を向こう」
「ひ、ひ、貧弱だって感じます。明らかに体幹とバランスが足りません。キャプテンのフィジカルは自分よりも弱いと分かります。ハッキリと分かってしまいます」
「私と希のプレーを見て、本当にお前が感じていることを、正直に認めろ」
「プロ入り2年目くらいから、どうしようもなく、信じたくないけど、キャプテンのプレーは下手だと感じてしまいます。希のバッティングも色々と物足りないです。2人とも、いつの間にか、凄くレベルが低くなっていました」
心に蓋をして隠していた本音を打ち明け、息吹は泣いた。
天を仰いで号泣する。
「そうだよな。今の私には息吹のプレーはレベルが上過ぎて、理解もできなければ真似しようとも思わない。それが現実だよ。だけど、それが私には、きっと希にも、他の仲間たちにも誇らしい筈だ。そろそろ自分の目標の為に野球をしろ。私の後を追うんじゃなくて」
「私の目標」
「高校、大学、NPBとお前は私の後を追ってきてくれたけど、そこから先のMLBに私はいない。だからここから先は、お前の道だ。お前自身の野球人生になる」
「どうすればキャプテンは褒めてくれますか?」
「そうだな。すぐにとは言わないが、いつかメジャーリーグでもNPBみたく首位打者と盗塁王を同時に獲る息吹を見てみたい。もし、そうなったら最高だろうな」
「はい、アメリカで頑張ります」
「いつだって高校時代の仲間、大学時代の仲間、そして芳乃がお前についているのを忘れるなよ。私も芳乃も世界一になった息吹が見たいんだから」
息吹は怜を力強く抱きしめ返す。
子供だった高校時代、あんなにも逞しく感じていた怜の身体が、こんなにもか弱く華奢だ。
いつの間にか、こんなにも遠くまで追い越していた。
これからは自分の道を歩んでいこう――
――約1年後のオフ。
息吹は同窓会の会場に入る。
大学や高校が主催する大掛かりなパーティーではなく、新越谷高校の11人と杏夏が個人的に揃う、年に1度の楽しみの日だ。今回の幹事は稜が引き受けてくれた。
横浜にある洒脱な高級焼肉店。
それを完全に貸し切りにしている。
「遅くなりました」
稜が上機嫌で応える。
「おう、待っていたぞ息吹。お前が最後で全員が揃ったからな」
「お久しぶりです、藤井先生。お元気そうで」
「はい、息吹さんもお元気そうで何よりです」
軽く挨拶を交わしてから、まずは1回目の乾杯だ。
この日ばかりは息吹も禁止しているアルコールを解禁する。乾杯以外で、ビールよりも強い度数を何度も摂取するのは、本当にこの面子との集まりだけである。
「今日の予算は全て菫シャチョーのポケットマネーからだから、遠慮なくいこう」
「半分はアンタの給料から分割で天引きしておくからね、稜」
「ケチだな、菫」
簡単な近況報告を終えてから、菫が一同を代表して杏夏にネクタイを渡す。
このネクタイは全員がお金を出し合っている。
「先生、今年も新越谷高校の春の全国準優勝と夏の全国制覇、そして秋の関東大会優勝、おめでとうございます」
「ありがとうございます。大切にしますから。それから皆さんからの多額の寄付金、今年も本当に感謝しています」
「そういった話は、野球部主催の正式な同窓会の方で。私達も後輩の活躍は嬉しいです」
稜がぼやく。
「でもよー。高校の後輩たちは大活躍だし名門大学やNPBに選手を輩出しているけど、大学の方の後輩たちはサッパリ駄目なのは、ちょっと悲しいな」
白菊が言った。
「私達の大学の後輩たちは大活躍していますけどね、稜さん」
「どうせ私と光先輩は高卒やけん」
「あははは。大学にも後輩がいるというか、やっぱりキャンパスライフは今でも少しだけ羨ましいかな」
菫が場を仕切り直す。
「じゃあ、いいタイミングだから記念の祝いと記念品の贈呈といきましょうか」
稜が記念品の説明をした。
「今年はロレックス デイトナで揃えてみた」
「最新モデルに今日の日付、新越谷と各自のイニシャルを裏面に掘って、かつダイヤモンドで文字盤をカスタムした逸品よ」
怜は驚く。
「随分と豪勢だな。お値段的に凄いことになってないか」
「会社が儲かっているのと、ヨミと珠姫がインセンティブを受け取らないので、これくらいは余裕というか、税金対策でもあったりします」
理沙が喜ぶ。
「嬉しいわ。実は私、去年から趣味で腕時計をコレクションしているの」
左腕に着けているパーペチュアルカレンダーを見せる。
怜が首を傾げた。
「時計には詳しくないが、それ高いのか?」
「約2000万円するわ」
「待て待て。理沙の年俸で2000万円の時計って、まさかローン組んで買ったのか? それとも公表されている来季年俸1億1200万より、実はもっと貰ってるとか?」
「年俸はそれで合っているわよ。実はこの時計、光からのプレゼントなの。スポンサーさんからのルートで安く手に入ったからって。ふふ」
光が補足する。
「オフィシャルの場で着けて貰う事と、SNSでのブランドアピールを条件に、スポンサーさんから是非とも理沙ちゃんにプレゼントして欲しいって話だよ」
そこで理沙が半白眼になった。
「私、けっこうSNSで時計コレクションをアピールしていたのに、その件でアプローチしてくれたのが光だけって。みんな私の事なんて」
菫がフォローする。
「気が付いていたから、今回の記念品は理沙先輩の為にデイトナにしたんですって」
稜も続く。
「私も気が付いていたし、他のみんなも気が付いていたよな? ちょっと時計に疎いし話題を振りにくかっただけで。なあ、そうだよな!?」
稜が見回すと理沙、菫、光以外の面子全員が目を逸らした。
理沙は拗ねる。
「どうせ私のSNSなんて知名度低いし、プロ野球選手人気ランキング71位よ」
白菊が言う。
「大丈夫です、理沙先輩。私のランキングも70位ですから」
「私より上じゃないの」
怜は慌てて話題を変えた。
「そういえば、光と息吹はスポンサーからの提供品の縛りがキツそうだな」
息吹と光は、頭の先から爪先までスポンサー提供の高級ブランド品一色だ。
乗っている車から野球用具、さらにはハンカチまで全て。
靴下1つにしてもSNSや公式の場でスポンサー以外の代物を使うのは厳禁だ。契約条件に入っているので、それが義務である。
「もう慣れましたよ」と、息吹。
「私も慣れているけど、希ちゃんはそういうのが窮屈って、ここ数年はあまり個人でのスポンサー契約しなくなったよね」
「正直お金はもう十分やけん。私は自分が使いたい物を使いたい」
「後でコッソリと渡そうと思っていたけど、この流れなら忘れない内に渡しちゃうね。別の時計も2本ほどあげるよ。その腕時計とは違うスポンサーさんから。定期的にSNSでコレクションの1つとしてアピールしてくれればOKだって」
時計の箱2つを受け取った理沙が感激する。
「ありがとう、光! スポンサーさんの連絡先を後で教えてね。お礼するから」
息吹は自分の腕時計を外して、理沙に差し出す。
「理沙先輩、だったらこれもプレゼントします。箱は後で郵送しますから」
「こ、これパテック フィリップじゃないの!」
「気に入ったから自分で買った代物ですけど、私も光先輩と同じで普段はスポンサーの腕時計ですし。それなら理沙先輩に大切にしてもらった方がいいかなって」
「しかもこれ、レアモデル?」
「高い物だと数億円っていうブランドみたいですけど、それは確か4000万円くらいですよ。使うの今日で2回目の新品同様ですし、遠慮なく受け取って下さい。税金の処理は芳乃に任せますので」
「贈与税の脱税とみなされない様に、書類の上は分割払いでの売却という形式にしますね。領収書を毎月送りますから、支払証明書をお願いします」と、芳乃。
「ありがとー息吹ちゃん」と、理沙は息吹に抱き着いた。
稜が呆れる。
「流石は超一流メジャーリーガー。ガチで本物のセレブだ」
「まだMLB1年終わったばかりだけどね」
FA権を獲得する前の最後の年となる来シーズン、息吹は単年32億円の契約を交わしている。今シーズンのスポンサー収入は約18億円(年俸6億円とは別)との推定。来シーズンのスポンサー収入は更に上がると見込まれているので、来年だけで息吹は50億円以上の総収入だ。ただし年俸に関しては、分割での支払いになる。
その次のシーズンからは、資金力のある複数球団による息吹争奪戦が起こり、8~10年で総額数百億円規模の超大型契約が必至という状況だ。
この1年の活躍で、MLBにおける息吹の市場価値は確固たるものとなった。
なお、FA権については高卒プロで8年を超えている希と光は取得済み。2人ともに年3.5億円+出来高変動での5年契約の最中である。光は次で3年目、希は2年目、無事に5年を終えると、再び共に5~7年(5億円ベース)での長期契約の見込みだ。
大卒プロ組は7年での取得になる。つまり怜と理沙は来シーズン完走でFAだ。
理沙はFA宣言予定。自分に興味を示している他球団の評価に興味があるという理由だが、所属球団は戦力として手放すつもりはないと公言済みで、ほぼ間違いなく残留が既定路線。ただし年俸は1億円以上アップで3年以上の複数年契約だろう。
怜はFAについては代理人と共にノーコメントを貫いている。センターのUZRが高く、守備だけでWARを稼げる上に、高い走塁技術に中堅打者以上の打撃成績――センターライン強化に怜を欲しがっている球団(特にDHがあるパリーグ)が、最低でも4球団、獲得に強い意志を示していた。
所属球団側からの公式ソースではないが、7年目が終わった後の内密交渉は既に大筋で合意に達しているという「お漏らし」が、複数の雑誌にリークされていた。それによると7年総額20億円。意図した漏洩で、他球団への牽制と噂されている。
パンパン! と菫が手を叩く。
「はいはい、それじゃあ記念を祝うわよ!」
「まず1人目は白菊。プロ入り後から5年連続の二桁本塁打と通算50本塁打達成、4年連続の200三振、おめでとう!」
「おめでとう」の合唱と拍手が響く。
「ありがとうございます! でも三振記録の方は嬉しくありません!」
デイトナを受け取った白菊は笑顔だ。
詠深が言う。
「50本塁打クリアは目出度いけど、ホームランなかなか増えないね」
「10本、13本、12本、11本、12本だっけ」と、稜。
「これで率があれば立派な成績なんだが」と、怜。
全部が文句なしの特大ホームランで、長打率自体は高い。単打が極端に少なく、三振かツーベース、たまにジャストミートすれば特大ホームランという「ロマン砲」そのものの打撃指標である。
上位打線には置けないが、一発のパワーを「宝くじ的に秘めた」下位打者としては、充分に魅力的な大砲といえよう。
「プロ入り後は一度もクリーンナップを打てていません。ずっと下位打線で打率も2割3分から2割2分を行ったり来たりです。比較的WARが高いので毎年年俸は上がっていたのですが、ついに来季は現状維持の1億円ジャストで止まってしまいました。交渉の際、三振数はこのままでいいからせめて2割4分を超えるか20本打ってくれ、そうでなければこれ以上の年俸は無理と言われました」
「もっともな意見だと思うよ」と、珠姫。
現在のNPBは年間約150試合。白菊はプロ入り2年目以降は、その頑健さもあり全試合スタメンだ。つまり、1試合で必ず1~2三振をしている。プロ入り1年目は、単に出場試合数が少なかったから140三振で済んだというだけだった。
「アンチどころか地元神戸のファンにすら『大和撫子扇風機』という不名誉なニックネームを付けられる始末。光先輩の『ギータ』みたいな語呂の良いニックネームや、理沙先輩みたいな『フジリサ』的なヤツが羨ましいです。しかし、来シーズンは汚名返上の為に打率大台を目指す所存です」
怜が言う。
「いきなり3割は非現実的な目標じゃないか?」
「え? 私にとっての大台は2割5分ですが?」
「「「「「「「 志低っ!! 」」」」」」」
菫は2人目の表彰に移る。
「それでは2人目に行きますよ。2人目は理沙先輩です」
理沙が立ち上がる。
「4年連続の二桁本塁打、通算50本塁打達成、3試合とはいえ4番打者就任、そしてキャリアハイとなる打率2割8分7厘、ホームラン19本、71打点、OPS.885おめでとうございます!」
「おめでとう」の合唱と拍手が響く。
「みんなありがとう」と、理沙は満面の笑顔だ。
受け取ったデイトナ(の箱)小さく掲げる。
本塁打は0本、5本、12本、15本、16本、19本と推移していた。
実は昨シーズンの段階で通算49本だったりする。
「20本の大台は逃したけれど、通算本塁打も68まで伸びて、できれば後2年でプロ入り前からの目標である通算本塁打100をクリアしたいと思うわ」
「来年こそはクリーンナップ定着だな」と、怜。
「いえ、基本的に猛虎の6番サードというチーム内ポジションで可能な限り長くスタメンを守りたいから、クリーンナップはチーム事情による極たまにでいいわ。私の実力で高望みは厳禁よ。6番打者が適正だと思うの」
「「「「「「「 志低っ!! 」」」」」」」
「続いて、3人目はキャプテンです」
注目が怜に集まる。
「通算100盗塁達成、キャリア初の規定3割クリア、ゴールデングラブ賞、そして来シーズンからのキャプテン就任、おめでとうございます!」
「おめでとう」の合唱と拍手が響く。
デイトナを受け取った怜は感無量といった様子だ。
「みんな、ありがとう。本当にありがとう。正直いうと、プロ入りした時は1軍定着なんて無理だと思っていた。レギュラーなんて不可能だと。それがフルシーズン出場で打率3割とか、ゴールデングラブ賞とか、今ここで引退したとしても、もう何も悔いはない」
詠深が若干引き気味で言う。
「あの、キャプテン。まだ若いし、ピークはこれからだし、怪我もないし、今すぐ引退しても悔いないとか、そんな超後ろ向きなコト」
芳乃が言った。
「気弱で自信がないのは昔からですね、キャプテン。大丈夫ですよ、守備・走塁・打撃の全ての指標が毎年向上しています。まだまだ上を目指せますし、今のキャプテンはデータ的にも紛れもなくPNBで一流選手の1人です」
息吹は嬉しく思う。
これで高校・大学・NPBと全て怜はキャプテンだ。
「さあさあ、光先輩にいきますよ。通算250本塁打達成、通算1500本安打達成、通算200盗塁達成、おめでとうございます!」
「おめでとう」の合唱と拍手が響く。
「みんな、ありがとう」と、光。
高卒でプロ入りして1年目から活躍している光は、すでに実働10年のキャリアだ。
来シーズンで通算1000打点達成はほぼ確実としている。本塁打数も通算で289本なので、区切りの300本塁打まで残り11本。
理沙が言う。
「やっぱり高卒で早い段階から成功すると、通算成績は見栄え良くなるわね。名球会入りはほぼ間違いないペースだし。引退まで450本に2500安打はいけそう」
「率以外は積み重ねだからな」と、怜。
光は苦笑しつつ――
「でも個人タイトルは獲れていないんだよね。どの部門も2位から5位で毎年終わるっていうか。2度目のトリプルスリーも失敗しちゃったし」
稜が言う。
「もっと走れば良かったじゃないですか。29盗塁だったし残り1つでしょう」
「27盗塁から失敗しまくってたし、あれ以上はチームに迷惑かけられないよ」
残りは2名だ。
「希の番よ。通算150本塁打達成、通算1500安打達成、そして通算で3度目となるパリーグ首位打者の獲得、おめでとう!」
「おめでとう」の合唱と拍手が響く。
希は照れくさそうだ。
プレゼンターは稜ではなく芳乃が務めた。
杏夏が感嘆する。
「プロ入り9年で首位打者3度、しかも打率3割OPS.850を割った年がゼロ。すでに日本プロ野球史でも歴代屈指のアベレージヒッターですね。名打者ですよ」
稜も同意だ。
「3年に1度の首位打者ってバケモンだよ、バケモン」
実働年数は光より1年少ないが、通算安打数は既に光を超えている。このままのペースで安打を積み重ねれば通算3000安打はほぼ確実である。ただし、本塁打のペースは年間30本ペースを維持している光とは異なり、ここ近年、投手のレベルアップおよび相手に研究されているのか、やや減少傾向にあった。
「それじゃあ、最後の1名は、もちろん息吹」
稜が怜にデイトナを渡す。
息吹は怜の前に立つ。
菫がゆっくりと語る。
「今年からメジャー移籍。日米通算で4年連続となる首位打者&盗塁王、1年目から20本塁打クリア、そして最高出塁率ほか数多くの打撃指標でメジャートップクラスのデータ。メジャー新人王とリーグMVPほか多くの賞を獲得。お疲れ様、そしてお帰り、息吹。――来年もアメリカで頑張って」
今まで一番の拍手の雨。
怜は笑顔で息吹にデイトナを手渡す。
「1年目から首位打者と盗塁王とは思わなかった。本当に嬉しいぞ、息吹」
メジャー移籍当初は大学4年からNPB4年間で守ったショートから、大学1年から3年まで守ったセカンドにコンバートされると予想されていたが、息吹はチームの花形であるショートストップとしてレギュラーを掴む。ショートの日本人メジャーリーガーは、正捕手や本塁打王よりも難易度が高いかもしれない。
「目指しますよ、世界一のリードオフガール。ヨミと珠姫が世界一のバッテリーに輝いたみたいに、私も世界一になってみせます」
そこからは再び焼肉を囲んでの飲み会だ。
自然と元珠川大学組、希・光・芳乃の3人、そして元皇京大学組に分かれている。
ちなみに年明けの自主トレキャンプは、この新越谷高出身の面子では行われない。希と光は中田奈緒が中心となっているYouTubeメンバー主体の自主トレに参加し、息吹たちは皇京大出身を中心とした、怜がまとめ役の自主トレキャンプとなっている。詠深と珠姫のプロ現役時代は、皇京大出身組の自主トレに参加していた。
怜がまとめ役のマスコミ通称・岡田塾は、皇京大卒の1軍選手8名(MLBの息吹含む)と詠深目当ての詩織(ホークスの正捕手、ただし今年は詠深がいなかったので不参加)が例年固定の面子で、他はその年ごとに弟子入りするメンバーは替わる。今回の自主トレキャンプはグアムを予定しており、ベイヒーローズの若手3名、広島コープに育成1位で入団し2年目(支配下登録なし)の新越谷高校卒の若手1名、そして他球団からもプロ入り4年以内の2軍選手3名が参加する。
奈緒がまとめ役のマスコミ通称・中田塾は、YouTube活動での悪評が響いてか、メンバー以外の参加は梁幽館⇒立大⇒楽全の高橋友理のみで、新人や部外者はなかなか寄り付かない有様だった。弟子入りがあっても、1名か2名という不人気ぶりである。弟子入りの少なさに「全く塾じゃない」とアンチにバカにされていた。
大学の寮生活時代を思い出す。
息吹は本音を打ち明けた。
「引退後、できればこの4人で何かしたいです。ヨミたち4人みたいに」
「いいわね、それ」と、理沙。
「資金的にセカンドキャリアの心配なくなりました」と、白菊。
「でも、引退時期はバラバラになるんじゃないか?」と、怜。
「引退が早かった順からセカンドキャリアの実務というか下準備を担当して、それぞれ引退したら事業に合流しましょう。資金は銀行からの融資なしで私が賄えると思います。引退してからの人生の方が長いのだから、焦らずゆっくり――」
「資金面は頼りにしていますよ、息吹さん」
「白菊こそ、このままだと1番引退が早いのはアンタなんだから、引退後の仕事はアンタが一番忙して大変になるわよ」
笑顔を交わし合う4人。
引退後の楽しみは引退後だ。
それまで各自、悔いのない様に現役を駆け抜けよう。
息吹、怜、理沙、白菊の4人はグラスを合わせた。
◆EXTRA:続・YouTuber中田奈緒(後)
遥菜たちの続きの撮影場所は別になる。
チャーターしたバスで移動した先は、埼玉県某所のグラウンド付き大型施設だ。
野球用グラウンド—―というか観客席もある野球場にトレーニングセンターと事務所が併設されている。
その名は『埼玉ベースボールカレッジ』。
奈緒がオーナーであり、メイン出資者である。
他にも遥菜、光、希、陽といった高額年俸者が出資していた。運営は黒字で、協賛企業も多く集まっている。地域密着型として野球教室やイベントも行われていた。
なお依織は現在1軍の2番手捕手として活躍している。スタメンマスクは年40試合ほどなので、年俸は9千万程度だ。ベテランの正捕手が引退すれば1番手捕手に繰り上げになるので、もっと出場機会が増えて年俸は大幅にアップするだろう。どの道、捕手は育成に時間がかかり最もハードなポジション、どのチームでも1軍3番手までは貴重なので、依織の現役期間が最も長いと予想される。
それと陽はファイヤーズからシャイアンズに国内FAで移籍していた。
事務所の玄関先で遥菜たちを出迎えたのは2人組YouTuberだ。
「NPB通算7安打の私、依子と」
「NPB通算77安打の私、由比」
「「 2人合わせてNPB通算777安打の戦力外コンビ! 」」
由比と依子が肩を組んで視聴者にはお馴染みとなっているポーズを華麗に決めた後、カメラマンの「はい、おっけーです」という声。
通算7安打帽子を被り通算7安打Tシャツを着ている依子は、このベースボールカレッジのコーチを務めている。
そして、通算77安打帽子と通算77安打Tシャツという恰好の由比は、このベースボールカレッジの監督だ。加えて2人は、現役引退後は『中田奈緒の埼玉魂』のメインメンバーとしてチャンネルを回している。1軍で活躍している面子は、多忙過ぎてYouTube活動に割ける時間は限られていた。
「お久しぶりです、由比センパイに依子さん」
由比は笑顔だ。
「元気してたか、遥菜。こっち来るのは久しぶりだな」
「なかなか忙しくて。奈緒さんは?」
「それが少し予定より遅れてくるとの事だ」
依子が詠深に挨拶する。
「やあ、本当に久しぶりだな、武田。マジでビッグになったなぁ」
「久保田さん、お久しぶりです。色々と上手く行っている様で何よりですよ」
「私も由比もプロ3年目のシーズンで「上で通用しない」って見切りは付けていたからな。奈緒に相談したらこのベースボールカレッジの設立と、引退後のセカンドキャリアについて話し合ったんだよ。だから戦力外通告に落胆はなかった」
由比が付け加える。
「監督とコーチとしての月給は普通の会社員並みだけれど、YouTuberとしてブレイクしてくれたお陰で、去年は共に年収2億円超えよ。特に2人のコンビとしてのオリジナルグッズがバカ売れで。野球じゃ2億円プレイヤーは無理だったから、これも縁ね。子供たちの指導者として野球に関われているし、幸せだわ」
「元プロ野球選手YouTuberコンビかつ、現役一流NPBプレイヤーが揃っているグループのメンバーっていうのは、レア感があって成功の最大要因だったよ」
光が言う。
「とはいっても、由比さんと依子さんの研究と努力、そして掛け合いと会話のセンスあってこその人気と知名度です。今の成功は間違いなくYouTuberとしての実力ですよ」
バスの中で撮影スタッフから詠深が説明された内容としては、生徒としてのカレッジ生は小学生限定になる。中学に上がってからは、軟式部活かガールズに所属しつつ、要予約で個人レッスンを受けるシステムだ。希望すれば高校生も受講可能である。
また3年後にガールズのチームを立ち上げ予定で、奈緒が現役引退したら彼女を監督としたクラブチームも結成して、独立リーグに参加する計画だ。クラブチームの拠点はこことは別に建設する意向である。ここはあくまで子供たちの為の施設だ。
「ここを拠点とした新しいガールズかぁ」と、詠深は歓心する。
「私と由比はYouTube活動とカレッジ生の面倒をみるので精一杯だから、ガールズのチームには別の監督とコーチそしてマネージャーの招聘が必要になる。設備と資金面では来年からでも立ち上げ可能なんだけど、人選は慎重にって感じだ」
「まだ候補者をピックアップしている段階ね」と、由比。
「武田と山崎が監督とコーチをしてくれてもいいんだぞ。奈緒も大歓迎だろうし」
「すいません。今は指導者は考えていません、私もタマちゃんも」
「やっぱりか。残念だ」
会話している中、カレッジ生の子供たちがやってきた。
パッと見で40名近くいる。学年はバラバラだ。これで全員ではなく、曜日によって人数は上下する。所属しているカレッジ生は約80人ほどだ。中高生のレッスン生は全員で20名前後である。
「由比カントク、依子コーチ、奈緒お姉ちゃんはまだですか?」
「奈緒はまだだが、あの武田詠深がYouTubeの撮影で来てくれたぞ」
歓声をあげて子供たちが詠深に群がる。
「すごい、レジェントよ!」
「世界一のピッチャーだわ」
「本物の武田詠深だよ」
「ワールドシリーズ、痺れました」
「目標にしてます」
「握手して下さい」
「世界最高のピッチャーが本当にきた」
「将来は武田さんみたいになりたいです」
「大人になったら私もメジャーで活躍したい」
「日本人初のサイヤング賞投手」
「憧れです」
「ホントに、あのレジェント武田がいる」
「武田さんの投球をみて野球を始めました」
「伝説のピッチャーだぁ」
その輪には入らなかった小さな子が、光に寄ってきた。
おずおずと上目遣いで挨拶する。
「あの、初めましてギータお姉ちゃん」
「ひょっとして最近カレッジ生になった子?」
「はい、1年生の尾川です。あの」と、真っ白な色紙を光に差し出す。
その色紙を、光の隣にいた遥菜が摘まみ上げて――
「おっ、新入りの子か。どれどれ、この私がサインを書いてやるゾ」
鼻歌混じりの上機嫌でスラスラとサインを書くと、色紙を子供に返す。
すると、遥菜のサイン色紙を受け取った子供が泣き出してしまった。
それに気が付いた子供たちが遥菜を一斉に非難する。
「あ~~、遥菜のヤツ、泣かしたわよ」
「尾川はギータお姉ちゃんのファンなんだよ」
「遥菜、謝れ」
「小1を泣かさないでよ、大人げない」
「遥菜、いい歳した大人のくせに」
「サイテー、遥菜」
「ヒデー」
「ばーか、ばーか、遥菜のバカ、アホ」
「ほらぁ、早く謝りなさいよ、遥菜」
「ったく、これだから遥菜は」
非難轟々の中、遥菜は焦りつつ反論した。
「な、なんだヨ。そんなに責めなくてもいいだろ。悪気はなかったんダ。それに私はライオンズの松井遥菜だゾ。私のサインだってかなり価値あるんだ!」
「ここじゃ遥菜のサインなんて全く価値ないし」
子供たち全員がある場所を指差す。
そこはトレーニング施設のエントランスである。
正確には、風除室の外側ドアの脇だ。
「な、なんだアレは!?」
遥菜が駆け寄ると、折り畳み式の机の上に段ボール箱が置いてある。
その上に位置するガラスには『ご自由にお持ちください』『転売禁止』『球団には許可とっています』という文言が貼り付けられていた。
段ボールの中身は――
大量の遥菜のサイン色紙とサイン入りボールだ。
「ゆ、由比センパイ、これってまさか」
「ベースボールカレッジのスポンサーに配るという名目で遥菜に書いてもらった色紙とボールよ。本当は無料の来場者プレゼントだったの。騙してスマン」
「隙間時間に一所懸命、丁寧に書いたのに」
「カレッジのロゴ入り色紙とロゴ入りボールだからかもしれないけど、思った以上に減らなくて。予定ではすぐに次のを補充するつもりだったのだけど、ご覧の通りよ」
依子が補足する。
「ちなみにライオンズ以外は球団側の許可が下りなくてな」
遥菜は半泣きになって自分のサイングッズを見た。
「ああぁあぁあ。わ、私のサイングッズ。こんなに埃をかぶって。すごい余っているじゃないカ。まるで半額ワゴンセール品だ。こんな現実、信じたくないゾ」
頑張って笑顔を作った遥菜は、小1尾川ちゃんに向き合った。
しゃがんで目線を合わせる。
「そうか。すでにカレッジロゴ入りの私のサイン色紙、もう持っていたんだナ。でも無地の色紙に書いた私のサインもいいかもしれないゾ」
その子は遥菜から気まずそうに視線を逸らす。
遥菜は色々と悟ったが、真実を確認するのは止めた。
光が「ハンカチに書いたサインで良ければ」と、その子にサイン入りハンカチをプレゼントする。「ありがとう、ギータお姉ちゃん」と笑顔になったその子を見て、遥菜は無言でその場を離れた。
「奈緒さん、撮影に入りまーす」
少し予定より遅刻したが、奈緒が到着した。
「奈緒お姉ちゃん!」と、カレッジ生の子供たちが奈緒に駆け寄った。
子供たち1人1人と、奈緒は丁寧に言葉を交わす。とても尊敬され親しまれている。
その様子を見て、詠深が光に訊く。
「あの、光先輩、どうして遥菜ちゃんだけ子供たちにバカにされているんでしょうか?」
「たぶん普段の言動の結果じゃないかな?」
スタッフが大きな段ボール3個を抱えて、詠深の傍まで運んできた。
開けると、中には背番号43のダイヤモンドバレッツのユニフォームがギッシリだ。包装からしても球団が発売している公式レプリカなのが分かる。
「武田さん、展示用1着と視聴者プレゼント用に3着、他は子供たちへのプレゼント用に、ユニフォームにサインをお願いしてよろしいでしょうか。購入時に球団側には話を通してありますので」
「喜んで」と、詠深はサインした。
子供たちは大喜びでサイン入りユニフォームを受け取った。
サインが終わってから詠深は奈緒に挨拶した。
奈緒から右手を差し出し、握手する。
「こうしてお会いするのは、あの夏の試合後以来ですね、武田さん」
「はい。凄く懐かしいです。こういう形で再会できて嬉しいですね、中田さん」
撮影外での軽い会話と打ち合わせを終えて、対談がスタート。
場所はトレーニングセンター内の1階メインフロアだ。
左から順に光、詠深、奈緒、遥菜と並んで丸椅子に座り、色々と語っていく。
後ろで、子供たちも興味深そうに対談を聞いていた。
対談は進み、奈緒が新しい話題を振る。
「ヨミが挙げていた生涯で忘れられない試合ベスト5だけど、1位と2位は納得というか当たり前だが、3位から5位が渋いチョイスだと思った」
「よく言われます」
1位はワールドシリーズ最終戦でパーフェクトを達成した現役最後の試合。
2位はメジャー初勝利を挙げた試合だ。
この2試合を外すとファンが大荒れ必至である。
遥菜が言う。
「で、5位が高校時代で初の全国出場を決めた試合。4位が大学日本一を決めた試合と、アマチュア時代の記念的な区切りの試合だったナ」
光が言う。
「そして第3位だけど、その試合は私もスタンドで観戦していたよ」
「はい、メジャーでの試合は別格にしても、あの試合は私が一生忘れる事がない、本当に嬉しかった、公式戦で初勝利を挙げた記念すべき試合でした」
「3位である、ヨミが高校1年の夏大会で私の母校――梁幽館に勝利した試合。私にとっては高校最後の試合で、あの試合、私は最後の打者だった」
(私もあの試合は大番狂わせだと印象に残っているナ)
「奈緒さんを2度敬遠して、ホームランを打たれちゃったりもしましたね」
「ガールズ時代からNPBまで全ての打席を正確に覚えている私にとっても、ヨミとの2打席は深く記憶に刻み込まれている」
「光栄です。でも凄いですね、全打席を記憶しているなんて」
「ヨミはどれくらい記憶している?」
「私は要所要所の試合で、全部の投球を覚えているとかはないですね。光先輩は奈緒さんみたいに全打席記憶とかしていますか?」
「無理だよ~~。そんなに覚えていないかな。遥菜ちゃんはどれくらい?」
「私はなるべく過去の打席は過去だと、可能な限り忘れる様にしているゾ」
「まあ、考え方はそれぞれだな。ヨミは私との2打席を覚えていてくれているか?」
「勿論です。凄いホームランを打たれちゃったりしましたね。渾身の1球だったんだけどなぁ。実はあの奈緒さんの一発がアマチュア時代の公式戦初被弾だったりします」
「私は打ち取られた最後の打席の印象が強い」
「確かファーストフライでしたよね」
「ああ、3球勝負でいいボールだった」
「そうですそうです、3球勝負だったんですよね」
「あのボールは凄かった。忘れられない。最後は切れ味バツグンのフロントドアのカットボールだった」
「え?」と、詠深。
(ん? 私の記憶が確かならば、最後の球種はストレートだった気がするゾ)
光を見ると、光も「あれ?」という表情だ。
笑顔を取り繕った詠深が奈緒に同調する。
「あのカットボール、私も自画自賛するレベルでしたよ」
(おいおい。中田のヤツ、全打席を記憶しているとかホラだったのかヨ)
どう考えても他の打席と混同して記憶している。
「コースも見事だった。あれはリードした山崎さんも素晴らしいと思う」
「そうですね、あそこでカットボールを要求したタマちゃんに感謝です」
「ストレートを待っていたんだけどなぁ」
「あ、あは、あははは」と、詠深の笑顔は引き攣り気味だ。
ちなみに編集で『最後の球種はフォーシームで中田さんの記憶違いでした』というテロップと当時の映像がカットインで差し込まれるのは、後の話である。
額に汗を浮かべた光は、気まずそうに視線を落とす。
(酷いな。中田のヤツ、ヨミの思い出を木端微塵に汚しやがったゾ)
自分が詠深の立場でも深いショックを受けるだろう、と遥菜は詠深に同情した。
最後の方は微妙な空気のまま対談を終えた。
そしてグラウンドへと移動する。
子供たちも見学だ。
予定通りに、左投げに転向した詠深の球を、光⇒遥菜⇒奈緒の順で打った。
当たり前の結果だが、詠深は手加減されても3人にパカスカ打たれてしまう。フリーバッティング感覚で、ポンポンとピンポン玉のごとくスタンドに運ばれた。
「う~~ん、予想通り簡単にはいきませんね」
「でも草野球ならいい線いくと思う。左とはいえ流石は元メジャーリーガー」
「ちなみにチーム名ですが『たまよみシンコシーズ』です!」
(ダサいチーム名だな、40点)
練習後のチームでのBBQ写真を見せてくれる詠深。
和気あいあいとしており、とても楽しそうだ。
(そうか。もうヨミにとっての野球は仕事でも戦場でもないんだナ)
自分も現役引退後は、あんな風に野球を純粋に楽しみたいと遥菜は思う。
「じゃあ、今度は私がピッチャーでヨミがバッターをやり、新越谷と梁幽館の試合では見られなかった幻の対決を実現、という企画をしようと思う」
「面白そうですね、それ」
「当チャンネルでも好評だった『新越谷と梁幽館の試合の3ランを再現する』企画で、私と希の5打席勝負をヨミは知っているか?」
「その動画、観ましたよ。5打席でいかにあの試合の逆転3ランに近いホームランを再現できるか、っていう企画でしたよね。5打席全部ライトポール際に打って、希ちゃんはやっぱり天才だって驚きました」
「今回は真剣勝負だ。3打席勝負で1安打でもすればヨミの勝ち。なお、ホームランが出た場合は、勝負に使ったバットに私とヨミ、そしてギータと遥菜のサインを入れて視聴者プレゼントにするから、視聴者の皆さんはヨミを是非とも応援してくれ」
「よし、頑張ってホームラン打つぞ~~」
鋭い素振りをしてから、詠深はバッターボックスに入る。
奈緒がマウンドに上がり、捕手は光が務める。
遥菜は審判だ。
「暇を見つけては、バッティングセンターに通っているんですよ」
「ストレートしか投げないから、できればホームラン打ってくれよ、ヨミ」
「はい! ホームラン打つぞ~~」
しかし詠深は呆気なく3打席連続の三振に終わる。
全て甘いコースの真っすぐだったが、バットに掠りもしなかった。
期待外れで申し訳ないと、詠深が謝る。
「あははは、すいません。ダメでした」
「気にするな、次の打席にいくぞ」
「え? 3打席勝負では?」
遥菜は提案する。
「奈緒さん、もう少しスピードを抑えた方が打ち易いかと。編集で途中だけ早送りすれば、視聴者にはハーフスピードだとバレないと思うゾ」
光も同意だ。
「私も遥菜ちゃんの意見に賛成です、奈緒さん」
「ちょっと待って下さい。3打席勝負でしたよね?」
遥菜は苦笑した。
「そういえばヨミはYouTubeでゲストとして呼ばれて対談はやっていても、こういった企画系の動画は初だったナ。こういうのはホームランが出るまで続けて、その打席を3打席目にするんだゾ」
「えぇぇえええええ!?」と、詠深は困惑だ。
「ひ、光先輩、本当ですか?」
「うん。よそのチャンネルはともかくウチはそういうやり方だね。ちなみに希ちゃんと奈緒さんの再現企画も、実際は12打席やっているから」
「え? それって、いわゆるヤラセ、では?」
光は朗らかに笑う。
「ヤラセだなんて、大袈裟だよヨミちゃん。私も最初の1、2年は良心が痛んで葛藤したりもしたけど、大丈夫だよ。こういうものだって慣れるから、大丈夫」
「よし、ヨミも納得したところで、再び第3打席にチャレンジだ」
「でも小学生の子供たちも見ているし、こういうのは」
詠深の声は震えていた。
「ああ、そうだったな。おーい、みんなもっとヨミに声援を頼む」
奈緒のリクエストに子供たちが「はーい!」と元気に応えて、詠深への声援を大きくする。詠深は何かを諦めた感じの顔になり、バッターボックスで構えた。
しかし続けての3打席でも打球を前に飛ばせない。
(子供たちの応援が逆にプレッシャーになっているのかもしれないナ)
遥菜はスタッフに渡された道具を手にし、ホームベース上にそれを設置した。
「あの、遥菜ちゃん、それは?」
「ティーバッティングに変更するゾ。ティーは緑色に塗ってあるからクロマキー合成で透明にできる。インパクトの瞬間からティーバッティングのシーンにシームレスに繋げればホームランを打てるだろ」
「というか、そんな胡散臭い道具を最初から用意しているって」
光が詠深に笑いかける。
「備えあれば憂いなし、だよヨミちゃん。うちのチャンネルの挑戦系企画動画では、こういった小細工、じゃなかった工夫をするのは割と普通だから。普通だよ普通」
「いま小細工って言いませんでした? 光先輩」
「気のせいだよ、ヨミちゃん」
ティーバッティングをする詠深だが、スイングがぎこちなく、どうしてもホームランにならない。ジャストミートしてもフェンス直撃のライナーになる。思った様に打球に角度が付いてくれないのだ。
(期待が重荷になっているのかもしれないナ)
「私が代わるゾ」
遥菜は可能な限り詠深の構えを真似て、詠深のスイングに近い軌道でバットを振る。スコーン、とボールは綺麗な弧を描いてレフトスタンドに放り込まれた。マウンド上の奈緒も、きちんと打球を目で追い、それも後方カメラで撮影されている。
「念のために、もう3発ほど撮っておくか」
「打っておくか、じゃなくて撮っておくか、なんだね」
軽く3発、続けてスタンドインさせて打撃シーンは終わった。
スタッフは「おーけーです。素材的に問題なしです」
詠深は遠慮がちにカメラマンに訊く。
「ええと、毎回こんな事を?」
「ノウハウが足りない頃は、けっこう編集によるイカサマが視聴者にバレて、その度に謝罪動画を出していましたが、ここ2年はほとんどバレていませんから安心して下さい」
奈緒が笑う。
「まあ、謝罪動画は謝罪動画で再生数を稼げるから、美味しいといえば美味しい」
光も笑顔だ。
「これがうちのチャンネルの普通だから。どうしたのヨミちゃん? なんかホラー映画を見ているみたいな顔しているけど。大丈夫大丈夫、そのうち慣れるから」
遥菜は苦笑した。
「ヨミも自分のYouTubeチャンネルを運営してみれば理解できるゾ」
「えっと、じゃあ、本日の撮影はこれで終わり、ですよね?」
(なんだか最初とは違って、ヨミは帰りたがっているナ。まあ、動画撮影は面倒だから私もヨミの気持ちはよく共感できる。いい加減に私も中田から自由になりたいゾ)
スタッフが告げる。
「いえいえ、ホームランを打った後のシーンがまだ残っていますから」
テイク1、スタート!
見物している子供たちが「やったぁ、ホームランだ!」と大歓声だ。
詠深は打席の上で立ち尽くす。
「やったよ、ヨミちゃん!」と、光。
「凄いぞ、ナイスだヨミ!」と、遥菜。
2人が笑顔で詠深に抱き着く。
かなりのオーバーリアクションである。
対して、詠深は茫然としたまま。
はい、カァ~~ト!、とカメラが止まる。
「どうしたヨミ、真面目にやってくれ」
「あ、いえ、ちょっと演技の仕方が分からないというか、カメラが止まった瞬間、みんな揃って真顔に戻るの割と怖いんですが」
「そうか、ならばギータが手本を見せるから参考にしてくれ」
光は右打席に入ると、スイングをした後、軽くバットを放り投げてジャンプ。
オーバーに全身で喜びを表現し「やった、ホームランです奈緒さん!」
遥菜も光に抱き着き、喜びの輪に加わる。
子供たちに手を振る光に対し、子供たちも「ヨミお姉ちゃん、凄い」「やったぁ、ナイス、ホームラン!」「流石は武田さん!」「最高のホームランだよ、ヨミお姉ちゃん」と様々な声援で応える。みんな笑顔笑顔笑顔だ。
光とガッチリ握手した奈緒は「素晴らしいホームランだった、ヨミ」
スタッフが「おっけーです」の声掛け。
次の瞬間、声援がピタリと止む。
光が真顔で言う。
「こんな感じで良いんじゃないかな」
「あの、光先輩、これって子供たちの教育に――」
「大丈夫大丈夫、私も最初の2年くらいは心が擦り切れる感覚がしていたけれど、慣れたら何も感じなくなるから大丈夫。これがウチのチャンネルの普通だから」
「え? それって洗、、の、ぅ」
「大丈夫だよ、ヨミちゃん。もっと自然に笑顔笑顔!」
奈緒は真剣な眼差しで詠深の瞳を見つめ――
「これは決して嘘じゃない。演出だよ演出。視聴者を騙したり欺く意図はゼロだ。ちょっとだけ事実に演出スパイスを加える事により、ほら、いい感じの画になるから」
詠深はぎこちない笑顔で頷く。
「あ、はい。演出ですよね演出!」
「そうだよ、ヨミちゃん。目が笑っていないから、もっと自然に笑顔笑顔!」
テイク3でどうにかOKが出た。
使用したバットにサインをすると、詠深は「ちょっとお世話になっている方から予想外の急用が入って」と、そそくさと帰ってしまった。
「気のせいか、逃げる様に行ってしまったな」と、奈緒。
「ヨミちゃんはタレントとして忙しいですから。あ、私も時間に余裕がないので、これにて撮影はお暇させてもらいます。次回の撮影はもっとゆっくりとしたいですね」
「ギータさんはこれから凛音さんと合流しての雑誌取材だっけ」
「うん。『ベースボールエクスプレス』と『プレイガール』の2誌。インタビューだけでなく写真撮影もあるから、先にスタイリストさんと合流しないと」
「今夜の食事は?」と、遥菜。
「それは予定通りに問題なく。凛音のマネージャーさんがお店を貸し切りでセッティングしてくれているので、皆で合流しましょう」
「うむ、久しぶりにメンバー全員でゆっくりと食事ができるな」
「隠し撮りとドッキリ企画は勘弁して下さいね、奈緒さん。やり過ぎるといい加減に依織ちゃんが本気で怒りますよ」
「スタッフや関係者も含めた忘年会と新年会のスケジュールは、今年も2人共ちゃんと確保しておいてくれよ。去年以上に派手にやるからな」
「勿論です」と、光。
「大丈夫だゾ」と、遥菜。
マネジメント契約を依頼している『アスリートマネジメントSUMIRE』から派遣されている専属マネージャーと、これからの予定の詳細を確認する光。
なお、遥菜と奈緒のマネージャーも後ろに控えているが、今はYouTubeスタッフ主導な上に予定は押していないのでマネージャー2名で雑談していた。
詠深絡みの撮影の次は、子供たちの成長記録的な動画の撮影に入る。カレッジ卒業生の中で何名かは既に名門ガールズで活躍しており、彼女たちをドキュメンタリー的に追っていたりもした。将来は、ここからプロ野球選手を輩出するのが目標だ。
光が退場してから、遥菜は奈緒と共にカレッジ生に特別レッスンした。
咲桜高校の1年生レギュラーで、すでにプロ注である高校生も受講しに来たので、遥菜が付きっきりで指導した。見どころがあるので、今日は時間が許す限り教えたい。
そんな中――
「あの、遥菜」
近づいてきたのは、新カレッジ生である小1尾川女児だ。
「どうしたんだ? あと遥菜じゃなくて遥菜お姉ちゃんだゾ」
「うん、遥菜。これにサイン、お願い」
差し出されたのは、遥菜がティーバッティングでレフトスタンドに打ち込んだボール。
「尾川はギータさんのファンだったろ?」
「でも私はショートでスイッチヒッターだから」
遥菜はボールにサインを書いて、返す。
「ありがと。私の夢はプロ野球選手」
「そうか。プロでショートのレギュラーを獲るのは簡単ではないし、スイッチヒッターを続けるのも大変だから頑張らないとナ」
「でも、ショートで両打ちを貫いてプロで活躍したい」
「楽しみだな。将来は私みたいなスター選手になるのを期待しているゾ」
「ううん、憧れは遥菜じゃなくて、メジャーリーガーの川口息吹さんだから」
「え? あ、そっちは「さん付け」なんだナ」
「それに息吹さんとは違って、遥菜はメジャーでもショートは無理だと思う」
確かに日本人メジャーリーガー初のショートレギュラーは息吹に先を越された。
でも、再来年のシーズンにはメジャーに移籍して、絶対に息吹に負けない活躍をしてやる。日本ではなく世界の松井遥菜になるのだ。
そして、この可愛げのないクソガキの鼻を明かしてやるゾ、と遥菜は誓った。
お し ま い。
注)執筆時間がとれたら、続きを書くかも